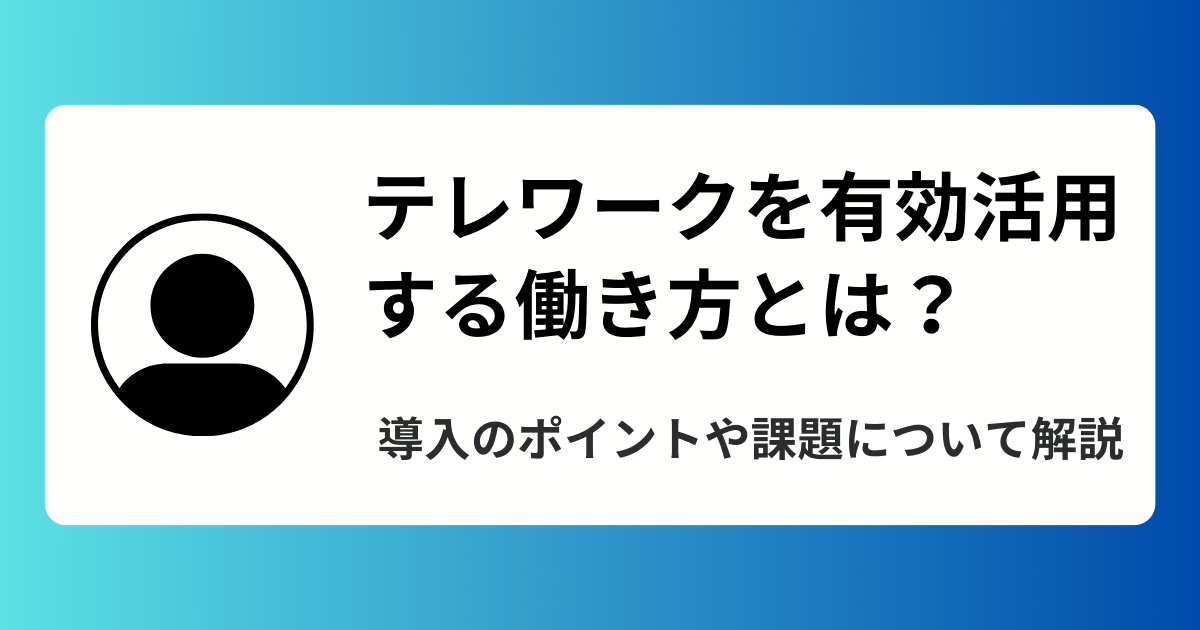郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
コロナ禍の影響によってテレワークの普及率は高まり、多くの企業が導入を進めています。しかし、テレワークのメリットや課題を理解しておかなければ、無駄なコストや余計なトラブルを発生させる可能性もあるでしょう。
本記事では、テレワークの基本と導入時のポイントや課題について解説するため、有効活用の参考にしてください。
テレワークとは
まずはテレワークという言葉の意味について、正確に理解することが重要です。以下を参考に、テレワークについての基本を押さえておきましょう。
「離れて(tele)」と「働く(work)」を組み合わせた造語
テレワークとは、「Tele(遠くの、離れた)」と「Work(働く)」という意味の英語を組み合わせた造語です。基本的に、会社のオフィス以外の場所を使って、勤務・仕事をすることを意味します。
厚生労働省のテレワーク総合ポータルサイトでは、「情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義されています。
テレワークの種類
テレワークにはいくつかの種類があります。また、それぞれに独自の労働スタイルがあるのも特徴です。以下では、テレワークの種類を解説します。
在宅勤務
在宅勤務とは、従業員がそれぞれの自宅にいながら仕事をするスタイルを意味します。テレワークの一種として数えられ、自宅で仕事ができるため、育児や介護などと両立しやすいのが特徴です。
在宅勤務の際には、個別に連絡や進捗確認を行うのではなく、専用のツールを用いて無駄なく情報共有をするのがポイントです。
モバイルワーク
モバイルワークとは、会社のオフィスと自宅以外の場所で働くスタイルのことです。Wi-Fiなどの通信環境が整っている場所や、隙間時間を使って働ける場所が対象となります。
例えばカフェ、ファミレス、移動中の電車内、取引先企業での待機時間を過ごす待合室など、さまざまな場所でモバイルワークが行われています。
サテライトオフィス勤務
サテライトオフィス勤務とは、サテライトオフィスやコワーキングスペースといった、テレワークに特化した場所で働くことです。各種スペースには働きやすい環境が整っているのが特徴で、Wi-Fi完備やドリンクの飲み放題などさまざまなサービスを利用できます。
サテライトオフィス勤務では企業が場所を指定することもあれば、個人が自由に場所を選べるケースもあります。
テレワークとリモートワークの違いとは?
テレワークと同じように使われる言葉に、「リモートワーク」があります。以下では、テレワークとリモートワークの違いを解説します。
テレワークとリモートワークに大きな違いはない
リモートワークとは、「Remote(遠隔)」と「Work(働く)」を組み合わせた言葉です。基本的にリモートワークとテレワークに大きな違いはなく、どちらもオフィスから離れた場所で働くという意味を持ちます。
一方で、リモートワークはテレワークほど明確な定義がなく、比較的新しい言葉としてIT業界や個人事業主の間で使われることが多いです。
企業にとってのテレワーク導入のメリット
テレワークの導入は、企業にとって多くのメリットがあります。以下を参考に、テレワークの魅力をチェックしてみましょう。
経費削減
テレワークの導入は、事業に必要なさまざまな経費の削減につながります。従業員の交通費のほか、オフィスのレンタル料金や光熱費などが削減の対象になるでしょう。
備品のペーパーレス化も進められるため、印刷代なども必要なくなり、事業の効率化も実現します。
人材不足の解消
テレワークを採用すると、会社から遠い場所にいる人材も雇用対象となります。車椅子の利用者など、働き方が限定される人もテレワークなら通常業務で採用可能です。
結果的に人材不足を解消し、事業の拡大を進められます。テレワークを中心とした働き方を推進することで、会社の可能性を広げられるでしょう。
生産性や事業継続性などの向上
テレワークは時間と場所を選ばずに働けるため、従業員が自分のライフスタイルや性質に合った働き方ができます。自由度の高い労働環境を実現できることから、生産性の向上などに期待が可能です。
自然災害などで事業が停止してしまうリスクも、テレワークを主体とすることで避けられます。事業継続性を意識した労働環境の整備にも、テレワークが役立つでしょう。
従業員にとってのテレワーク導入のメリット
テレワークの導入は、従業員にとっても多くのメリットがあります。以下では、従業員側から見たテレワークのメリットを紹介します。
自由な働き方を実現できる
テレワークの導入は、従業員に自由な働き方を提供するきっかけになります。基本的なテレワークのルールさえ守れば、自由に働けるのがメリットです。
自宅やカフェなど気分によって働く場所を変えたり、都市部から地方へ移住したりといった選択肢を従業員に与えられます。
家庭の課題と両立しながら働ける
テレワークは、従業員が家庭で抱えている問題と仕事を両立するためにも役立ちます。例えば、育児や介護などによって働き方が制限されてしまう人でも、テレワークならフルタイムでの仕事が可能です。
家庭の事情で仕方なく離職してしまう人を減らせるため、企業にとってのメリットもあります。
テレワークによるQOLの向上
テレワークの導入は、従業員のQOL向上にもつながります。QOLとはクオリティ・オブ・ライフ(Quality of Life)を意味し、仕事と生活面で充実した日々を過ごせている状態のことを指します。
テレワークは、通勤時間の削減などによってプライベートで使える時間が増えるため、QOLが向上して結果的に仕事へのモチベーションアップが実現するでしょう
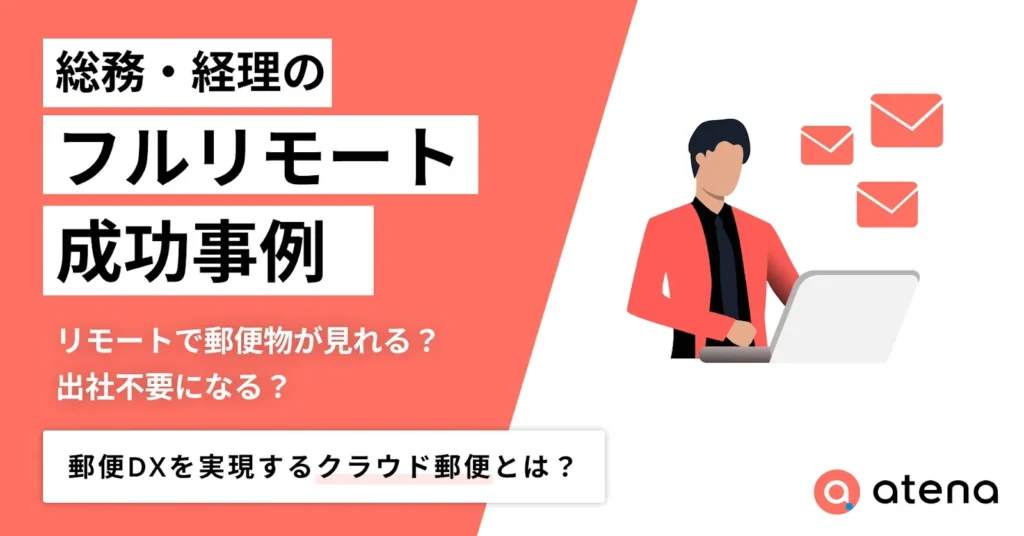
テレワークが持つ現状の課題
テレワークには多くのメリットがありますが、その一方で課題も存在します。事前に課題を把握して、対策が取れるように備えましょう。
勤務や評価の管理が難しくなる
テレワークを導入すると、従業員がきちんと働いているのか確認が難しくなります。オフィスでの仕事のようにチェックする手段が乏しいため、従業員次第ではテレワークによってサボり癖がついてしまう可能性もあるでしょう。
また、仕事への姿勢を参考にする定性評価が難しくなるため、成果で判断する定量評価のための仕組みづくりも必要になります。
セキュリティ上の問題に注意が必要
テレワークの導入時には、セキュリティリスクについても考えなければなりません。従業員ごとに仕事の環境が変わると、企業にとっては情報漏洩などのリスクが高まります。
テレワークの実行時にはセキュリティ向上のためのシステム導入や、従業員個々の意識改革、厳格なルールの制定などが必要です。
テレワーク導入におけるポイント
テレワークの導入時には、意識しておきたいポイントがあります。以下を参考に、テレワークの導入をスムーズに進められるように備えましょう。
各種制度の調整や改定を行う
テレワークの導入時には、それに合わせて社内環境やルールを変える必要があります。
事業で使用するツール、業務フロー、勤務管理や評価制度の方法を、テレワーク用に変更する計画を立てましょう。
いきなりすべての環境を変えるのではなく、テレワークの状況を把握して徐々に必要な変更を加えるのがポイントです。
テレワークに必要なITツールを洗い出す
テレワークの導入時には、さまざまなITツールの利用が必要です。実際にどのようなツールが必要になるのかを、事前に洗い出しておくことがポイントになります。
例えばコミュニケーションツール、Web会議ツール、クラウドの情報共有システムなどから、自社の事業に必要な機能をピックアップしましょう。基本的にテレワークを行う従業員全員が、同じツールを使うようにして効率化を図ります。
テレワークの実施による効果測定を行う
テレワークによって生産性にどのような変化があったのか、定期的に効果測定を行うのもポイントです。先に紹介した通り、テレワークには多くのメリットがある一方で、解決すべき課題もあります。
効率の低下や従業員のストレスにつながる結果が出た場合、原因を追求して解決を図りましょう。
テレワークの普及率について
テレワークを導入している企業は増えていますが、事業全体を完全にテレワーク化するのはまだ容易ではないといえます。多くの会社には「どうしても出社しなければならない理由」があるため、その点を解決できなければ、テレワークの導入も中途半端な形で終わってしまうでしょう。
例えば「郵便物の対応」などが出社の原因となりやすいため、事前に対策を取ってテレワークの普及率を向上させることが重要です。
まとめ
テレワークが必要な環境を整備できれば、事業や従業員の働き方に多くのメリットをもたらします。
この機会にテレワークの基本をチェックして、有効活用する方法を考えてみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は、「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と、今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。