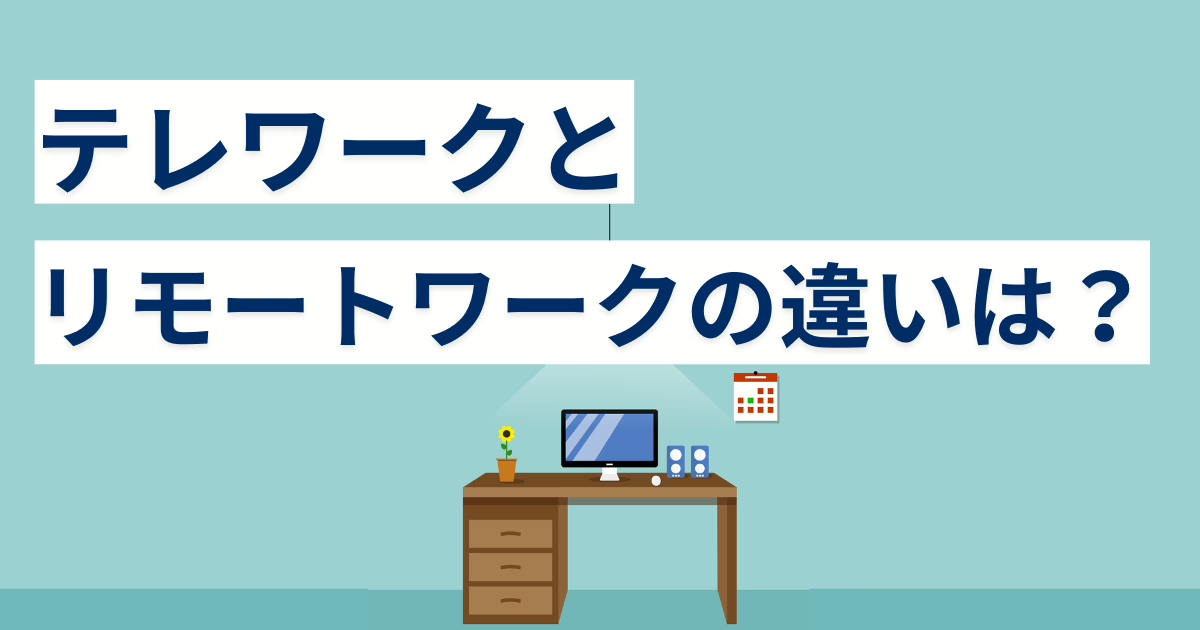郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
昨今、テレワークやリモートワークという言葉を耳にする機会が増えています。しかし、テレワークとリモートワークの違いが明確には分からないという方も多いようです。それぞれの違いを理解しておくことで、自社でどのような働き方を導入すべきかが分かります。
本記事では、テレワークとリモートワークの違いや導入のメリット、テレワークやリモートワークから派生した働き方など、テレワークとリモートワークについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
テレワーク・リモートワークとは
テレワークもリモートワークも、「遠隔で仕事をする」という意味を持つ単語です。これらは働き方改革などを機に、国内でも急速に推進が進められました。そのため、従来型の働き方とは異なり、近年普及してきた働き方といえます。
テレワークとリモートワークの違い
実は、テレワークとリモートワークには明確な違いはありません。しかし、それぞれの単語に若干の違いがあることも事実です。ここでは、テレワークの定義やリモートワークとの違いなどについて見ていきます。
テレワークには明確な定義がある
テレワークには明確な定義が存在しています。厚生労働省によれば、「情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のことをテレワークと呼んでいます。つまり、時間と場所にとらわれない働き方の総称をテレワークと呼びます。
また、テレワークには3種類の働き方がありますが、こちらの定義に関しては後ほど詳しく紹介します。
リモートワークは近年浸透した言葉
テレワークは以前から存在した単語ですが、リモートワークは、近年浸透してきた言葉です。オフィスから離れた場所で働くことを意味する単語「remote(遠隔)」と「work(働く)」の造語です。
実際のところ、テレワークと同じ意味を持っており、明確な定義はありません。ただし、リモートワークはテレワークよりも新しい言葉で、ベンチャー企業やIT企業などを中心に使われはじめたという背景があります。
テレワークとリモートワークに大きな違いはない
上記でも紹介した通り、「オフィスから離れて柔軟に働ける」という意味では、テレワークもリモートワークもさほど違いはありません。そのため、会社でどちらを導入すればよいかわからない場合は、社風に合わせて言葉を選ぶのが効果的でしょう。
ただし、厚生労働省など格式の高い機関ではテレワークが使用されており、明確に区分している様子が伺えます。また、IT企業ではリモートワークを好んで使うという特徴もあります。ただし、一般的にはあまり使い分けはされていないため、どちらを使っても間違いではないでしょう。
テレワーク導入のメリット
テレワークを導入しようと考えている企業は多いです。しかし、テレワークを導入することでどのようなメリットがあるのか、理解していない企業も多数あります。
ここでは、テレワーク導入におけるメリットを2つ紹介します。
コスト削減
企業におけるテレワークのメリットとして最も大きいのは、コストを削減できる点です。オフィスを使用せず働くため、具体的にはオフィスの固定費や光熱費、交通費などを節約できます。また、完全テレワークの企業の場合はオフィスの契約を解除し、固定費なしで会社を運営することも可能です。
加えて、ペーパーレス化を進められるなどのメリットもあるため、テレワーク導入は企業のコスト削減に大きく役立つでしょう。
人材を獲得しやすい
テレワークを導入することで、さまざまな人材を獲得しやすい点も魅力です。例えば、地方に住んでいる方など、通勤に時間がかかることで入社を諦めていた人材でも、リモートワークという形態であれば勤められる可能性があります。また、リモートワークの自由な働き方にメリットを感じている人も多く、優秀な人材が確保できる可能性も高いです。
加えて、まだ小さな子どもを抱えている方や、親の介護であまり外に出れないなどの事情がある方にも仕事を任せられるため、従業員の離職防止にもつながります。
テレワークの定義にある3つの働き方
テレワークは、細分化すると3つの働き方があると言われます。それぞれの働き方で、働き方の特性や働く場所が大きく異なります。ここでは、テレワークの定義に沿って、3つの働き方について解説します。
在宅ワーク
在宅ワークは、オフィスに出社せず自宅で仕事をする勤務形態です。仕事中は原則的に自宅にいることを求められます。例えば、10時出社、6時退社であれば、その時間は基本的に外出することはできません。また、外出する場合には上司の許可を取ることが必要です。
ツールなどを活用して、コミュニケーションを取りながら業務を進めていくのが、在宅ワークの特徴です。
モバイルワーク
モバイルワークとは、移動中に仕事をしたり、自宅とは異なる場所で作業したりすることです。カフェや電車、ホテルで仕事をする場合は、モバイルワークと呼びます。
ノートパソコンやスマホなどのデバイス1つで業務ができる仕事であれば、モバイルワークに対応できるでしょう。ただし、Wi-Fiなどの回線が必要である点は注意が必要です。
サテライトオフィス
サテライトオフィスは、本来のオフィスではなく別でオフィスを構えたり、コワーキングスペースで仕事をしたりする働き方のことを指します。サテライトオフィスは一般的には企業が契約しますが、従業員が個別で借りられるのも特徴です。
在宅勤務やモバイルワークと比較して、仕事ができる環境を整えている点で、生産性向上にも役立つ働き方であるといえるでしょう。
テレワーク・リモートワークから派生した新しい働き方
テレワークやリモートワークの概要を上述しましたが、これらの働き方から派生してできた働き方も存在します。ここでは、テレワークやリモートワークから派生した3つの新しい働き方を紹介します。
ハイブリッドリモートワーク
ハイブリッドリモートワークは、特定の日だけオフィスに出社し、それ以外はリモートで働く勤務体系です。オフィスで会議があるときはオフィスへ出社し、通常業務はリモートワークで行うというケースも一般的です。
コミュニケーションが不足しがちなリモートワークの難点を、うまく解消できる働き方だといえます。
フルタイムリモートワーク
フルタイムリモートワークとは、完全にオフィスへ出勤せず、リモートのみで仕事を完結させる勤務体系のことです。基本的に業務のやりとりはWeb会議や電話、チャットで完結させ、仕事もリモートワークで完結させます。
そのため、出社が難しい従業員にとって非常に働きやすい形態だといえるでしょう。
テンポラリーリモートワーク
テンポラリーリモートワークは、オフィス勤務とリモートワークを組み合わせた働き方のことです。基本はオフィス勤務で、必要に応じてリモートワークを行うという働き方になります。
ハイブリッドリモートワークと比較して「出勤」の割合が高い点が異なり、従業員の都合によってリモートワークに切り替えることが可能です。
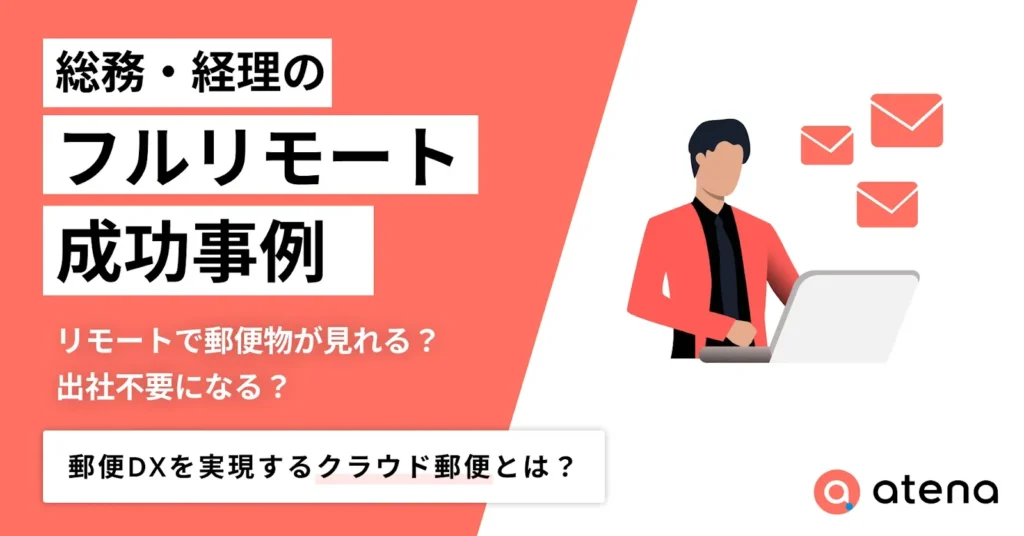
テレワーク・リモートワークが重要視される時代的背景
テレワーク・リモートワークが重要視される時代的背景には、一体どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、3つの要因を紹介します。
新型コロナウィルス蔓延
新型コロナウィルスの感染拡大によって、対面での会話や打ち合わせなどを控えることが求められました。これがリモートやテレワーク導入の走りになったという意見が一般的です。
近年では、ほとんどの業種でリモートワークを推奨する動きが進んでいます。
少子高齢化の促進
少子高齢化の原因は労働環境が悪く、子供を産むことが難しいと判断したことによるものでした。しかし、働き方の多様化によって、主婦や子持ちの方でも働ける状況を生み出すことが可能です。そのため、少子高齢化改善の一貫としてもリモートワークが推奨されています。
厚生労働省の働き方改革
厚生労働省により、ワークライフバランス向上に努めるため、働き方改革が推進されました。その際に、コスト削減や業務効率化などのメリットを提唱した結果、リモートワークに魅力を感じ、導入する企業が多くなったという事実があります。
まとめ
本記事では、テレワークとリモートワークの違いや、導入のメリット、テレワーク・リモートワークから派生した働き方などについて紹介しました。テレワークとリモートワークには大きな違いがありません。そのため、今後導入する企業は、自社の特性に合わせてどちらの名称を使用するか選ぶとよいでしょう。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。

引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況