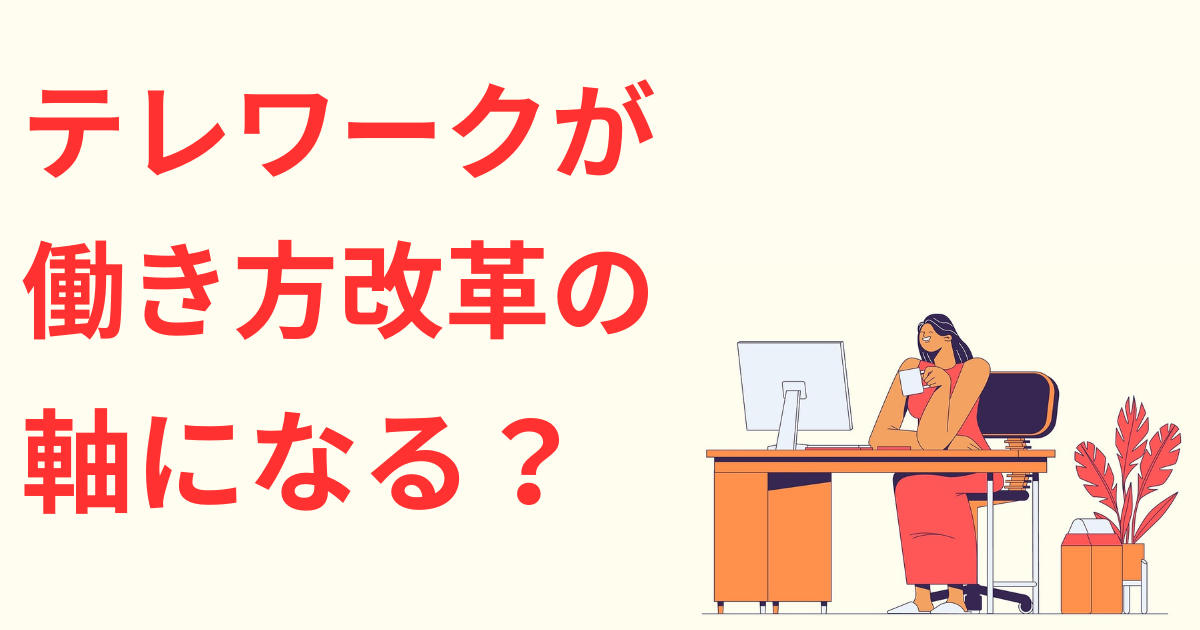郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
現代では、多くの企業が働き方改革に力を入れており、その一環としてテレワークが取り入れられています。テレワークの効果や課題を理解して有効活用することが、働き方改革を進めるきっかけになるでしょう。
本記事では、働き方改革におけるテレワークの重要性やメリット・デメリット、企業にもたらす具体的な変化について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
テレワークとは?
そもそも、テレワークとはどのような働き方を指すのでしょうか。ここでは、概要について簡単に説明します。
社外で業務を行うこと
テレワークとは、会社の外で業務を行うことを指す単語です。「Tele=離れたところで」「Work=働くこと」を合わせた造語で、日本語では「離れたところで行う仕事」という意味があります。
また、日本テレワーク協会では「ICT(情報通信技術)を活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義されています。
在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務など、テレワークにはいくつかの種類がありますが、それらの総称がテレワークと呼ばれます。
テレワークは働き方改革のひとつ
テレワークは、日本政府が推奨している「働き方改革」の一環としても知られています。ここでは、働き方改革の目的や、テレワークが働き方改革につながる理由についてみていきましょう。
働き方改革の目的
働き方改革の目的は、それぞれが理想的な働き方を実現し、柔軟に仕事ができる環境を構築することです。現在、少子高齢化問題によって中間層を活躍させ厚みを持たせることが重要だと考えられています。
政府の掲げる「一億総活躍社会」を目指す戦略のひとつとして、テレワークの導入が期待されているのです。
テレワークは働き方改革を実現できるポテンシャルがある
テレワークは、場所や時間にとらわれず働けるニューノーマルな働き方として知られています。また、この新たな働き方が、働き方改革の実現に大きな一歩を踏み出すと考えられています。
テレワークは、従業員だけでなく、企業にとっても多くのメリットがあり、導入するケースが増えている働き方です。
テレワークは社会的に推進されている労働スタイル
テレワークは社会的に推進が進められている働き方となっています。
政府が主導してテレワークの普及を進めている
テレワークは、政府が先駆けとなって普及を進めている働き方改革です。最終的には、「全労働人口の10%をテレワーカーにする」という目標が掲げられており、従業員のワークライフバランスを整えるとともに、雇用形態の多様化を目指して普及活動が進められています。
事実として総務省は、テレワーク導入のための初期相談や問合せ窓口の設置、セミナーの開催、テレワークマネージャーによる無料コンサルティングなど、様々な施策を実施しており、導入をサポートしているようです。
参照:『世界最先端IT国家創造宣言』
「雇用形態の多様化とワーク・ライフ・バランス(「仕事と生活の調和」)の実現
働き方改革としてテレワークが注目される理由
そもそも、働き方改革としてなぜテレワークが注目されているのでしょうか。ここでは主な理由を2つ紹介します。
従業員が自由な働き方を求めるようになった
テレワークが推進されている要因として最も大きいのは、「働き方改革」という言葉が浸透したことにあります。「働き方改革」の言葉自体から「自由度の高い働き方」というイメージを受ける人が多く、従業員全体が自由度の高い働き方を求めるようになりました。
テレワークのように場所や時間を自由にできる働き方は、従業員にも人気があるため、テレワークの普及が進められているのです。
コロナ渦の影響でテレワークを経験した企業・従業員が増えた
コロナウィルスを発端とした緊急事態宣言によって、テレワークを経験した企業や従業員が増加しました。
実際に、総務省が発表している「令和3年版 情報通信白書|テレワークの実施状況」において、1回目の緊急事態宣言時に17.6%から56.4%までテレワークの実施率が上がたという調査結果が出ています。
また、コロナウィルス蔓延によってテレワークの働き方に対する魅力を知る機会が増え、近年注目度が高まっていることも大きな理由の1つです。
参照:総務省 令和3年版 情報通信白書|テレワークの実施状況
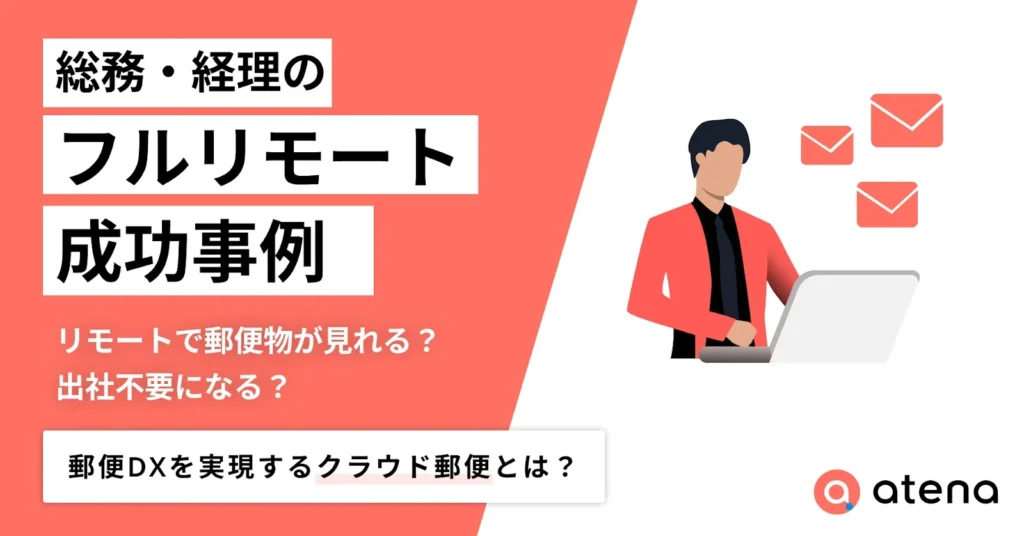
働き方改革におけるテレワークの効果・メリット
働き方改革において、テレワークはどのような効果を与えているのでしょうか。ここでは、働き方改革による3つの効果についてみていきます。
人材の確保と離職率の低下を同時に実現
テレワークによって働き方改革を進めると、新規人材の確保・離職率の低下を同時に実現可能となります。
1つは会社に出社できなくても働くことができ、地方や海外に住む人材も採用できるようになります。
また、2つ目のメリットとして、介護・育児をしながら仕事ができる人が増えるなど、やむを得ない事情で離職する人材の維持にもつながっています。
生産性向上に期待できる
テレワークによる働き方改革においては、従業員の生産性向上につながるケースがほとんどです。
実際に、テレワークを実施している企業において、未導入企業と比較して労働生産性が上がったケースは多く、総務省によって実施された「平成28年通信利用動向調査」によれば、未導入の企業において、1.6倍になったという結果が出ています。
コスト削減につながる
テレワークで出社する従業員が限定されれば、通勤手当などのコストを削減できます。また、従業員にとっても通勤時間を短縮でき、満員電車のストレスから解放されるというメリットがあるでしょう。
働き方改革におけるテレワークの課題・デメリット
大きな恩恵を受けられるテレワークですが、已然として課題が残る部分もあります。ここでは、主な課題を2つ紹介します。
コミュニケーションが希薄になりやすい
テレワークの最も大きな課題は、コミュニケーション不足に陥りやすいという点です。テレワークでは出社の機会が減るため、同僚や上司とコミュニケーションが取りづらくなります。
また、チャットやメールでの連絡がメインとなるため、正確に意図や感情を伝えられないこともあるでしょう。
場合によってはコミュニケーション不足によってトラブルが発生したり、従業員が孤独感に悩まされたりという可能性もあり、テレワークの課題のひとつになっています。
セキュリティ面に懸念がある
テレワークでは場所を問わず作業ができます。会社からすれば外部に社内データを持ち出すことになるため、セキュリティ問題に発展するケースもあるでしょう。
データの盗み見やデバイスの盗難・紛失などによる物理的情報漏洩など、テレワークならではのセキュリティリスクを考慮する必要があります。
テレワークの導入時には助成金が利用できる
テレワークを導入する場合、いくつかの助成金を利用できる場合があります。これらを活用すれば、より効率的にテレワーク導入が進められるでしょう。ここでは、主な助成金を3つ紹介します。
テレワーク促進助成金
都内の中堅・中小企業を対象にした制度が「テレワーク促進助成金」です。一般コースと非正規社員拡充コースがあり、どちらか一方を選択することで、テレワークを実施するための設備経費の支援が受けられます。
助成金の上限は30人以上999人以下の規模で最大250万円(助成率1/2)、2人以上30人未満の規模で最大150万円(助成率2/3)というようなルールが設けられています。詳しくは以下を参照ください。
参照:テレワーク促進助成金
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、厚生労働省が支援している助成金です。機器等導入助成と目標達成助成が設けられており、要件を満たすことで利用可能です。詳細は以下を参照ください。
IT導入補助金
IT導入補助金は中小企業や小規模事業者を対象にした制度で、ITツール導入時に利用できます。
ソフトウェア費用、クラウド利用料、導入関連費などが補助され、通常枠のB類型では最大450万円支援されています。(補助率は1/2以内)詳しくは以下を参照ください。
参照:IT導入補助金
テレワークによって働き方改革を実現する方法
最後に、テレワークによって働き方改革を実現する方法について3つ紹介します。
自社における働き方改革の目的を明確にする
まずは、自社における働き方改革の目的を明確にすることが大切です。なぜなら、働き方改革の目的やゴールは企業によって異なり、目標を明確にしなければ、テレワークを導入しただけで満足してしまうためです。
結果として業務効率化に全く役立たないケースもあるでしょう。まずは、導入時にどのような目標を達成したいか検討しておくことが大切です。
従業員の意見を尊重する
テレワークがしたい従業員もいれば、出社して働きたい従業員もいます。そのため、いきなりテレワークを強制するのではなく、授業員が自分らしい働き方を選択できるようにすることがポイントです。
頭ごなしにテレワークを導入するのではなく、従業員が最も働きやすい環境を整えることが大切です。
テレワーク中のルールを定める
テレワークにおいては、ルールを事前に決定し、専用の就業規則を確立することが大切です。明確なルールのない環境だと、従業員が自由に動いてしまいマネジメントが難しくなるためです。
場合によっては、トラブルに発展することもあるため、まずはテレワークのルールを制定して従業員全員に周知することを意識しましょう。
まとめ
本記事では、働き方改革におけるテレワークの重要性やメリット・デメリット、企業にもたらす具体的な変化について解説しました。テレワークを導入することで働き方改革が進むというメリットもあります。
とはいえ、目標などを定めずにテレワークを導入してしまうと、結果的に業務の効率が下がってしまうこともあります。本記事の内容も参考に、効果のある働き方改革を進められるよう、しっかりと検討した上でテレワークを実施しましょう。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況