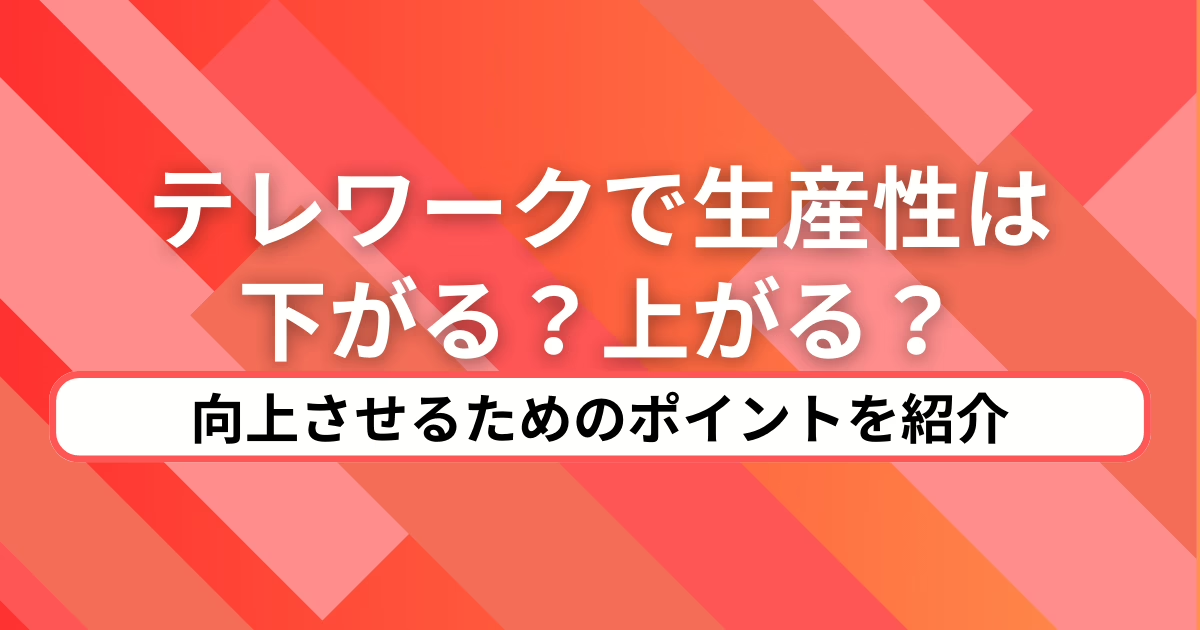郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークは、生産性を高めるための施策として導入されるケースが多いです。ところが、近年の調査ではテレワークを導入したことによって、かえって生産性が下がってしまった企業も珍しくありません。
本記事では、テレワークの生産性が下がる理由や、生産性を上げる方法について紹介します。また、テレワークで生産性を高めた企業の事例についても紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
テレワークのメリット
テレワークの導入には、生産性向上以外にもさまざまなメリットが想定できます。ここでは、テレワークの主なメリットを紹介します。
従業員のワークライフバランスの向上
テレワークの導入は通勤時間の削減につながるため、従業員のワークライフバランス向上に貢献できるのがメリットです。「平成28年 社会生活基本調査」によると、日本の平均通勤時間は往復で1時間19分程度となっています。
テレワークの導入によって、この1時間を従業員が自由に扱えるようになるため、プライベートが充実してストレス解消などの効果にも期待可能です。
オフィスコストを削減できる
テレワークによって出社の機会を減らすことで、オフィスの家賃や電気代の削減、備品の購入費用の削減が可能です。結果的にオフィスの規模を縮小して、最小限のコストだけで会社を運営していくことも想定できるでしょう。
近年は完全なテレワークへの移行を実施して、オフィスを解約する企業も増えています。
人材採用で有利に働く
テレワークを導入することは、「働き方改革を積極的に実施している企業である」というブランドイメージの確立につながります。自由な働き方をしたい人材に注目されやすくなるため、人材採用において有利に働くこともあるでしょう。
テレワークでは働く場所を選ばないため、遠く離れた場所にいる優秀な人材を採用できるケースも考えられます。
テレワークで生産性が下がる理由
テレワークには多くのメリットがある一方で、やり方によっては生産性が下がってしまうリスクもあります。生産性が下がる原因を、以下で解説します。
コミュニケーションが取りづらい
テレワークは自由に働けるメリットがありますが、コミュニケーションが取りづらくなるというデメリットに注意が必要です。
従来のオフィス勤務では、常に同僚や上司が在籍していたため、情報共有やトラブルが起こった際の問題解決がスムーズに行えました。
しかし、テレワークの場合にはチャットの文面で状況を伝えたり、電話で説明したりといった方法がメインです。対面で同僚や上司と接触する機会が減るため、コミュニケーション不足に陥って情報共有に支障が出てしまい、結果的に生産性の低下につながるケースも少なくありません。
従業員の労働環境がわからない
テレワークでは、従業員の詳しい労働状況を把握できないため、会社としてはどのように評価を下せばよいかわからなくなることがあります。従業員としても評価基準が曖昧なままでは、上司から適切な評価を受けられるかわからない不安に苛まれ、ストレスを感じることになるでしょう。
上記の問題が放置されたままだと、チーム全体の士気が低下し、生産性が下がる可能性が高くなります。
プロジェクト進捗状況がわからない
メンバーの業務がどこまで進んでいるか把握しづらいことも、テレワークにおける欠点の一つです。特にチームで動くプロジェクトの場合、進捗状況が管理できないと現状の作業ペースが適切かどうかを判断できなくなる恐れがあるでしょう。
状況がわからないとフォローアップもできないため、問題の対処が後手に回って生産性が低下してしまいます。
自宅に仕事環境が整っていない
テレワークで在宅勤務を行う場合、自宅に仕事の環境が整っていないために生産性が低下するケースもあります。アドビの「COVID-19禍における生産性と在宅勤務に関する調査」によると、日本の労働者の約4割が「在宅勤務は生産性が下がる」と回答しているのが実情です。
例えばシステムのバージョンアップを怠っている従業員に仕事のデータを送付する場合、環境に合わせてデータの保存方法を変更したり、アップデートを促したりといった無駄な業務が増えます。そのほか、パソコンのスペックやインターネットの通信速度などが、仕事をするための基準を下回っているために生産性が低下するケースもあるでしょう。
仕事の切り替えが難しい
テレワークでは気持ちの切り替えが難しく、仕事とプライベートのオン・オフがしづらい点が問題となりやすいです。仕事中なのについ趣味に手を出してしまうことで、生産性が低下する例もあります。
また、業務中に手を抜いても誰の目にも触れないため、サボり癖がつきやすいことも課題となっています。

企業ができるテレワークで生産性を上げる方法
テレワークの生産性を上げる方法を理解することで、上記で解説した課題の解決が図れます。ここでは、企業ができるテレワークの生産性向上方法を解説します。
コミュニケーションツールを導入する
テレワークの生産性を上げるには、Zoom、Microsoft Teams、Slackのようなコミュニケーションツールを導入することがポイントです。基本的にテレワークでは通常業務と比較してコミュニケーション量が減ってしまいます。
そのため専用ツールを導入して、テレワーク中でも会話を円滑に進められる環境を整備することが重要です。
業務可視化ツールを導入する
テレワークにおいては、業務可視化ツールの導入も生産性向上に貢献します。日常の業務を可視化することで、プロジェクト進行状況などを正確に把握可能です。
テレワーク中でも遅れが出ている部分にフォローを回したり、仕事の振り分け方を見直したりできます。コミュニケーション機能やタスク・プロジェクト管理機能など、さまざまなシステムが複合的に搭載されていることも多いのが特徴です。
また、業務可視化ツールは人事評価をする際のデータとしても利用できるため、従業員に正確な評価を与えられます。
テレワークに必要な仕事道具を支給する
テレワークの際には、従業員にとって必要な仕事道具の支給も検討が必要です。従業員の自宅に仕事の道具や環境が整っていない場合、オフィスでの業務と比較して生産性が低下する可能性が高まるでしょう。
例えば日常の業務に耐えられるパソコンを購入したり、従業員の体格に合わせたオフィスチェアを支給したりすると、生産性向上に役立つことがあります。
サテライトオフィスを導入する
テレワークの生産性を高めるには、サテライトオフィスの利用も検討するとよいでしょう。サテライトオフィスとは、職場以外で仕事をする際に利用するコワーキングスペースのことです。
仕事の環境を変えることは、従業員にとって気分転換になり、生産性向上に期待できます。サテライトオフィスは月額料金制で利用できるケースも多いため、必要コストが計算しやすいのもメリットです。
従業員ができるテレワークで生産性を上げる方法
テレワーク中の生産性は、従業員の工夫によっても上げることができます。ここでは、従業員ができる生産性向上方法を紹介します。
積極的にチャットを活用する
テレワークでの生産性を高めるためには、積極的にチャットを活用していく姿勢が重要です。チャットでのコミュニケーションに慣れていないと、スムーズな意思疎通ができず、業務が停滞する時間が増えてしまいます。
積極的にチャットを活用することで、コミュニケーションを活性化して円滑な業務を可能とできるでしょう。雑談専用の部屋などを設けておくことで、仕事以外の会話がしやすくなるため、従業員同士の関係性を円滑に保ちやすくなります。
体の負担を軽減させるオフィス家具を利用する
テレワークの環境が整っていない場合には、自宅のダイニングテーブル等で作業をすることもあります。しかし、仕事向きではない環境での長時間業務は、肩こりや腰痛の原因になり、結果的に生産性を下げることにもつながるでしょう。
安価なオフィスチェアは一万円未満から購入できるため、できるだけ体への負担が少ないものを購入するのがおすすめです。
会社のサテライトオフィスを積極的に活用する
企業がサテライトオフィスを導入している場合には、積極的に活用することが生産性向上につながります。自宅以外の場所で仕事をすることは、気分転換になるだけでなく、普段の仕事のやり方を見直すきっかけにもなるでしょう。
テレワークで生産性を向上させた事例
テレワークによって生産性を向上させた企業の事例は、ここ数年多く見られるようになりました。ここでは、実際にテレワークで生産性を向上させた企業の事例を、3つご紹介します。
ソフトバンクの動画面接
スマホ事業などで知られるソフトバンクは、新卒採用選考を動画面接で行なったことで話題となりました。具体的には提示された質問に対して回答した動画を撮影し、企業のプラットフォームにアップロードするという形を採用しています。
採用にかかる時間の短縮だけでなく、面接者と志望者の負担の軽減にもつながっている点が特徴です。
日本航空株式会社のフリーアドレス導入
JALは2015年4月から在宅勤務制度を導入し、その後フリーアドレス制のオフィスを構えて従業員の働き方を支援しています。従業員が働く時間や労働環境を自由に選択できるため、モチベーションアップからの生産性向上につなげられると考えられるでしょう。
上記制度の実施によって、時間外・休日労働時間の月間平均が、2016年は12.1時間だったのに対し、2017年は7.9時間に減少したというデータも出ています。従業員のプライベートの充実にも貢献できている点も、この事例の特徴です。
株式会社ベネッセホールディングスのテレワーク@Home
ベネッセホールディングスでは、従業員が月5日まで取得できる「終日在宅勤務」と、月の取得制限が設けられていない「部分在宅勤務」という制度が採用されています。終日在宅勤務では限られた時間の中で業務を終えられるよう、基本的に残業なしであることが特徴です。
従業員の生産性向上のために専用の制度を企業側から提供した事例として、注目されています。
まとめ
テレワークの生産性を高めるには、さまざまな工夫が必要です。会社側と従業員側でそれぞれできることが異なるため、この機会に生産性を高めるための方法をチェックしてみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。