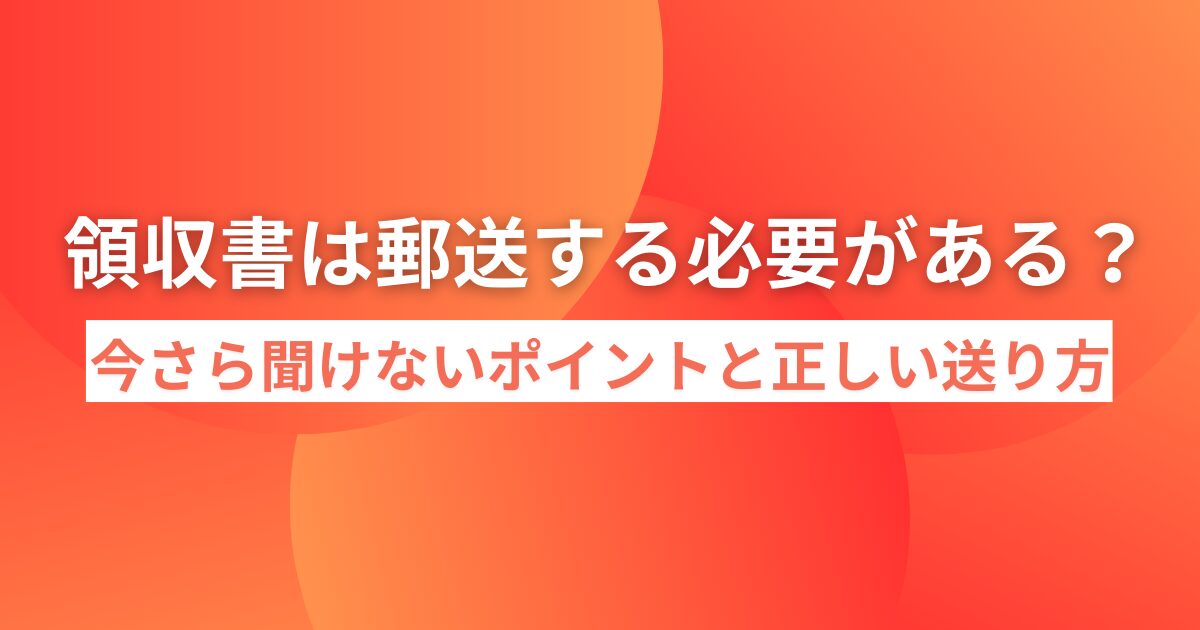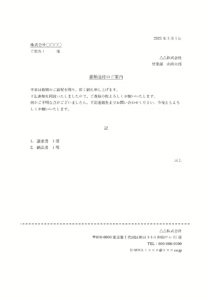領収書の取り扱いにお困りではありませんか?
「電子化できるはずだから郵送は不要では?」と思いつつも、取引先から紙の領収書を求められたり、「本当に郵送して大丈夫?」と疑問を感じたりしている方も多いでしょう。
本記事では、領収書は郵送が必要なケースと不要なケースの見分け方、そして郵送方法の具体的な手順を分かりやすく解説します。さらに記事の最後では、総務の業務効率化をサポートするツール「atena」のご紹介もします。ぜひ最後までご覧ください!
領収書の郵送は必要?
「領収書はわざわざ紙で送る必要があるの?」と疑問を抱く方は少なくありません。ここでは、郵送が必要な場面と不要となるケースの違いを見ていきましょう。
取引先が電子取引に対応しているか
- 電子帳簿保存法の改正
2022年に電子帳簿保存法が大幅に改正され、電子取引データの保存や電子化の要件が緩和されました。これにより、取引先が電子取引に対応している場合は、PDFなどの電子データで領収書を受け渡しすることが可能になっています。 - 電子取引の場合は郵送不要
相手先から「電子データでも問題ない」という回答を得られるのであれば、領収書を郵送する必要はありません。データでやり取りするため、コストや手間も削減できるうえ、紛失リスクも減らせます。
依然として紙で管理している企業も多い
- 実は紙文化が根強い現場
一方で、電子化が進んでいるといっても、まだまだ紙でのやり取りを重視している企業は少なくありません。リコージャパン株式会社によると、2023年時点で請求書や領収書を完全に電子化している企業は半数程度にとどまるという調査結果が発表されました。 - 税務署対応のために原本が必要な場合
税務上の確認のために原本保管を徹底している企業や、内部監査で紙の原本を要求される企業も依然として多数存在します。取引先の方針を確認したうえで、紙の領収書が必要なのかどうかを見極めることが大切です。
領収書の郵送方法
領収書の原本を相手に送る場合、普通郵便だけでなく、さまざまな送付方法があります。ここでは費用や補償、追跡サービスの有無などを比較しながら解説します。

普通郵便
- メリット
- 郵便ポストから手軽に切手を貼って発送できる
- コストが最も安い
- デメリット
- 追跡サービスや補償がないため、紛失リスクがある
- 重要書類の送付にはやや不安が残る
特定記録
- メリット
- 郵便物を差し出した事実を追跡できる(追跡番号が発行される)
- 料金は基本料金 + 210円で対応可
- デメリット
- 補償はないため、万が一の紛失に対する賠償はない
- 相手がきちんと受け取ったかどうかを証明するわけではない(配達証明ではない)
簡易書留
- メリット
- 受領印をもらい、確実に相手に届けた証拠を残せる
- 5万円までの実損額を補償してくれるため、重要書類でも安心
- デメリット
- 送料が定形郵便より高い(基本料金+350円)
- 郵便窓口での手続きが必要(ポスト投函は不可)
レターパックライト
- メリット
- A4サイズまで対応、薄い書類なら封筒いらずで便利
- 430円で追跡サービスが利用でき、ポスト投函で完結できる
- デメリット
- 補償が付いていないため、万が一紛失した場合に補償はない
- 厚さ3cm・重量4kgまでの制限がある
送付状について
領収書を郵送する際は、相手に「何を送ったのか」を明確に伝えるために、送付状を同封するのが一般的です。ビジネスマナーとしても送付状があると丁寧な印象を与えられます。
記載すべき情報
- 宛名・送付日
- 取引先の企業名、担当者名
- 送付日(○年○月○日)
- 送付する書類の概要
- 「領収書(○○円分)」
- 「請求書や納品書と一緒に同封している場合はその品目」
- 差出人情報
- 自社名、担当者名、連絡先(電話番号・メールアドレス)
- 緊急連絡先があると親切
文例
送る前のチェックリスト
書類を送った後になって「ミスに気づいた」「領収書をコピーしていなかった」など、トラブルが起きると後処理が大変です。以下のチェックリストを活用し、安全に手続きを進めましょう。
領収書の控えを保管しておく
- コピーやスキャンで電子化
- 紙の領収書を郵送する前に、必ずコピーやスキャンを取りましょう。
- 紛失や誤送付があった場合にも対応しやすくなります。
メールで連絡を入れる
- 「書類をお送りしました」と連絡する
- 領収書を発送した当日に、相手先に「本日郵送しました」と一報を入れると良いでしょう。
- 先方も到着予定日を把握でき、スムーズに受領確認ができます。
送付状を同封する
- ビジネスマナーの基本
- 書類のみでは、「これは何の書類か?」「どの担当者が送ったか?」が分かりづらい場合があります。
- 送付状を同封すると、トラブル回避につながり安心です。
まとめ
領収書の郵送は、相手企業が紙で管理しているケースや、税務署対応で原本が求められる場合には有効です。一方で、電子帳簿保存法の改正に伴い、電子データでのやり取りが可能になっている取引先なら郵送は不要かもしれません。まずは相手の状況を確認しつつ、適切な方法を選びましょう。
郵送を選ぶ際は、普通郵便から簡易書留、レターパックライトなど、費用・補償の有無・追跡サービスを比べて最適なものを利用してください。送付状やチェックリストも活用し、ビジネス上のトラブルを防ぎましょう。
総務業務の効率化に「atena」を活用しませんか?
書類の郵送業務や管理には、多くの時間と労力がかかります。そこでおすすめしたいのが、総務の業務効率化ツール「atena」です。「atena」は、郵送物の受付・管理をデジタル化し、書類をスキャンして共有するなどの機能を提供しているため、オフィスにいなくても郵送物をリアルタイムに確認できます。
これにより、書類の受け渡しや管理にかかる手間を大幅に削減し、本来注力すべき業務に集中できます。「領収書が届いているはずなのに確認に時間がかかる…」といった悩みを解消し、業務効率を格段に向上させませんか?
ぜひ「atena」の導入をご検討ください。詳細や導入事例は公式サイトからお問い合わせいただけます。総務業務の効率化を実現し、煩雑な郵送業務の負担から解放されましょう!