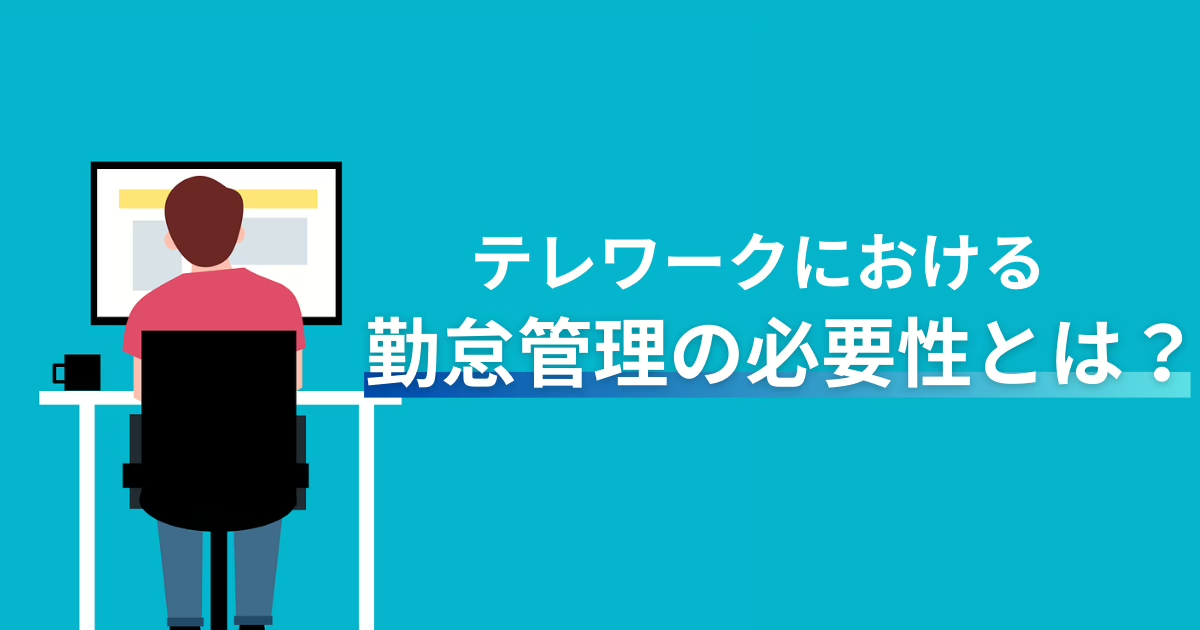郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークは、従業員の勤怠管理が必要です。正確な勤怠管理ができないと、テレワークにおいて課題が生まれてしまいます。
本記事ではテレワークにおける勤怠管理の必要性と課題、その解決法について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
テレワークにおける勤怠管理の必要性とは?
結論から述べると、テレワークにおいて勤怠管理は必要です。テレワークにおいて勤怠管理が重要な理由は主に2つあります。
テレワークでは従業員の姿が見えない
テレワーク中は、従業員の働いている姿が見えません。場合によっては、従業員が手を抜いて業務に取り組んでいることもあるでしょう。
そのため、勤怠管理を徹底して、真剣に業務に取り組んでいるかを確認できる体制づくりは必要です。
信頼関係を崩さないためにも勤怠管理が必要
勤怠管理が曖昧だと、従業員が「丁寧な仕事をしているか」「Webサイトを閲覧していないか」などと疑念を持ってしまうでしょう。
また、従業員側も人事評価に対して「仕事をきちんと見てくれるのか」と不安になってしまうことも考えられます。そのため、適切な勤怠管理の環境づくりは不可欠です。
テレワークで勤怠管理が必要とされる背景
テレワークが重視される背景には2つの理由があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
従業員を公平に扱うために欠かせない
テレワークを実施する際、従業員を公平に扱う必要があります。具体的には、従業員の能力によって人事評価を下してしまうことは大きな問題だといえるでしょう。
勤怠管理を実施すれば、業務時間や出社日数を把握でき、公平な評価が行えるようになります。その結果、従業員は仕事に対するモチベーションを欠くことなく、仕事にやりがいを感じてもらえる可能性が高まります。
勤怠管理がテレワーク中心の事業展開を可能とする
勤怠管理の環境を整備することで、テレワークを前提として事業を展開することも可能です。従来のように印刷や交通費にコストが掛からなかったり、従業員の通勤時間を減らしたりできるというメリットがあります。
今後さらに多くの業務をテレワーク化するのなら、しっかりとした勤怠管理ができないといけないことは理解しておきましょう。
テレワークにおける勤怠管理の課題
これからテレワークを実施しようと考えている企業においては、大きく4つの課題に悩まされることが多いでしょう。それぞれの課題について詳しく見ていきます。
進捗が把握しづらい
テレワークの勤怠管理では、個々の業務の進捗を把握しづらいという難点があります。仮に状況が理解できていない場合には、納期が近くなってから、従業員の仕事が遅れていることを発見してしまうケースもあるでしょう。
勤怠管理においては、現状の進捗を報告する時間を作ることも必要です。
テレワーク中の業務量や勤務態度を評価できない
テレワークでは、業務量や勤務態度を正確に把握することは難しく、人事評価に活かせないというデメリットがあります。
その結果、仕事の評価は成果主義になり、人事評価の方法を大きく変更する必要が出てくるかもしれません。従業員によっては、人事評価方法の変更が不満となり、離職につながるケースが発生する場合もあります。
時間外労働や休日出勤の管理が難しい
テレワークにおいては、時間外労働や休日出勤の管理が難しくなります。例えば、従業員が自発的に残業をすると、残業代を支払わなければならないため給料として支払うコストが増えてしまいます。
また、残業した時間を証明することも難しく、ルールが曖昧だと残業代の支払いでトラブルに至ることもあるため、注意が必要です。
労災認定の判断がしづらい
テレワーク中に怪我をした場合、労災認定となるかの判断が難しい点も課題です。仕事が原因で怪我をしたのか、もしくは仕事中に関係のないことをして怪我をしたのかで、対応が変わってくるためです。プライベートと仕事が混在している、テレワークならではの課題といえるでしょう。
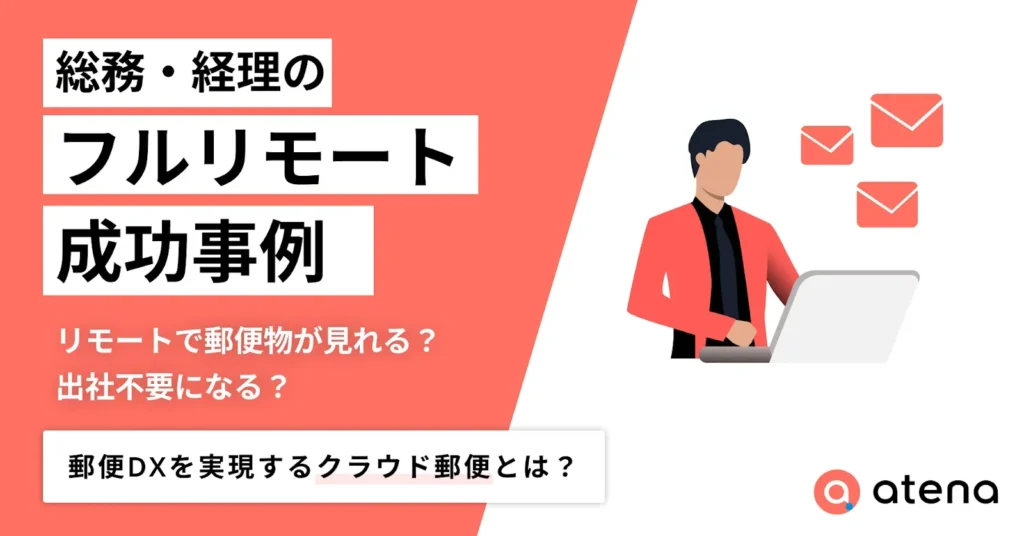
テレワークにおける勤怠管理の課題を解決する方法
テレワークにおいて、勤怠管理の課題を感じたら、どのように解決すればよいのでしょうか。ここでは、4つの対策方法について紹介します。
コミュニケーションが取りやすい環境を構築する
テレワークの環境で最も重要なのが、コミュニケーションが取りやすい環境をつくり、従業員が働いていることを確認できるようにすることです。チームで仕事をしていることが、結果的にモチベーションの維持にもつながります。
例えば、定時にオンラインミーティングを行うなど、1日の仕事を振り返る機会をつくり、コミュニケーションを取ることがポイントです。
残業や休日出勤は申告制にする
残業や休日出勤は、事前に申告が必要としてルールを改定することも重要な心がけです。申告制にすれば、何時間残業をするのかが事前に把握できるため、残業代を計算しやすくなり、無駄なコストを支払う必要がありません。
また、無駄な残業だと会社側が判断した場合には、申請を却下してコストを抑えることも可能になります。
従業員が上司に直接コンタクトを取れるルートを設置する
集団でコミュニケーションを取れる場だけでなく、上司やマネジメント担当者に直接コンタクトを取れるようにしておくことも重要です。
他の人に状況を知られずに話ができるようにしておけば、悩みを打ち明けやすくなり、改善に導ける可能性が高まります。
勤怠管理の専用システムを導入する
従業員の勤怠管理を人間の手で行うと、申告ミスが発生してしまいます。勤怠管理専用のツールを導入することで、スムーズに管理ができるようになるはずです。
勤怠管理システムのツール選びについては、次の項目で紹介しますが、正しいツールを選ぶことで、担当者の負担を軽減し、業務効率化につなげられます。
テレワークで役立つ勤怠管理ツールの選び方
テレワークに役立つ勤怠管理ツールを選ぶ場合、次の3つの方法があります。それぞれ詳しく解説します。
勤務時間を詳細に記録できるか
まずは、従業員ごとの業務時間を詳細まで記録できるものを選びましょう。業務時間を精密に把握し、月末に集計できるシステムがあれば、簡単に勤怠管理が行えるためです。
また、残業時間や割増賃金などにも対応できる、柔軟性の高い勤怠管理ツールを選ぶことが大切です。
給与システムと連携できるか
給与を算出するシステムと連携ができれば、勤怠状況に合わせて給料を自動計算してくれます。自動計算であれば集計ミスがなくなり、従業員とのトラブルを未然に防げます。
また、給与システムとうまく連携が取れれば、業務効率化にもつながるはずです。
在席と離席がチェックできるか
テレワークにおいては、在席と離席が区別できるシステムも重要です。休憩中や業務時間外は離席にしておくことで、プライベートに連絡をすることがなくなり、従業員の働きやすさ向上につながるためです。
もちろん、休憩時間を計測できれば正しい実働時間がわかり、正確に給与計算ができる点でも役立ちます。
申請と承認が行えるか
有休の利用申請と、その承認が行えるシステムがあれば、便利かつわかりやすく管理することが可能です。
また、従業員の休暇状況を管理しやすくなるだけでなく、有休の利用を申請しやすく、有休消化率UPにもつながります。
テレワークでも直感的に利用できるか
勤怠管理システムは、多くの従業員が利用するツールとなります。そのため、直感的に使用できるものを選ぶことが大切です。
具体的には、難しい操作が必要なものは避け、シンプルなUIを採用しているものを選ぶことで、勤怠管理システムがスムーズに浸透していくでしょう。
まとめ
本記事ではテレワークにおける勤怠管理の必要性と課題、その解決法について紹介しました。テレワークにおいて勤怠管理は必要不可欠な業務です。システムを導入することで効率よく勤怠管理が行えるため、本記事の内容も参考にシステム導入を検討してみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況