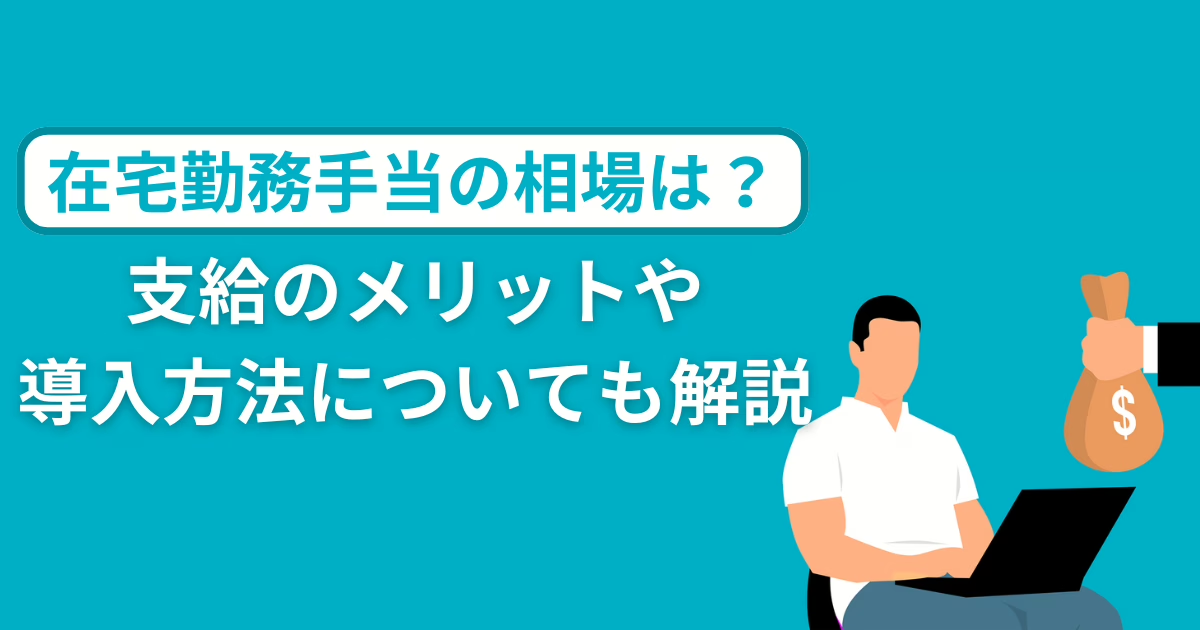郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
社会情勢の変化によって在宅勤務が普及した昨今、従業員に対して「在宅勤務手当」を支給するケースが増えています。在宅勤務手当の支給には多くのメリットがあるため、相場を確認した上で導入することがおすすめです。
本記事では、在宅勤務手当の相場とメリットや導入方法・注意点について解説します。
在宅勤務手当とは?
そもそも、「在宅勤務手当」とはどのような制度を指すのでしょうか。まずは在宅勤務手当の基本的概要について、以下で解説します。
在宅勤務を行う従業員に対して支給される手当
在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う従業員を対象に支給される手当です。基本的に在宅勤務に必要な諸経費を支援するために実施され、従業員の負担を軽減する目的で導入されます。
例えば、業務中の光熱費や通信費、サテライトオフィスの利用料金などを補助することが役割です。
なぜ在宅勤務手当に注目が集まっているのか?
在宅勤務をはじめとした働き方改革が進むなか、在宅勤務手当には多くの企業が注目しています。以下では、在宅勤務手当が注目される理由について解説します。
在宅勤務を導入する際に重要視される
在宅勤務手当は、在宅勤務を導入する際の仕組みのひとつとして重要視されるケースが多いです。近年はコロナウィルスなどの影響で在宅勤務が普及し、社会的にも推奨する流れになっています。
しかし、在宅勤務は多くのメリットを持つ一方で、従業員に光熱費や仕事の場所を確保するためのコストを強いるという課題もあるのが事実です。そのため在宅勤務手当を支給して、会社が従業員のコストをカバーすることが求められるようになっています。
通勤手当の代わりとして採用する事例も増えている
在宅勤務手当は、通勤手当の代わりとして採用される事例も多いです。従業員の働き方が在宅勤務に切り替わると、通勤の必要がなくなります。
その結果、会社も通勤手当を支給する必要がなくなり、両方がメリットを得る結果になるでしょう。通勤手当の分をそのまま在宅勤務手当に回せるため、必要な予算が比較的確保しやすい点も注目される理由となっています。
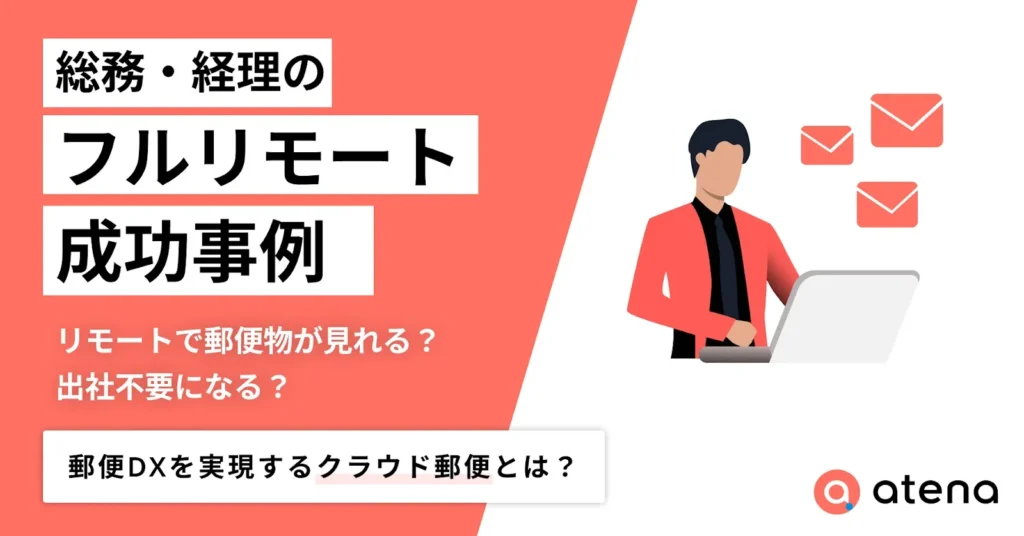
在宅勤務手当の導入におけるメリット
在宅勤務手当の支給および制度の導入には、多くのメリットがあります。以下を参考に、具体的にどのようなメリットがあるのかをチェックしてみましょう。
働き方改革につながる
在宅勤務手当の導入は、社内の働き方改革を進めるきっかけになる点がメリットです。在宅勤務手当によるサポートがあると、従業員はいまの働き方から在宅勤務を選択しやすくなります。
将来的には出社と在宅勤務を従業員が自由に選べるようになり、働き方が多様化した環境の構築も可能となるでしょう。在宅勤務手当は、将来の環境づくりのきっかけになる点も評価されています。
従業員のモチベーション低下を防げる
在宅勤務手当の支給は、在宅勤務にかかるコストを会社がカバーする形になるため、従業員のモチベーション低下を防げるのがメリットです。従業員が在宅勤務中の経費を負担することになると、志望者が減少する可能性があります。
支給された在宅勤務手当は自由に使えるため、事実上の年収アップにつながる点もメリットになるでしょう。
コスト削減になることも
在宅勤務手当は、業務に必要なコストの削減につながるケースもあります。通勤手当の場合、従業員の通勤距離次第では高額になってしまい、毎月のコストを高騰させる要因となり得るでしょう。
一方で、在宅勤務手当の支給額には、従業員の住む場所や通勤距離は関係ありません。遠距離に自宅がある従業員が多い会社の場合、毎月の通勤にかけるコスト(手当)を在宅勤務手当の導入で削減できます。
在宅勤務手当の相場は?
在宅勤務手当を導入する際には、支給額の相場を把握しておく必要があります。以下を参考に、在宅勤務手当の相場を確認してみてください。
在宅勤務手当の相場は3,000〜10,000円前後
在宅勤務手当の相場は、だいたい3,000〜10,000円前後に設定されることが多いです。基本的には光熱費やネット回線の利用料、その他在宅勤務に欠かせない環境の構築費などをまかなえる金額を計算して算出されます。
毎月決まった金額を支給するばかりではなく、月々の変動を考慮して半年に1度まとめて支給する形を取る会社も多いです。
在宅勤務手当の具体例
在宅勤務手当の支給額は、企業ごとにさまざまな事例があります。相場を把握するために、いくつかの企業の事例をご紹介します。

在宅勤務手当の相場を基準に支給額を決める
上記のように、企業によって在宅勤務手当の支給方法や金額は変わります。そのため、自社にとって最適な金額を相場を基準に見つけ出すことが、導入におけるポイントです。
導入時には支給額に上限を設けたり、在宅勤務の環境を整える最初の段階で特別手当を支給したりすることも考えられます。また、支給額は1度決めたらそのまま固定するのではなく、社会情勢や会社の状況に応じて柔軟に変更していくことも必要です。
在宅勤務手当における2つの支給方法
在宅勤務手当の支給方法には、大きく2つのタイプがあります。それぞれの特徴を確認し、どちらを採用するか検討しておきましょう。
在宅勤務手当の支給方法①現金支給
在宅勤務手当の支給方法として一般的な方法が、現金支給です。給与にプラスする形で現金を支給するだけなので、処理が簡単に済む点が特徴となっています。
毎月決まった金額を支給することもあれば、従業員ごとに光熱費や通信費を確認し、毎回精算する方法もあります。
在宅勤務手当の支給方法②現物支給
在宅勤務手当では、現物支給も方法のひとつとして検討されます。在宅勤務に必要な機材などを現物で支給し、快適に仕事をする環境の構築をサポートすることが主な目的です。
会社の意図しない使い方を防止し、必要な環境を全ての従業員に対して公平に提供できます。一方で、支給が数回で終了してしまうため、従業員から不満が出やすい点がデメリットです。
在宅勤務手当の導入方法
在宅勤務手当を導入する際には、いくつかの手順を踏む必要があります。以下では、在宅勤務手当の導入方法について解説します。
在宅勤務手当に関する基本的なルールを作る
在宅勤務手当の導入時には、まず基本となるルール作りを行います。例えば支給額の決定方法や、支給対象となる従業員の条件などを明確にすることが考えられるでしょう。
支給における手続きの流れや、支給対象として認められない事例などを事前に提示することで、混乱を避けることが可能です。
従業員から在宅勤務に関する情報をヒアリングする
在宅勤務手当を導入するのなら、在宅勤務における不便な点や金銭的な問題点などを、従業員から直接ヒアリングするのがポイントです。実際に在宅勤務を行う、もしくは既に実行している従業員の意見を聞くことで、必要な金額の相場が確認できます。
定期的なヒアリングを参考に、支給方法やルールの改定などを行うことも考えられるでしょう。
在宅勤務手当の注意点
在宅勤務手当を導入する際には、いくつかの注意点を把握することも重要です。以下では、在宅勤務手当の導入における注意点を解説します。
在宅勤務手当についての情報を正確に提示する
在宅勤務手当の導入時には、その情報を正確に従業員へと提示する必要があります。従業員全員に申請条件や受給のルールを説明し、共有する機会を作りましょう。
在宅勤務手当について理解しきれていない従業員がいる状態で支給をはじめると、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。説明後も、従業員が好きなタイミングで詳細を確認できるように、常に最新の情報を提供できる環境を構築することも検討されます。
在宅勤務手当は課税対象となる
在宅勤務手当は、支給された全額が課税対象となる点に注意が必要です。通勤手当の場合、月15万円を上限に非課税となる制度を利用できますが、在宅勤務手当にはそのような措置がありません。
在宅勤務手当を受け取ると、社会保険や雇用保険の支払い額が変わる可能性があるため、事前に従業員への周知が必要となるでしょう。
まとめ
在宅勤務を実施する際には、従業員の負担を軽減するために在宅勤務手当の導入が検討されます。
在宅勤務手当の支給には多くのメリットがありますが、導入のためには相場の把握など事前準備が必要です。
この機会に在宅勤務手当の相場や導入方法などを確認し、具体的な制度の確立を進めてみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、
郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。