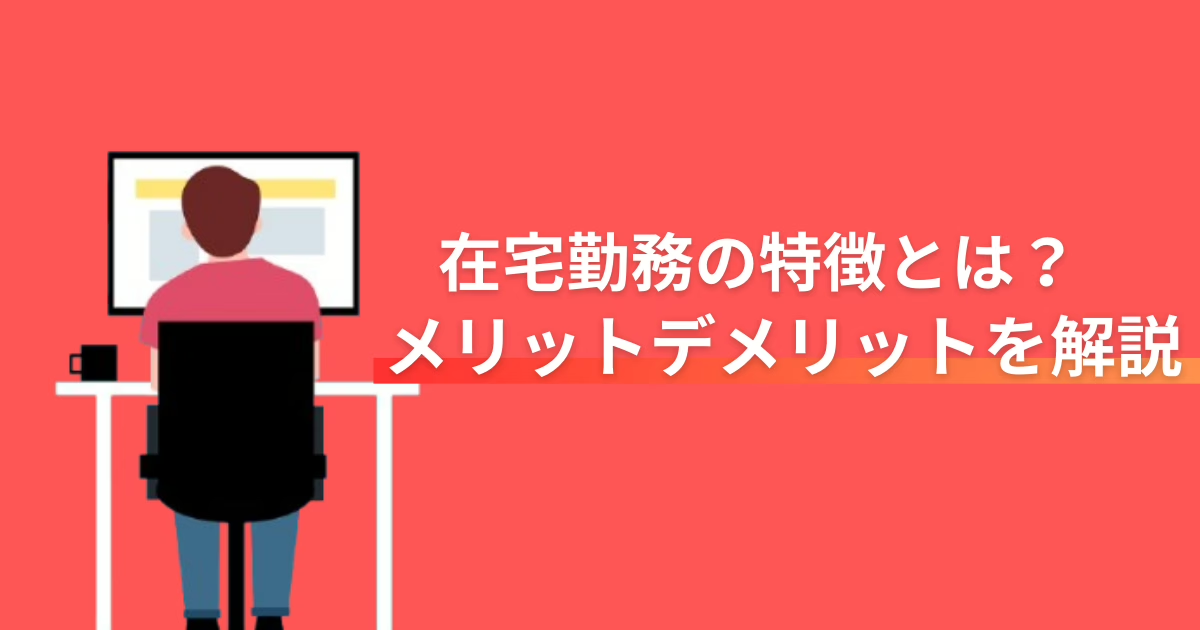郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
近年はWebシステムの発達やコロナの影響で非接触を優先するケースが多くなったため、在宅勤務を行う人が増えています。しかし、在宅勤務は一歩間違えると生産性の低下につながり、企業にとっての不利益なものとなるでしょう。
本記事では、在宅勤務の基本となる特徴やメリット・デメリット、導入時の注意点などを解説します。
在宅勤務とは?
在宅勤務の長所を活かすには、まずその特徴を理解する必要があります。以下では、在宅勤務の特徴や、同列で語られることが多いテレワークとの違いについて解説します。
在宅勤務はテレワークの一種
在宅勤務とは、場所や時間にとらわれない労働形態である「テレワーク」の一種です。従業員がそれぞれの自宅で仕事をすることを意味し、会社への出勤を強制しないのが特徴となっています。
フリーランスとは違い、在宅勤務はあくまで企業に所属したまま在宅で仕事をすることを意味します。企業の福利厚生や給料制度に影響はないため、「働く場所が自宅に変わった」という点が重要です。
在宅勤務とテレワークの違いについて
在宅ワークはテレワークの一種ですが、その労働スタイルにはいくつかの違いがあります。以下では、在宅勤務と同じように使われるテレワークやモバイルワークの意味を解説します。
テレワークは「柔軟な働き方」を意味する
テレワークとは、「柔軟な働き方」を重視した労働形態です。総務省や厚生労働省によれば、「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」をテレワークと定義しています。
インターネットやパソコンなどの情報通信技術に含まれる環境を活用して仕事をすることが、一般的なテレワークとなるでしょう。また、テレワークとほとんど同じ意味を持つ言葉に、「リモートワーク」があります。
リモートワークもICT技術を活用して、会社から離れた場所で柔軟に働くスタイルのことです。
在宅勤務とモバイルワークの違いについて
在宅勤務に近い働き方のひとつに、モバイルワークがあります。モバイルワークは在宅勤務と違い、自宅以外でネット環境のある場所で働くことです。
例えばWi-Fi環境のあるカフェやファミレス、移動中の電車やタクシーなどで仕事をするのがモバイルワークです。自由度の高い形で働ける一方、パソコンや周辺機器の紛失、セキュリティへの配慮など注意すべき点も少なくありません。
在宅勤務とサテライトオフィス勤務の違いについて
在宅勤務のほかにも、近年はサテライトオフィス勤務が多くの企業に浸透しています。サテライトオフィス勤務とは、リモートワーク環境をそろえた専門の施設で働くことを意味します。例えばレンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどが、サテライトオフィス勤務の対象施設です。
ほかの人たちと共有して使うスペースで仕事をすることが多く、人によっては集中しづらく感じるケースもあります。そのような場合、個室を完備している施設を選ぶことで、サテライトオフィス勤務がしやすくなるでしょう。
在宅勤務のメリット
在宅勤務には、モバイルワークやサテライトオフィス勤務にはないメリットがあります。以下を参考に、在宅勤務ならではのメリットを確認しましょう。
生産性向上や業務効率化に期待できる
在宅勤務は、自分の生活リズムに適した自宅という環境で仕事ができるため、生産性向上や業務効率化に期待できます。オフィスと比較しても自由に働けるため、伸び伸びと仕事ができる点が特徴です。
自由に働ける在宅勤務への切り替えは、労働意欲の向上につながる可能性もあります。仕事に対するストレスも軽減されるため、継続した労働がしやすくなる点がメリットです。
無駄なコストカットが可能
在宅勤務は、無駄なコストカットにつながる点もメリットです。例えば会社への通勤が不要になるため、交通費の支給が必要なくなり、会社の負担が軽減されます。従業員も満員電車によるストレスから解放されるため、両者にとってメリットがあるでしょう。
そのほか、在宅勤務の環境整備のためには多くの資料をデジタルデータに変換する必要があります。結果的にペーパーレス化が進み、備品のコストカットも可能です。
離職を防ぎやすい
在宅勤務の常駐化は、従業員の離職を防ぐきっかけにもなります。例えば介護や育児を理由に辞めてしまう人が多い場合、在宅勤務を推奨することで会社に引き止めることが可能です。
止むを得ない理由で離職してしまう人を減らす施策としても、在宅勤務は役立ちます。離職率を低下させ、人材の流出を防ぐことを目指すのなら、在宅勤務の環境整備にメリットがあるでしょう。
緊急時の事業継続性が確保できる
在宅勤務は、緊急時における事業継続性の確保にもつながります。事前に在宅勤務が社内に定着していれば、万が一災害などによって出社が困難となっても、自宅で事業を継続可能です。
従業員の安全を確保しつつ事業継続が行えるため、プロジェクトの進行に与える影響を最小限に抑えられます。災害時におけるマニュアルを事前に作成して、事業が簡単にストップしないように備えるのがポイントです。
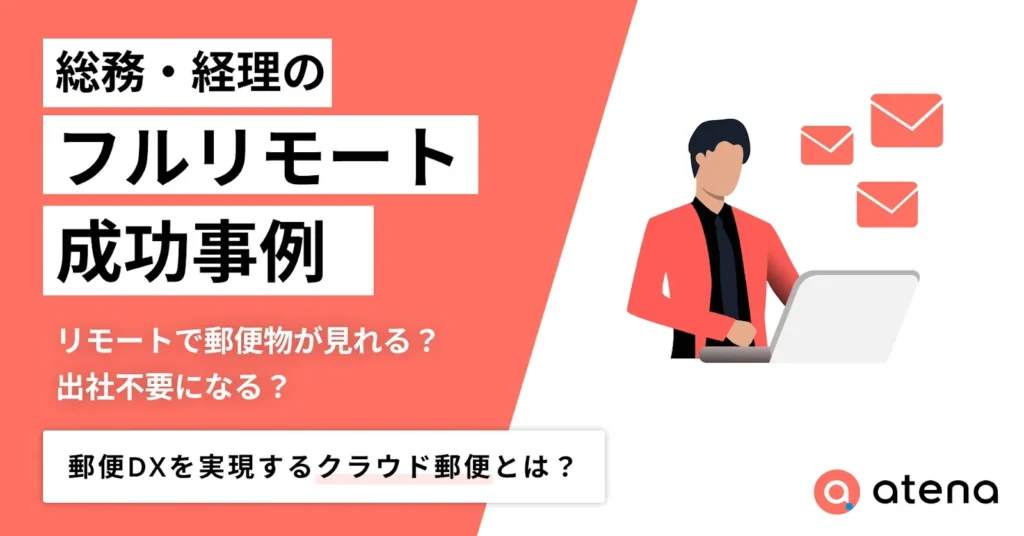
在宅勤務のデメリット
在宅勤務にはメリットが多い一方で、デメリットもいくつかあります。以下を参考に、デメリットになり得る要因をきちんと確認しておきましょう。
セキュリティリスクが高くなる
在宅勤務では、各自宅にあるネット環境と個々のパソコンを使うことになるため、セキュリティリスクが高まります。「ウィルス対策を行っているか」など、いくつかのチェックポイントを作成し、それらをクリアしなければ在宅勤務不可などのルール作りも重要です。
また、在宅勤務では、従業員の口から重要機密が流出するケースも多いです。家族や友人に仕事のことを話してしまうことで、機密情報の流出などのトラブルに発展する可能性も考えられます。在宅勤務中も職場で働いているときと変わらない意識を持てるように、事前の指導が必要です。
従業員間のコミュニケーションが不足しがちになる
在宅勤務が長期化すると、従業員同士のコミュニケーションが不足してしまいます。仕事上の伝達が上手くいかなくなったり、親交を深めることが難しくなったりする可能性がある点はデメリットです。特に新規で入社した従業員は、在宅勤務がメインとなると社内で良好な人間関係を作りづらくなります。在宅勤務では仕事を教えることも簡単ではないため、余計な負担や作業を増やす結果にもなり得るでしょう。
在宅勤務中も週に数日は出社する機会を作るなど、コミュニケーションを取りやすい環境を構築する必要があります。
在宅勤務によってサボり癖がついてしまうことも
在宅勤務が長引くと、仕事のサボり癖がついてしまう可能性があります。これまで真面目に働いていた従業員の生産性が落ちるなど、予期せぬデメリットも考えられるでしょう。
サボり癖のつく原因は、在宅勤務特有の「仕事とプライベート境界が曖昧になりやすい」点が問題だと考えられます。仕事とプライベートのON・OFFが上手く切り替えられないことで、生産性やモチベーションが低下するケースも少なくありません。働き方を個人の裁量に任せるのではなく、サボることができないシステムの導入やルール作りの検討が必要です。
在宅勤務を導入する際のポイント
在宅勤務の導入時には、いくつか把握しておきたいポイントがあります。以下からは、在宅勤務を行う前に確認しておくべきポイントを解説します。
勤務状況の管理方法を確立する
在宅勤務の導入時には、個々の仕事の状況を管理できる方法を確立するのがポイントです。基本的に在宅勤務中は、仕事の様子や進捗が確認できないため、個人のやり方を信用するしかありません。
しかし、個人にすべてを任せることになると、人によっては生産性や効率化が低下するでしょう。定期的に進捗を連絡するルールを作ったり、成果物を途中で提出させたりといった対策の導入が検討されます。
評価方法の変更も必要
在宅勤務がメインになると、これまでのように努力している姿勢を評価する定性評価は難しくなります。実際に仕事をしている現場を把握できないため、評価方法を変更する必要もあるでしょう。
例えば仕事の成果を重視する定量評価に切り替えるなど、在宅勤務用の評価方法を確立することが考えられます。いきなり評価方法を大きく変えると正確な判断ができなくなる恐れがあるため、徐々に中身を改善していくのがポイントです。
セキュリティ対策を万全に整える
在宅勤務中のセキュリティリスクを下げるためにも、複数の対策を考案して万全な環境を構築するのもポイントです。例えば個々のパソコンにセキュリティソフトの提供を行って、インストールを必須とするのもひとつの方法となります。
また、セキュリティ上問題のある行為について説明し、従業員の意識改革を行うのもポイントです。セキュリティの重要性を理解しきれていない従業員がいる可能性を考慮して、基本的な部分から指導をしていきましょう。
在宅勤務における注意点
在宅勤務の導入時には、注意すべき点もあります。以下では、在宅勤務における注意点を紹介します。
在宅勤務の導入におけるコストを考慮しておく
在宅勤務の導入時には、さまざまなコストがかかります。例えば専用ツールの導入、システムの改善、専用部署の設置などによって、多くのコストが発生することも考えられるでしょう。
事前にコスト面を想定して、在宅勤務の導入がそれを超えるくらいの利益になるように工夫していくことが重要です。初期投資を抑えることも大切ですが、必要な環境整備を怠ると結果的に仕事の効率が低下してしまいます。あくまで在宅勤務に必要な環境はしっかりと整備しつつ、不要なものを選別して削減していくのがポイントです。
まとめ
在宅勤務はテレワークの一種として、多くの企業に浸透しています。この機会に基本的な部分を確認して、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は、「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と、今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。