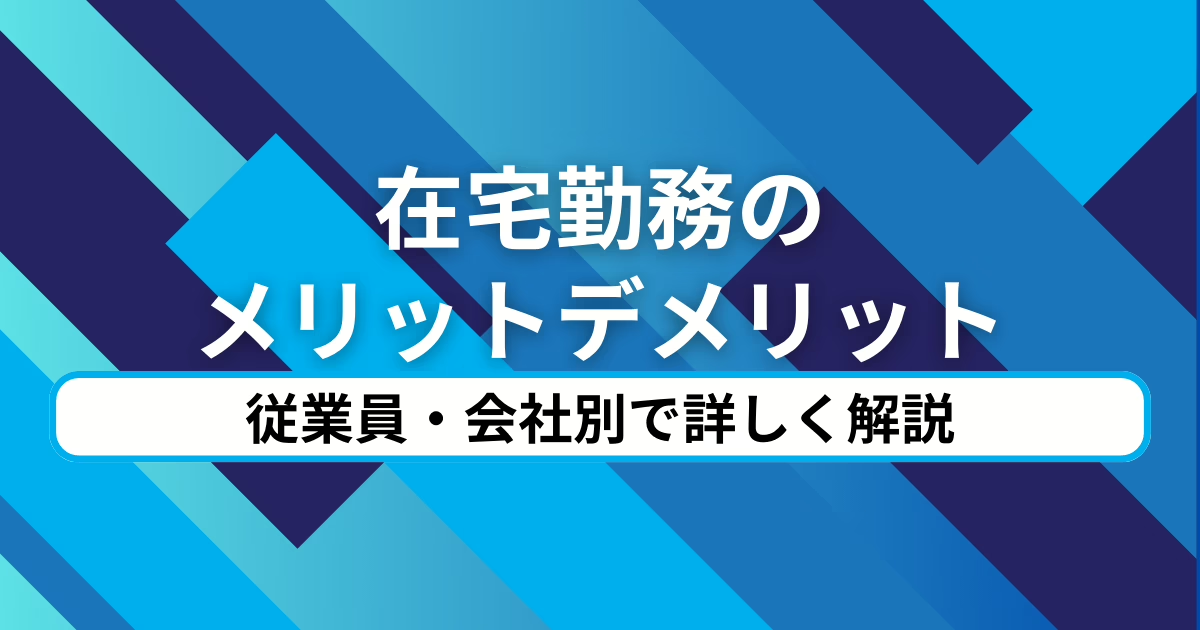郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです
近年は従業員の自主性を取り入れた柔軟な働き方が推奨されているため、在宅勤務を導入する企業が増えています。在宅勤務には、企業側と従業員側ともにさまざまなメリットとデメリットがあるため、導入前に詳細を確認しておくことがおすすめです。
本記事では、在宅勤務のメリット・デメリットについて、会社側と従業員側のそれぞれ視点から解説します。在宅勤務ならではのメリット・デメリットを確認し、実際の導入に役立ててください。
在宅勤務を取り入れる企業側のメリット
在宅勤務を取り入れることには、会社側にさまざまなメリットを与えます。ここでは、在宅勤務における会社側のメリットについて解説します。
従業員のワークライフバランス向上
在宅勤務では会社のオフィスに通う必要がないため、従業員のワークライフバランスの向上につなげられます。「平成28年 社会生活基本調査」によると、日本の平均通勤時間は往復で1時間19分もかかっているそうです。
そのため、在宅勤務に切り替えることで、従業員が毎日約1時間の時間的余裕を持つことができます。手に入れた時間によってプライベートが充実すれば、ワークライフバランスが向上し、仕事のモチベーションも高まるでしょう。
オフィスコストを抑えられる
在宅勤務を主流にすることで、会社はオフィス運営に必要な電気代、印刷代、ソフトウェア代、備品購入代などの削減ができます。業務における無駄なコストを見直し、ランニングコストを安く抑えるきっかけにできる点もメリットです。
完全在宅勤務にできれば、オフィスを解約してこれまで必要だった全てのコストをなくすこともできます。
事業継続性が高い
在宅勤務による業務は、災害など不測の事態が発生した際にも、事業を中断することなく継続できるメリットがあります。仮にオフィスやその周辺に問題が生じても、その他の地域に住んでいる従業員で事業を進められるため、事業継続計画(BCP)対策にも役立つでしょう。
企業のブランディングにつながる
多様な働き方への理解がある企業という宣伝ができれば、世間からのイメージアップおよびブランディングが行えます。今後数多くの企業が在宅勤務を取り入れるとしても、いち早く在宅勤務を導入したという実績があれば、それは企業にとって大きなアピールポイントとなるでしょう。
「在宅勤務による働きやすい環境が整っている」という状況を作ることで、今後優秀な人材確保がしやすくなるメリットもあります。
優秀な人材を確保できる
在宅勤務での業務を許可することで、会社に通勤できない場所にいる優秀な人材も確保できます。
例えば育児や介護で家を離れられない人や、海外にいる人なども、採用対象に含められるでしょう。また、通勤に必要な交通費を浮かせられる点も、在宅勤務導入のメリットです。
在宅勤務を取り入れる会社側のデメリット
在宅勤務の導入には、メリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、在宅勤務の導入時に考えられる会社側のデメリットを紹介します。
セキュリティに問題がある
在宅勤務で問題視されているのが、セキュリティ面に関する課題です。例えばカフェや電車などでパソコンを使った仕事をする場合、知らないうちに会社の情報を盗み見されるリスクがあります。
リスク軽減のためにサテライトスペースを導入したり、自宅での作業を徹底したりと、在宅勤務用のルールを設ける必要があるでしょう。
勤怠管理が難しくなる
在宅勤務は通常の業務スタイルよりも、従業員の出社・退社のタイミングが明確にできないため、勤怠管理が難しくなります。勤怠管理ができないと、労働時間中に怠ける従業員が出てくるなど、生産性の低下を招く恐れがあるでしょう。
勤怠管理の難しさは、従業員に対して成果以外での評価がしにくくなるというデメリットもあります。真面目に働いている従業員がいても、定量性評価による成果が確認できなければ、昇進させられないケースが増えるでしょう。
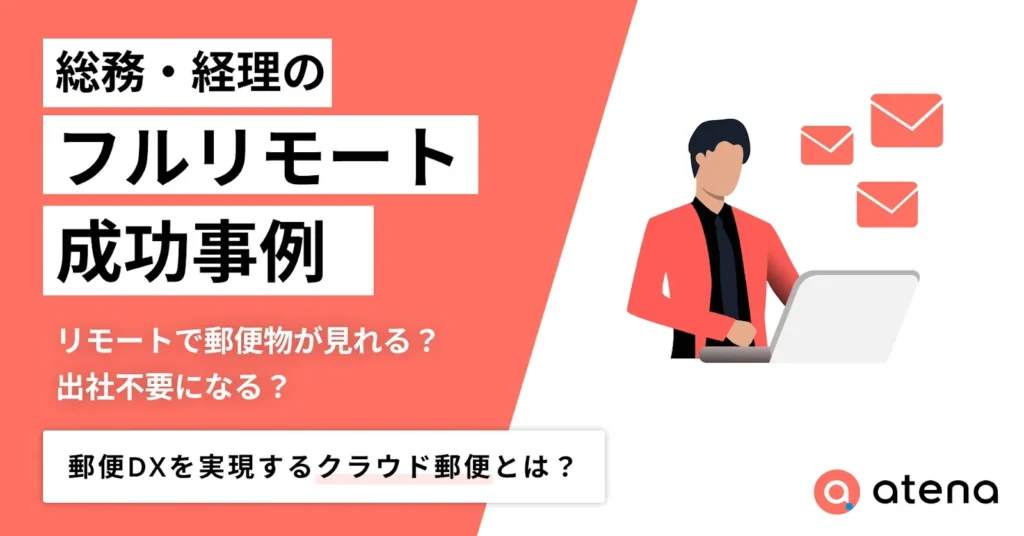
在宅勤務を取り入れる従業員のメリット
在宅勤務の導入は、従業員にも多くのメリットがあります。ここでは、従業員視点から見た在宅勤務のメリットを解説します。
仕事とプライベートを両立させられる
在宅勤務は従業員にとって、仕事とプライベートを両立させやすい環境だといえます。例えば出産などプライベートな事情で出社が難しい場合でも、安心して仕事が続けられるのがメリットです。
また、在宅勤務は仕事と生活を調和させられるため、ワークライフバランスを整えることにも貢献してくれます。
勤務地の制限がない
在宅勤務は決められた場所への出勤が必要ないため、住む場所に制限がかけられません。毎日の通勤時間が削減できるため、自分のためにより多くの時間を使えるようになります。
また、転居が必要になった場合でも、それを理由に仕事をやめなくても良い点がメリットです。
在宅勤務を取り入れる従業員のデメリット
在宅勤務の導入は、従業員側にもいくつかのデメリットが生じます。以下を参考に、どのようなデメリットが考えられるのかを把握しておきましょう。
コミュニケーション不足による疎外感を感じる
在宅勤務では常にひとりで仕事をすることになるため、コミュニケーション不足で疎外感を覚える時間が多くなります。同僚や上司と交流する時間も減ってしまうため、精神的な不安を感じてしまう人が増えやすい傾向です。
疎外感や孤独感はストレスの原因にもなり、心身に不調をきたす結果につながる可能性もあります。
成果を出すことへのプレッシャーを感じる
在宅勤務では仕事のプロセスを参考にすることが難しいため、どうしても成果中心で従業員を評価しなければなりません。そのため従業員は「成果を出さなければ昇進できない」という不安を感じてしまい、仕事へ集中できなくなる可能性があります。
成果を出すためのプレッシャーに悩まされる点は、従業員側から見た在宅勤務のデメリットです。
仕事のオンオフの切り替えが難しい
在宅勤務で仕事をする場合、プライベートとのオンオフを切り替えるのが難しくなります。例えば仕事中に家族が声をかけてきたり、プライベートの時間に仕事の連絡が入ってきたりと、生活が乱れるケースが増える懸念があるためです。
ひとり暮らしの場合も自室と仕事部屋を分けられないと、業務とプライベートの線引きができずに生活リズムが崩れてしまうことがあります。
評価基準が曖昧でやる気が出ない
在宅勤務における評価基準が曖昧だと、前述した通りに成果のみで評価されることに不信感を感じるケースもあります。どれだけ頑張ってもスキルや能力によって評価が決まってしまうと、やる気が出ないだけでなく仕事にストレスを感じてしまう従業員が増えるでしょう。
在宅勤務を導入する際のポイント
在宅勤務を導入する際には、メリットとデメリットを考慮した上で、いくつかのポイントをチェックすることが重要です。
従業員宅の労働環境を整える
在宅勤務を導入する際には、まず従業員の自宅に仕事用の環境を整えることがポイントです。自宅に専用の環境がないまま在宅勤務をはじめても、上手く仕事を回せずに生産性が下がるケースがあります。
場合によっては会社が環境整備に必要な費用を負担し、個々の在宅勤務環境を整備することも検討する必要があるでしょう。
セキュリティソフト導入を進める
在宅勤務では、セキュリティに関する課題解決も最も重要なひとつです。仕事に使っているパソコンの覗き見や無料Wi-Fiによる情報の抜き取りなど、在宅勤務中にはさまざまなセキュリティリスクがあります。
在宅勤務の際には高度なシステムを備えたセキュリティソフトの導入や、従業員への教育を徹底して、問題の発生を未然に防ぐことがポイントです。
評価方法を明確にする
従業員の不安を払拭するために、在宅勤務の導入時には同時に評価制度を明確にする必要があります。
在宅勤務では成果以外の部分を評価することが難しく、「頑張っているのに報われない」と悩む従業員も多いです。そのため評価方法を事前に提示し、従業員のやる気を引き出してアウトプットの質を上げられるように支援するのもポイントです。
在宅勤務のルールを決める
在宅勤務を実施する場合、専用のルールを設けるのもポイントです。例えば1日の最大労働時間の決定や自宅以外の勤務不可など、従業員が守るべきルールを制定することで、在宅勤務における仕事の質を上げられます。
誰でも閲覧可能な専用マニュアルを作成し、全従業員がルールを守るよう意識を高める必要があるでしょう。
在宅勤務導入の注意点
在宅勤務の導入時には、いくつかの注意点もあります。以下を参考に、在宅勤務における注意すべき点を事前に確認しておきましょう。
福利厚生を見直す
在宅勤務を導入するのなら、従来の福利厚生の内容を見直す必要があります。例えば従業員に通勤手当を出していた場合、在宅勤務によって支給の必要がなくなります。
逆に従業員の自宅の通信費や電気代などは、新たに会社側で負担すべき項目になるでしょう。在宅勤務での働き方を考慮した福利厚生の見直しを行い、従業員に負担がかからないようにしなければなりません。
オンラインツールを正しく選ぶ
在宅勤務を進める上で、オンラインツールの導入は必須事項です。しかし、現在はさまざまなツールを各企業が展開しているため、どれを導入するべきか判断に悩むこともあるでしょう。オンラインツールには、「Zoom」や「Google Meet」など無料で使用できるものから、月額料金や初期費用が必要な有料のツールも存在します。
そのため、いくつかのツールを比較し、どのツールを使用すればコストを抑えられるのかを見極めたうえで、最適なツールを選定するとよいでしょう。
まとめ
在宅勤務には、会社側と従業員側の両方に、それぞれメリット・デメリットがあります。まずは導入前に各メリットとデメリットを把握し、それに合わせた最適な環境整備を検討してみましょう。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。