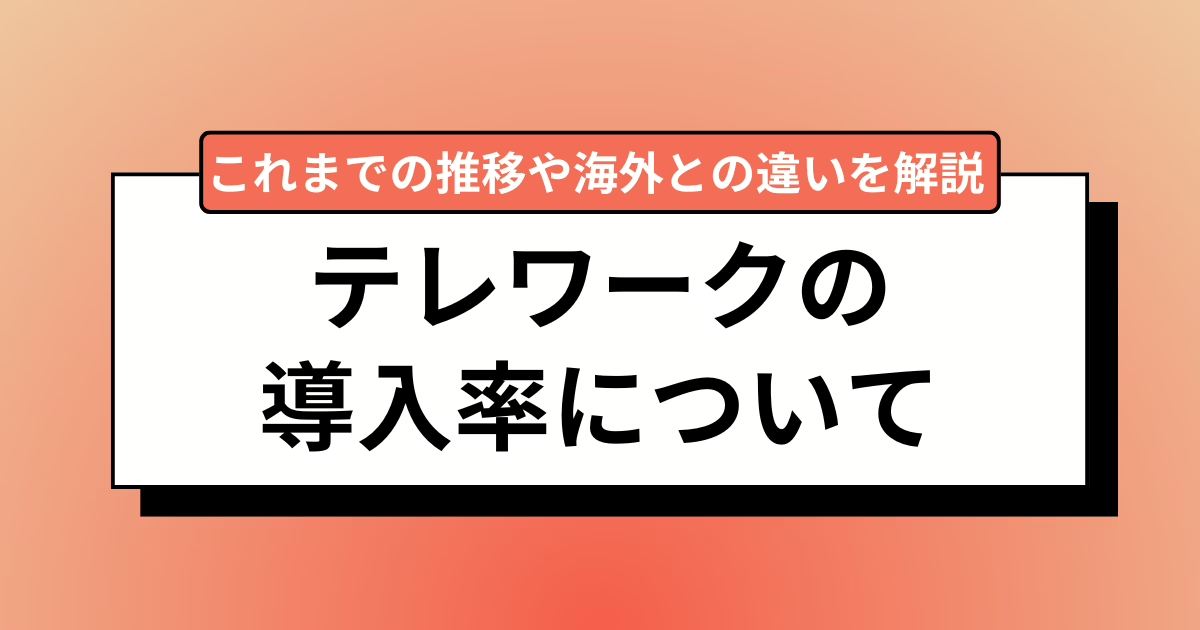郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークによる仕事の方法は多くの企業に認知されていますが、実際の導入率はさまざまな要因によって変動しています。具体的にどれくらいの導入率になっているのかを把握しておくことは、自社でテレワークの導入を検討するうえで参考になるでしょう。
本記事ではテレワークの導入率とその推移の他、導入を妨げる理由や海外との違いを解説します。
テレワークの導入率について
日本国内において、テレワークの導入率は以下のようになっています。
テレワークの導入率は2022年2月時点では28.5%
株式会社パーソル総合研究所の調査によると、2022年2月4日〜7日時点でのテレワーク実施率は、正社員雇用の場合28.5%です。約3割の企業が、実際にテレワークを導入・継続していることが分かっています。
過半数にはいたらないため、日本国内においてテレワークが定着している企業は、まだまだ少数派だといえるでしょう。
テレワークの導入率の推移
現在の導入率が把握できたところで、続いてテレワーク導入率の推移を確認します。以下を参考に、これまでの導入率の変化をチェックしてみましょう。
テレワークの導入率は新型コロナによる影響で急上昇
総務省のデータによると、1回目の緊急事態宣言の際には17.6%から56.4%までテレワークの導入率は急上昇しています。これまでテレワークに興味がなかった企業も、社会情勢の急激な変化に合わせて、仕事の体制を整え直す必要に迫られたケースが多いことが想像できるでしょう。
その後テレワーク導入率は低下したものの、2回目の緊急事態宣言時には再び38.4%まで上昇しました。このように日本のテレワーク導入率は社会の情勢に左右されることが多く、その都度大きく変動している点が大きな特徴です。
テレワーク導入率(業種別)
テレワークの導入率を業種別にチェックすると、以下のような数値になります。
情報通信業:55.7%
各術研究、専門・技術サービス業:43.2%
金融業、保険業:30.2%
電気・ガス・熱供給・水道業:28.4%
不動産業、物品賃貸業:27.9%
(参考:パーソル総合研究所(2020)「第四回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」)
Web関係やIT系技術職が含まれる情報通信業がもっとも導入率が高く、次いで研究職や技術関係の職種がテレワークを実施しています。
テレワーク導入率(従業員数別)
テレワークの導入率を企業の従業員数別にみると、以下のような数値になります。
従業員10,000人以上:46.9%
従業員1,000〜10,000人未満:39.9%
従業員100〜1,000人未満:26.1%
従業員10〜100人未満:15.4%
(参考:パーソル総合研究所2022年2月時点の調査)
従業員数の多い企業ほど、テレワーク導入率が高いことが分かります。
テレワーク導入率(年収別)
続いて従業員の年収別に、テレワークの導入率を確認します。
1000万円以上:51.0%
700万円以上1000万円未満:41.2%
500万円以上700万円未満:27.9%
300万円以上500万円未満:20.6%
300万円未満:12.7%
(参考:内閣府 政策統括官 第2回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査)
上記のデータによると、年収が高い従業員ほどテレワークを実施していることが分かります。上述の従業員数別のデータとあわせても、従業員に高い年収を提示できる企業は、従業員数の多い企業以上に積極的にテレワークを実施していると判断できるでしょう。
テレワーク導入率(地域別)
テレワークの導入率を地域別に確認すると、以下のような数値になります。
関東:36.3%
近畿:20.8%
東海・北陸・甲信越:15.9%
北海道・東北:12.4%
中国・四国・九州:11.2%
(参考:パーソル総合研究所2020「第四回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」)
関東の導入率が高く、その他の地方とは大きな差があることが分かります。また、東京都の発表した「テレワーク実施率調査結果(2022年3月時点)」を確認すると、従業員30人以上の都内企業におけるテレワーク実施率は62.7%です。
東京都内のテレワーク導入率は、群を抜いて高いといえるでしょう。
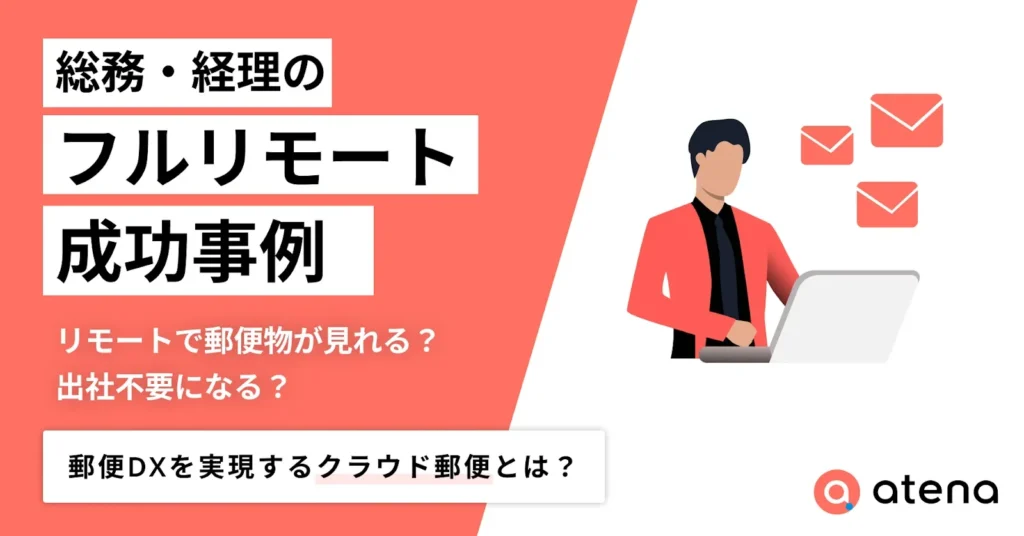
日本と外国のテレワーク導入率の違い
日本と外国のテレワーク導入率を比較すると、大きな違いがあることが分かります。2015年のデータを参考にすると、日本の導入率が19%であるのに対し、アメリカは既にその時点で85%を達成しています。
アメリカでは2010年に「テレワーク強化法」を制定するなど、早くから企業にテレワークを推奨する動きがはじまっていました。その工程が現在にも影響を与え、海外のテレワーク導入率は日本と比べて非常に高い数値になっているのです。
テレワークの導入率上昇における課題
日本のテレワーク導入率がなかなか上昇しないことには、いくつかの理由があります。以下では、テレワークの導入率上昇における課題について解説します。
企業側がテレワークに消極的
テレワークの導入率の低さは、企業側の消極的な姿勢がひとつの理由になっています。いまだにテレワークに消極的な企業は多く、従来の仕事スタイルを継続しているケースは珍しくありません。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った「テレワークの労務管理等に関する実態調査」における「テレワークを導入・実施していない理由」によると、「できる業務が限られる」が68.1%ともっとも高い理由になっています。その他、セキュリティ確保が難しいことや、社内のデータが電子化されていないこと、従業員の勤怠管理が難しいことなどが理由として挙げられています。
テレワークの環境整備にかかるコスト問題
テレワークを導入するには、専用ツールや新たな経費の発生など、コスト面での課題もあります。コストに見合った効果が出るか分からないため、導入を踏み出せない企業も多いのが現状です。
経営に余裕のない企業などは、「テレワークを導入したくてもできない」という事情がある可能性も考えられます。
セキュリティに対する課題
先のテレワークを導入しない理由にも挙げられていたセキュリティ問題も、大きな課題となっています。会社のシステムだけでなく、個々の従業員が使うパソコンにも適切なセキュリティ環境を整備しなければなりません。
そこまでしても情報流出などに発展するリスクをゼロにはできないため、導入を躊躇する企業は増えてしまいます。
従業員のメンタルに関する課題
テレワークは、従業員のメンタルにマイナスの影響を与えるケースもあります。例えば日常的なコミュニケーションが希薄になって孤独感に苦しんだり、周囲の目がなくなったことでサボり癖がついたりすることが考えられるでしょう。
従業員によってはテレワークという業務形態が合わずにストレスとなる可能性もあるため、必ずしも導入がプラスの方向に向くとは限らない点が課題です。
テレワーク時の勤怠管理や進捗の把握が難しい
テレワークの際には、勤怠管理や進捗管理が難しくなる点も課題です。管理がきちんとできないと、本当に仕事をしているのか、納期に間に合うのかといった疑念が発生しやすくなるため、従業員への信頼を損なう理由にもなってしまうでしょう。
また、外部からのマネジメントが困難となるため、従業員の作業効率の低下や健康状態の悪化なども心配されます。
テレワークの仕事の評価が難しい
テレワーク中は従業員ごとの様子をチェックできないため、正確な評価が難しくなります。従来の評価制度が機能しなくなり、従業員から査定結果に不満が出るリスクもあるでしょう。
そのためテレワークの導入時には、新たに評価基準を作って共有する必要があります。
テレワークの導入に必要な準備
テレワークの導入を行う場合、いくつか必要とされる準備があります。以下を参考に、テレワークの導入に向けた準備について確認してみてください。
テレワーク導入に向けた計画の立案
テレワークの導入を検討するのなら、まずは具体的な計画の立案が必要です。自社業務でテレワークが可能なのか、どのような設備やシステムが必要なのかを話し合うことが最初のステップになります。
導入前の課題と導入後の課題を事前にピックアップして、対策を考えておくことも重要です。
テレワーク化する業務を選別する
実際にテレワーク化する業務の選別も、導入時に必要な準備です。業種や会社の方針次第では、全ての業務をテレワーク化することが難しい場合もあります。
全業務を当てはめるのではなく、一部をテレワーク化するなどの対応も検討されます。
必要なツールをピックアップする
テレワークの際に使用するツールをピックアップし、実際に導入するものを決めます。チャットツール、Web会議ツール、勤怠管理ツールなど、複数のツールを活用するのが基本です。
無料で使えるツールやトライアルで試せるツールを活用し、仮の状態でテレワークをはじめてみることもひとつの方法です。
テレワークのルールを明確化する
テレワークの導入時には、ルールを明確化することもポイントです。報連相の流れや勤怠・進捗情報の伝え方など、スムーズに仕事ができるルールを考案します。
ルールを作成したら全従業員に内容を周知させ、納得してもらった上でテレワークを開始します。
まとめ
テレワークの導入率は、今後さまざまな要因によって伸びていく可能性があります。導入方法や課題を事前に確認し、いつでも導入できる環境をこの機会に整えてみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、
郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。