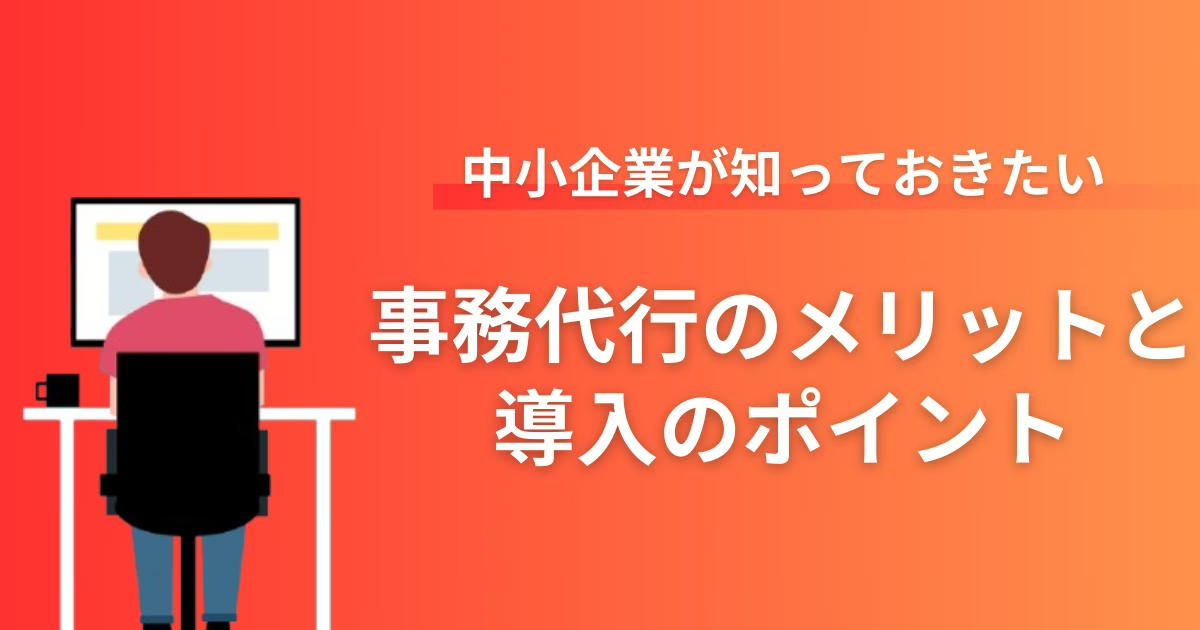「事務代行(バックオフィス業務のアウトソーシング)」は、企業の成長や組織拡大に伴って増加する管理業務を効率化する有力な手段です。特に中小企業にとっては、限られた人材リソースをコア業務に集中させるためにも、バックオフィス業務の外注化が検討されることが増えています。しかし、実際には「どのタイミングで導入すればいいの?」「外注化で失敗しないために気を付けるポイントは?」など、疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、事務代行が必要になるタイミングや失敗例、その解決策、導入ステップなどをわかりやすく解説し、バックオフィス効率化のヒントをお伝えします。
事務代行が必要になるタイミング
創業期から拡大期への移行
創業したばかりの頃は、経理・請求書管理など最小限の事務対応が主になることが多いでしょう。ところが従業員を増やすタイミングで、労務管理や社会保険の手続きなど、社内で処理すべきバックオフィス業務は一気に増加します。
特に郵便物が増えてくると、書類の受け取り・管理・ファイリング・データ化といった手間も大きくなりがちです。オフィスに届く契約書や請求書などをうっかり見落としてしまうと、ビジネスチャンスの損失や支払い漏れといったリスクにもつながりかねません。企業が成長期に入る前後こそ、事務代行を検討する最適なタイミングと言えます。
アウトソーシングの失敗例
事務代行を導入するときに「想定した効果が得られない」「かえって工数が増える」といった失敗も起こり得ます。以下のような要因が代表例です。
外部と社内のコミュニケーション不足
事務代行を委託する際、必要な情報を適切に共有していなかったり、発注者・受注者間でコミュニケーションの頻度が不足していたりすると、すれ違いやトラブルが発生しやすくなります。
- いつまでにどんな資料が必要か、どのフォーマットで提出すればいいか伝わっていない
- 細かな仕様や優先度が伝わっていない
これらの伝達不足により、作業が手戻りになる、成果物に対して修正が多発して社内負担が増えるなど、かえって工数が増えるという事態に陥りかねません。早期の段階から、連絡手段(メールやチャットツールなど)とコミュニケーションルールを明確にしておきましょう。
範囲や成果物が不明確なままアウトソーシング
「〇〇業務をお願いしたい」と思い描いていても、具体的にどの作業をどこまで行うのか、いつまでにどんな成果物を提出するのかがはっきりしない場合、外注先との認識ズレが生まれやすくなります。あらかじめタスクの範囲やスケジュールを事細かに定義しておくことが大切です。
具体例
- 経理を全て代行にお願いしたが、細かい領収書のスキャン・データ入力は結局社内で行わなければならない
- 労務の代行を依頼したものの、勤怠管理や給与計算結果の最終チェックは社内に戻り、代表の手間が減らない
情報や資料が分散していて連携が進まない
業務をスムーズに進めるためには、関連書類・データを適切に共有し、タイムリーにアクセスできる環境が不可欠です。社内のあちこちに情報が散らばっていると、外注先に渡すべき資料がすぐに用意できず、作業が滞る原因となります。共有フォルダやクラウドストレージを整備するなど、情報の一元管理を意識しましょう。
本当に効率化できる外注
事務代行に成功している企業は、次のようなポイントを意識しています。
業務フローの設計
外注化する際には、あらためて自社の業務フローを見直すことが効果的です。外注先に丸投げするのではなく「なぜこの業務が必要か?」「どのタイミングで外部へ依頼すればよいか?」といったプロセスを洗い出し、最適化を図りましょう。
- 自社: 業務の優先順位設定 → 必要データやマニュアルの提供
- 外部: 受託範囲の作業実施 → 成果物の納品 & フィードバック
オンラインアシスタントやクラウドサービスの活用
リモートワークの普及も相まって、オンラインで依頼可能なサービスが充実しています。
たとえば経理・労務系のクラウドソフトや、契約書の電子管理システムなどを導入すれば、紙のやり取りや対面での打ち合わせが減り、作業時間の短縮が期待できます。
オンラインアシスタント
- 経理、労務、資料作成など多岐にわたるバックオフィス業務に対応することができる
- 顧問税理士、社労士との「橋渡し」も含めて任せられる仕組みを整えることができる
クラウド郵便
- 面倒な紙の処理を減らすことができる
- 郵便物の受け取り→電子化→転送、廃棄をワンクリックで指示できる
- 郵便物も電子化することでオンラインアイアスタントとの情報共有も容易に
コミュニケーションツール設計とツール連携
チャットツール(Slack、Chatworkなど)やオンライン会議システム(Zoom、Google Meetなど)を活用することで、外注先とのやり取りをスピーディーに行えます。さらに、ファイル共有ツールやタスク管理ツールと連携しておくと、担当者ごとの作業進捗が一目でわかり、二度手間が防げます。
あらなに会計システム、勤怠管理システム、クラウドストレージなど、社内で活用しているシステムと外注先のワークフローと連携することで重複入力や手動でのファイル受け渡しを最小限にすることができます。
事務代行導入のステップ
事務代行の導入は、下記のようなステップを踏むとスムーズです。
1. 優先順位の洗い出し
まずは「自社でしかできない業務」「他社に任せられる業務」を仕分けします。次に「任せたい業務」の重要度や緊急度を評価し、優先順位をつけると整理しやすくなります。
2. 必要要件の整理
優先度の高いタスクから順に、どの程度の専門知識が必要か、どれぐらいの頻度で発生するかなど、要件を具体的にまとめましょう。これにより、自社に合った外注先を選定しやすくなります。
3. サービスの比較検討
複数の事務代行会社やオンラインサービスを比較するときは、料金プランやコミュニケーション体制、納品スピードなどをチェックします。事前に導入事例や口コミを参考にするのも効果的です。
4. 導入テスト & 効果検証
いきなりすべての業務を任せるのではなく、まずは一部の業務で試験導入し、効果や課題を検証します。問題点があればフィードバックし、修正しながら最終的な運用スタイルを確立していきます。
導入時の注意点
外注化できる範囲と自社で行う範囲の明確化
事務代行に任せられる範囲をしっかり切り分けることが大切です。高度な判断や意思決定を伴う業務は自社内で完結させ、事務作業的な工程を外注するなど、分担をはっきりさせるとトラブルを減らし、追加工数が発生するリスクを抑えることができます。
コストと対応スピードのバランス
外注化のメリットを最大化するためには、コストだけでなく、どれだけ迅速に問題対応や修正が可能かも重要です。コスト面の安さだけに注目すると、レスポンスが遅かったり品質が安定しなかったりする恐れがあります。費用対効果を見極め、自社の経営戦略やリソースに合ったバランスで外注先を選びましょう。
まとめ
ここまで、事務代行(バックオフィス業務のアウトソーシング)のメリットや、導入時に気をつけたいポイント、スムーズな導入手順などをご紹介してきました。実際に外注化を進めるには、業務フローの見直しや外注先との綿密なコミュニケーションが欠かせません。
そのうえで、総務部門の業務効率化に有効な方法として注目されているのが、クラウド郵便サービス「atena」 です。オフィスに届く郵便物をデジタル化し、スマホやPCでどこからでも確認・共有できるため、郵便物の受け取りや管理にかかる手間を大幅に削減できます。
- atenaの特徴例
- 受け取った郵便物を開封・スキャンし、即座にデータを確認可能
- 書類の保管場所や誤配リスクを抑制
- リモートワークでも郵便対応ができるので、オフィス不在時の業務がスムーズ
- 複数支店があっても郵便物が一元管理できる
「外注化で生まれた時間をコア業務に回したい」「郵便物の管理や業務フローをもっと効率化したい」とお考えの方は、ぜひ一度 atena の導入を検討してみてください。
また、atena 事務代行を使えば、契約書の製本・押印・発送や、備品の管理、キッティングまで、オンライン型の事務代行ではカバーできない業務もアウトソースすることができます。

詳しい機能や導入事例、料金などはそれぞれの公式サイトでご確認いただけます。事務代行とあわせて、クラウド型サービスをうまく組み合わせることで、バックオフィス全体の大幅な効率化を目指しましょう。