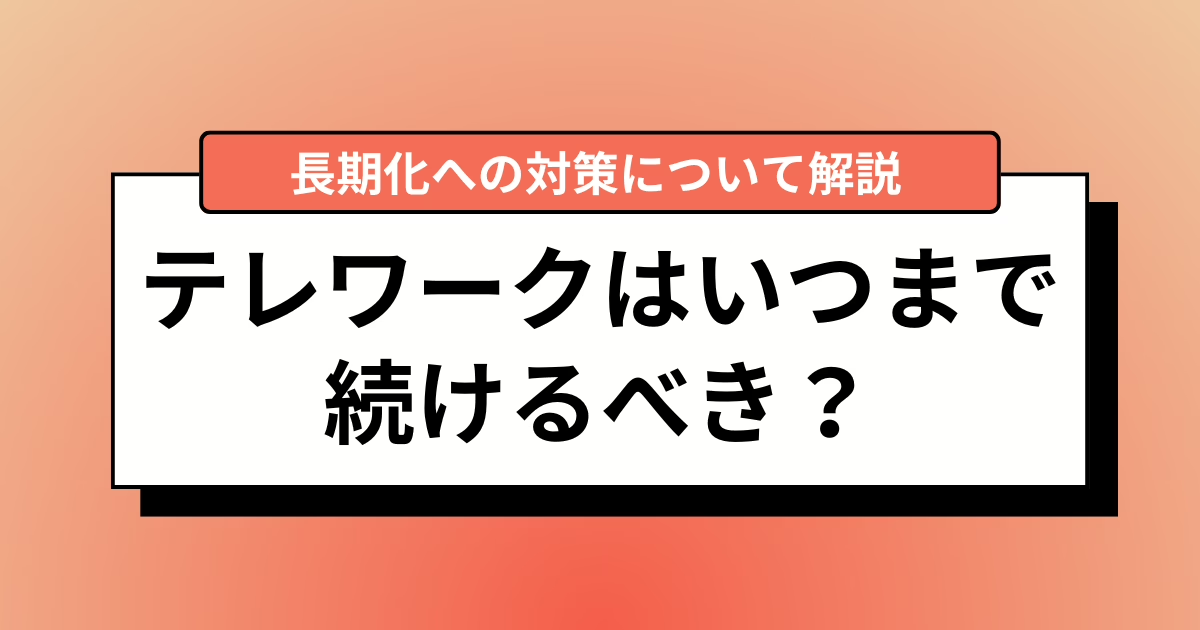郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークを導入したものの、いつまで継続すべきか迷っている企業も多いのではないでしょうか。今後の社会情勢や他社の動向次第では、継続を断念することも検討されるでしょう。
本記事では、テレワークをいつまで継続すべきなのかを検討している企業に向け、海外と国内企業の動向を解説します。また、テレワークの長期化に向けた対策も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
テレワークはいつまで続けるべきか?
「テレワークをいつまで続けるべきか」という点は、企業にとってひとつの課題となりつつあります。現在テレワークを導入している企業も、今後いつまで続けるか考えておく必要があるでしょう。
いつまでテレワークを継続するか判断が必要
テレワークは現在多くの企業に普及していますが、今後もその流れが続くかは不明です。特に日本国内では、あらかじめテレワークが普及していたわけではありません。そのため、コロナウィルスをはじめとした社会の動向次第では、通常業務に戻す企業が増える可能性もあるでしょう。
早いうちから、自社がいつまでテレワークを継続するべきなのかを判断し、その準備をする必要があります。
海外では今後もテレワークを継続する企業が多い
海外の企業に関しては、今後もテレワークを継続するケースが多いです。以下では、海外企業のテレワーク事情について解説します。
TwitterやMeta(旧・Facebook)は恒久的に継続すると発表
TwitterやMeta(旧・Facebook)といった海外企業は、今後も恒久的にテレワークを継続すると宣言しています。従業員が希望すれば、いつまでもテレワークで仕事ができる環境を構築するようです。
その他、海外では期限を設定した上で、テレワークの継続を決めている企業も少なくありません。
Appleは段階的にテレワーク以外の働き方を復活している
海外企業でも、Appleは段階的に出社や店舗の再開を行っています。テレワークという選択肢も残しつつ、以前のスタイルに戻す動きが見られることが特徴です。
Appleのようにテレワークとそれ以外の働き方を両立するケースも、今後増加すると考えられるでしょう。
日本もテレワークを継続する企業が多い
海外企業に限らず、日本国内の企業もテレワークを継続するケースが多いです。以下では、日本企業のテレワーク事情を解説します。
Yahoo!は「無制限リモートワーク」を実施
Yahoo!は2014年という早い段階からテレワークを導入していましたが、コロナウィルスをきっかけに無制限にテレワークを実施する制度を開始するに至りました。2022年には通勤手段の制限を緩和し、従業員の居住地を全国に拡大するなど、テレワーク環境の整備を進めています。
積極的なテレワークの推奨は企業イメージの向上につながり、将来の人材を確保するきっかけになり得るでしょう。
東京都内の企業は9割以上がテレワークを継続予定
東京都で令和3年10月に行われた調査によると、テレワークを導入している企業の9割以上が、今後も継続する意向を示しています。都内は特にテレワークを導入している企業が多いため、国内における継続事例として参考になるでしょう。
企業によっていつまで継続する予定なのかは異なるため、今後の実態調査にも注目です。
IT系や事務などの職種はテレワークを継続しやすい
IT系や事務などの職種は、テレワークを継続する意向が強いです。特に自宅やサテライトオフィスでも働ける仕事の場合、そのまま継続するケースが多くなると予想されます。
IT系の職種などは、テレワークによって業務の効率化を実現できた例も少なくないため、今後も継続を希望する可能性が高いです。
営業や介護などはテレワークの継続が難しい
一方で、営業や介護などの職種は、テレワークの継続が難しいと判断されます。そもそも営業や介護など対面で仕事をする職種にとって、テレワークのメリットを活かすことは容易ではありません。
近年は需要に合わせてオンライン環境を使った業務スタイルも確立されていますが、会社が導入を決断できないケースも多いです。
テレワークをいつまでも継続するメリット
テレワークを導入している場合、今後も継続して利用し続けることも検討されます。以下で解説するテレワークを続けるメリットを、継続の判断材料にしてみてください。
コストの削減につながる
テレワークの継続は、事業のコスト削減につながるメリットがあります。具体的にはオフィスの賃料や光熱費、交通費や備品の購入費などを削減できるでしょう。
事業形態によってはオフィスの縮小など、大幅なコストカットができる可能性もあります。
従業員のワークライフバランスが充実する
テレワークは従業員を満員電車から解放し、通勤時間の省略など多くのメリットを生んでいます。ストレス軽減や自由に使える時間の増加などによって、従業員のワークライフバランスが充実してモチベーションアップにつながるでしょう。
業務継続性を保てる
テレワークが常駐化することで、出社しなくても仕事が回るようになります。仮に災害などで出社できない状況になっても、事業を止めずに済むのがメリットです。
事業継続性の確保のために、テレワークを続けることも検討されるでしょう。
新たな人材確保と離職率の低下が実現する
テレワークは仕事をする場所を選ばないため、遠方に住む人や事情があって出社できない人材も採用できます。また、育児や介護を理由に退職してしまう人をテレワークに回すことで、離職率を下げられるのもメリットになるでしょう。
人材確保と離職率の低下を同時に実現できる点は、テレワークという労働スタイルの大きな魅力です。
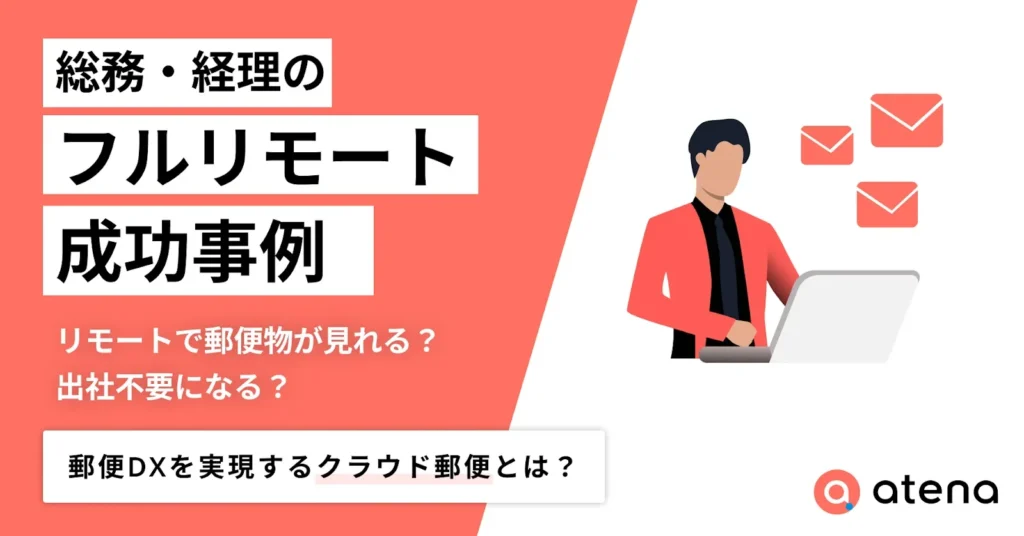
テレワークをいつまでも継続するデメリット
テレワークの継続にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。以下では、テレワークをいつまでも続ける場合に考えられるデメリットを解説します。
コミュニケーション不足が当たり前になる
テレワークの継続は、コミュニケーション不足を加速させる結果につながります。意見のすれ違いや進捗管理ミス、作業の非効率化などのデメリットが継続する可能性があるためです。
テレワークによってコミュニケーション不足が問題視されている場合には、中断もしくは現状の改善が必要とされるでしょう。
体調を崩す従業員が増加する可能性
テレワークの継続は、体調を崩す従業員を増やす可能性もあります。例えば慢性的な運動不足や、仕事とプライベートの切り替えができないことによる労働時間の長期化などによって、少しずつ体調に悪影響が出るケースもあるためです。
従業員の状況次第では、テレワークのルールを改定するなどの措置が必要になるでしょう。
従業員のメンタルに影響が出ることも
テレワークは肉体的な問題だけでなく、従業員のメンタルに影響を与える可能性もあります。例えばテレワークで人と交流する機会が限定されると、従業員によっては孤独を感じてしまうことがあるでしょう。
家に閉じこもってばかりいる生活が続くと鬱などのリスクが高まるため、特に在宅勤務がメインとなるテレワークの場合には注意が必要です。
セキュリティリスクが高まる
テレワークが続くと、油断によってセキュリティリスクが高まる可能性も懸念されます。重要機密の入ったパソコンの紛失など、ヒューマンエラーによる情報漏洩などが起きれば、多大な損害を被ることになるでしょう。
セキュリティ面が重要視される業種の場合には、継続時に改めて情報管理を徹底するように見直すのがポイントです。
テレワークの長期化に備えて企業が行うべき対策
テレワークを継続する場合、長期化に備えて対策を講じる必要があります。以下では、企業が行うべきテレワークの継続対策を解説します。
従業員同士のコミュニケーションを活性化させる
テレワークを継続する場合には、授業員同士のコミュニケーションを活性化させる施策が必要です。例えば、雑談がしやすいツールの導入や定期的なミーティングの機会を設けて、コミュニケーション不足を解消することが考えられます。
最小限のコミュニケーションで終わるのではなく、人とのつながりを重視した積極的な交流を習慣化するのがポイントです。
従業員のメンタルチェックやヒアリングをこまめに行う
テレワークの継続時には、従業員の体調やメンタルを管理するために、こまめなチェックを繰り返すことが必要です。業務や生活に関するヒアリングを行い、悩みの解決に協力するのもテレワークを継続する企業の役割となるでしょう。
メンタルチェックなどは外部の専門家に依頼して、本格的な解決を目指すことも考えられます。
テレワークに関する最新のサービスやソフトウェアの導入を検討していく
テレワークを継続するのなら、最新のサービスやソフトウェアを積極的に導入していくことも重要です。近年はテレワークが普及したことによって、関連するサービスの発展が促されることになりました。
現在も、テレワーク業務をサポートするさまざまなサービスが展開されていますが、今後はさらに便利で使いやすいシステムが開発される可能性もあるでしょう。
定期的にテレワーク環境を見直し、最新のサービスやシステムを導入していくことも求められます。
まとめ
テレワークは今後、企業次第で継続か中止かが決められていくことになります。海外も含めた他企業の動向を確認した上で、判断が必要となるでしょう。
仮に今後も継続する場合には、「いつまで」継続するのかを考える必要があります。この機会に継続時のポイントを確認し、よりテレワークのメリットを引き出せる環境の整備を行ってみてはいかがでしょうか。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。