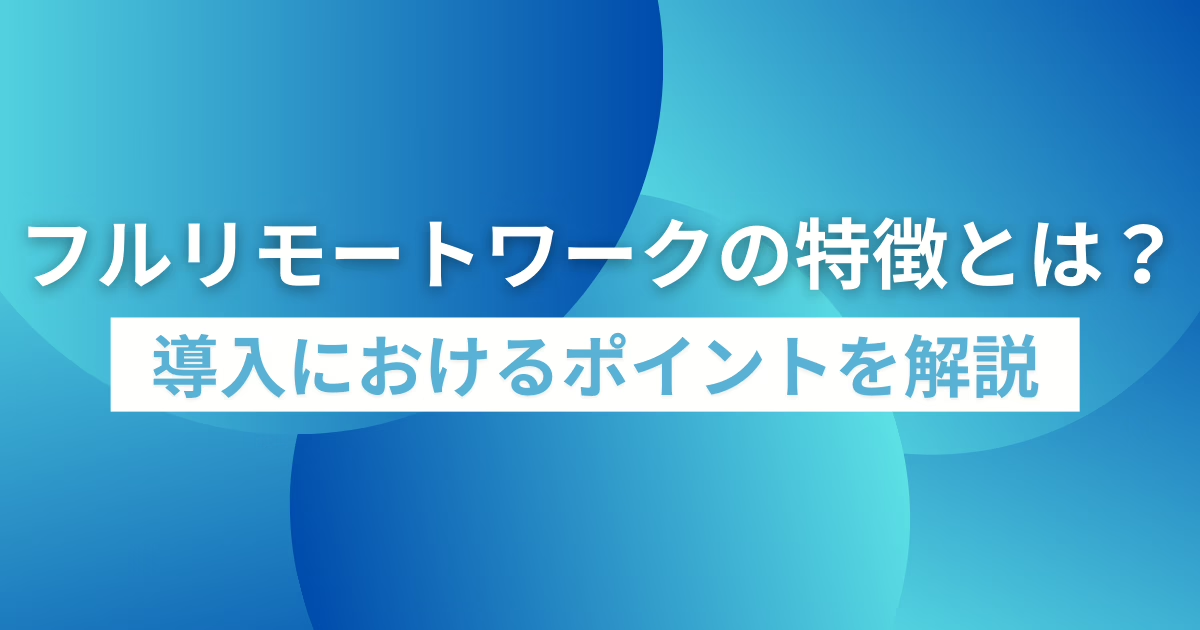リモートワークの普及に合わせて、「フルリモートワーク」の導入も進んでいます。フルリモートワークは、導入することで企業に大きな影響を与えると期待されています。
本記事ではフルリモートワークの概要とメリット・デメリット、導入時のポイントを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
フルリモートワークとは?
そもそも、フルリモートワークとは、どのような働き方を指す単語なのでしょうか。ここでは、概要やリモートワークとの違いについてみていきます。
業務の全てをリモートワーク化すること
フルリモートワークとは、企業内の全業務をリモートワークで行えるようにすることを指します。つまり、全従業員が社外にいても、業務が継続できる状態です。
フルリモートワークを推進している企業の中には、オフィスが不要となり、すでにオフィスを契約解除してしまっている企業も存在します。
フルリモートワークとリモートワークの違い
一般的なリモートワークとフルリモートワークの大きな違いは、「出社の必要性」にあります。
簡単に言えば、リモートワークをメインとしていても、何らかの理由で出社しなければならないケースがある企業は、フルリモートワークとはいえません。
フルリモートワークは出社を不要にし、オフィスに出向く従業員を完全にゼロとしていることが何よりも大きな特徴です。その結果、物理的に距離が離れた場所で過ごすことも可能となり、離島や海外など離れた場所から仕事をしている従業員もいます。
今後フルリモートワークは増える?
フルリモートワークは自由度が高いとして人気のある働き方となっています。そこで、気になるのが「今後フルリモートワークの企業が増えていくか」という点です。
フルリモートワークの会社は多くの従業員に需要がある
リモートワークが普及しつつある昨今、今後もリモートで働きたいと考える従業員は多いです。そのため、多くの従業員に需要のある働き方だといえるでしょう。
SELF株式会社が2022年に実施した、同社の提供するスマホアプリ調査によれば、47.7%が通勤よりもリモートワーク希望しているという回答が得られています。(通勤希望は29.7%)
また、日本労働組合総連合会の調査でも同様に、81.8%がリモートワークの継続意向を示しているようです。
つまり、フルリモートワークは多くの従業員が求めている働き方のため、今後も増えていくことが期待できるでしょう。
参照:SELF株式会社 リモートワークに関するアンケート調査
日本労働組合総連合会 テレワークに関する調査2020
フルリモートワークの求人数も増加傾向にある
近年は、フルリモートを前提とした求人も増加傾向にあります。HRogリスト (日経転職版を含む転職系主要6媒体)によると、2021年以降フルリモートの求人件数は右肩上がり状態です。
2020年初には0件だったにもかかわらず、2022年1月には2,500件に迫る勢いがあり、このデータからも、今後フルリモートワークは増加していくと予想できるでしょう。
参照:HRogリスト「フルリモート」と「在宅勤務」を含む求人件数
フルリモートワークのメリット
今後ますます需要が高まることが見込まれているフルリモートワークですが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、フルリモートワークにおける4つのメリットを紹介します。
通勤にかかるコストがゼロになる
フルリモートワークは出社を必要としないため、通勤に時間や費用がかかりません。そのため、通勤手当や出張費などのコストが削減できるほか、従業員の通勤によるストレスも緩和できるでしょう。
そのため、企業・従業員両者にとってメリットのある施策だと言えます。
採用対象を広げられる
フルリモートワークの場合、採用対象が大きく広がります。例えば、会社から遠い場所にいる海外の人材や、田舎暮らしをしている人材、自宅から出ることが難しい人材も採用の対象になります。
また、そういった人材を正社員雇用できるため、優秀な人材を確保しやすい点がメリットだといえるでしょう。
従業員に合った働き方を推奨できる
フルリモートワークの場合、自宅、サテライトオフィス、コワーキングスペースなど、好きな場所で働けるというメリットがあります。
従業員ごとにマッチする働き方を推奨できるため、業務効率化やモチベーションアップにつながり、仕事にやりがいを感じてもらえる可能性が高まります。
オフィスを持たなくても問題なくなる
オフィス不要で会社が運営できる点も、フルリモートワークのメリットだといえます。オフィスを解約したり、都心から離れた家賃の安い場所に移ったりすることで、固定費を削減できます。
また、震災やウィルス蔓延などによって事業の継続性が危ぶまれる場合でも、問題なく会社を運営できる点も魅力といえるでしょう。
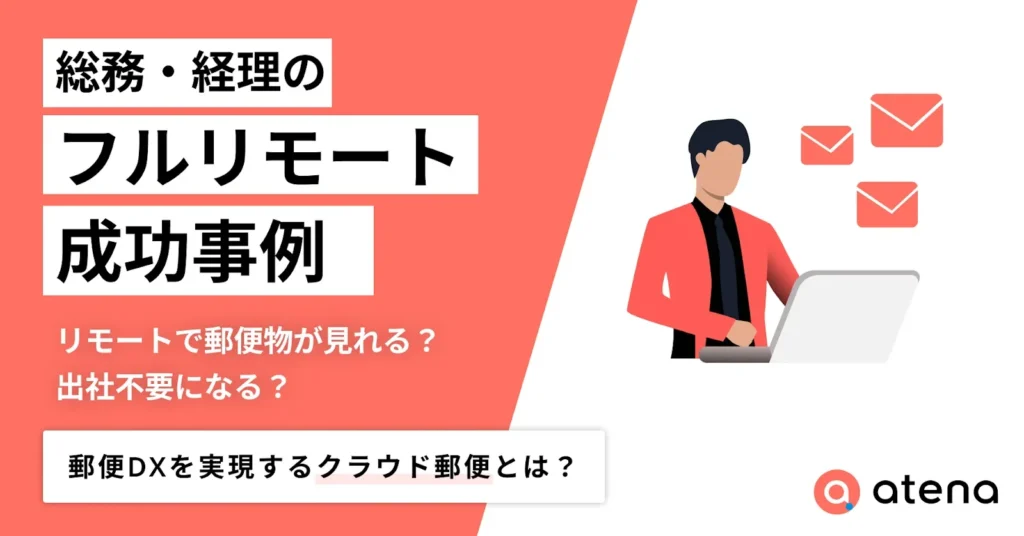
フルリモートワークのデメリット
様々な魅力があるフルリモートワークですが、一方でデメリットが存在することも理解が必要です。ここでは、3つのデメリットについて紹介します。
セキュリティ意識の向上が必須
フルリモートワークでは、セキュリティに関する問題が発展しやすいです。そのため、従業員にはセキュリティ意識を持ってもらう必要があるでしょう。
どこで働いても自由だからこそ、常に覗き見や外部からの侵入に気をつけるとともに、悪意のある攻撃者から情報を取得されないようソフトを導入することも求められます。
評価方法を事前に明確にしなければならない
フルリモートワークの場合、基本的に成果物のクオリティで従業員を評価することになります。これまでの評価制度は通用せず、勤務態度や労働年数などは、評価の対象外になることをあらかじめ示しておくことが大切です。
リモートワークによって勤務態度の評価がなくなることで、従業員からの不満が蓄積する可能性があることは理解しておきましょう。
コミュニケーション不足への対策が必要
フルリモートワークではそれぞれが自由に働ける一方、従業員同士のコミュニケーション不足に陥りやすいという課題があります。
そのため、定期的にオンラインでミーティングしたり、オフライン環境で会話の機会を設けたりするなど、会社側がコミュニケーション不足を解消するためのイベントを開催する必要があるでしょう。
新たな業務が増えてしまい、対応に追われてしまう可能性が出てくるかもしれません。
フルリモートワークが可能な業種について
ここでは、フルリモートワークに適した業種の特徴について紹介します。
オンライン環境のみで仕事が完結する
オンライン環境で仕事が完結する業種はフルリモートワークと相性が良いです。具体的には、パソコン、ネット回線、各種ツールがあることで仕事ができる場合や、仕事の成果や報告についてオンラインで共有できるなら、フルリモートワークを検討した方がよいでしょう。
専用ツールが提供されている仕事
リモートワークを実施するための専用ツールが提供されている業種は、フルリモートワークを導入可能です。
例えば、経理やコールセンター業務などもリモートワーク向けの専用ツールが用意されており、出社不要で仕事が可能となります。
フルリモートワークに必要な環境
フルリモートワークを導入する場合、主に以下のような環境が必要です。
フルリモートワーク中の全従業員を管理できる環境
フルリモートワークにおいては、会社の全従業員の勤怠や進捗を管理できる環境が必要です。直接仕事を確認できないため、労働時間や現在の状況を適宜確認・管理できるツールやソフトを使うことが欠かせません。
大容量の情報を扱えるデータベースの所有
フルリモートワークでは、会社の資料や仕事の情報などを全てペーパーレス化し、データ化する必要があります。そのため、膨大な情報を扱えるデータベースが必要となります。また、安全性確保のためにアクセス権限を設定できるツールの導入も必要です。
フルリモートワーク中の労働状況をマネジメントできる環境
フルリモートワークでは、従業員の労働状況を正確に把握できないという問題点があります。健康面やメンタル面に問題がないことを定期的に確認できるよう、マネジメントできる環境の構築が必要です。
場合によっては、マネジメント専用の部署を立ち上げたり、外部から専門家を雇用したりするなどしてストレスチェックやカウンセリングを行える環境も必要となるでしょう。
まとめ
本記事ではフルリモートワークの概要とメリット・デメリット、導入時のポイントを解説しました。フルリモートワークを導入することで、従業員の負担を減らしつつコストカットにつながるというメリットがあります。一方で、フルリモートワークならではのデメリットも存在するため、それぞれの特徴を理解したうえで、導入に踏み切ることが大切です。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況