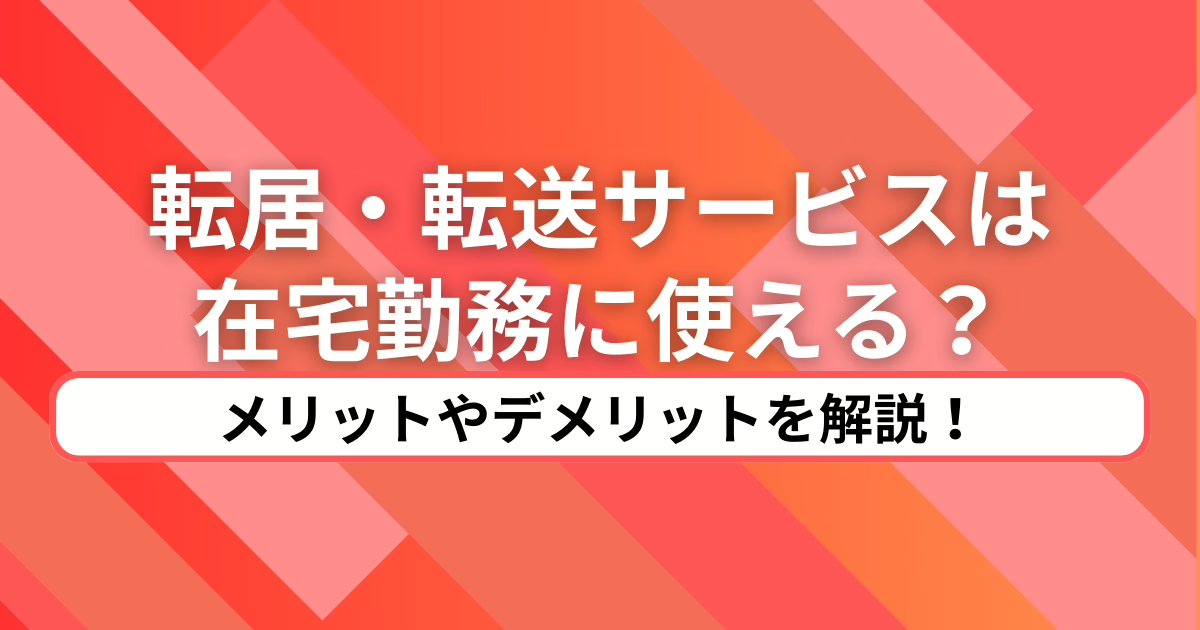コロナ禍が落ち着き、在宅勤務(リモートワーク)からオフィス出社へと回帰する企業が増えている昨今。しかし、完全にリモートワークを廃止するのではなく、ハイブリッド勤務(オフィスと在宅の併用)を取り入れている企業も少なくありません。
出社日が減ると、オフィスに届く郵便物をどう管理するかは依然として課題です。そこで、郵便局の「転居・転送サービス」を使って会社宛の郵便物を在宅ワーカーの自宅へ転送できるのか、また最新事情を踏まえたメリット・デメリットなどを改めて整理してみましょう。
「転居・転送サービス」とは?
郵便局に「転居届」を出すことで、旧住所に届いた郵便物を新住所へ転送してもらえるサービスです。
つまり、東京都中央区八重洲ABCという住所に住んでいた人が、東京都中央区日本橋ABCという住所に引っ越したとすると、八重洲に届いた郵便も日本橋の住所に届けてくれるようになります。
- 1年間有効で、期限前に再度申し込みをすれば延長もできます。
- 対象は普通郵便や書留、レターパック、ゆうパックなど、日本郵便が扱う荷物全般です。
- 法人利用も可能。会社や店舗の移転時にもよく使われます。
本来は引っ越しが前提のサービスですが、在宅勤務などを理由に一時的に別住所へ郵便を転送する使い方も、ケースによっては認められる場合があります。

△ 日本郵便のウェブサイトより
メリットとデメリットは?
メリット
1.手軽に郵便物を違う住所で受け取れるようになる。
2.手続きも簡単でウェブからも手続きができる。
インターネットや郵送で申請を完了できるため、面倒な書類作成は多くありません。
3.幅広い郵便物が転送の対象
普通郵便だけでなく、書留やゆうパックなども基本的には転送されるため、重要書類の見落としを防げます。
デメリット
1.「転送不要」郵便物が受け取れなくなる
銀行などから届く郵便物の一部には「転送不要」と書いて送られてくることがあります。この郵便物は「転居・転送サービスを使っていても、その住所に住んでいない(所在していなければ)返送してほしい」という意思表示になります。そのため、この記載のある郵便物は「転居・転送サービス」を使っている場合は返送となります。

2. 転送は止めることができない
一度出した「転居・転送サービス」は止めることができません。そのため、転送が有効な期間に引っ越した場合は、A(元住所)→B(転送先)→C(さらに新しい住所) のように順々に転送になります。
また、転送を止める場合は A→B→A のように転送先から転送元宛てに逆向きの転居届を出す必要があり、手続きが煩雑になります。
3. リードタイムがかかる
郵便物は転居・転送届の有無に関わらずまずは郵便物に記載されている住所をもとに、「集配郵便局」という近くの配達を担当する郵便局まで運ばれます。
その上で、転居・転送届が出ている場合は転送シールを貼り付け、転送先の集配郵便局へ運ばれ、転送先の住所に配達されます。
仮に北海道から東京へ転居・転送届を出しており、福岡から元の住所である北海道へ郵便物を送ったとすると、福岡→北海道→東京、と郵便物は運ばれます。
このように、通常以上に配達に時間がかかることがあるので注意が必要です。転居・転送届に頼らず、しっかりと元々の発送先住所を変える手続きをすることが大切です。
在宅勤務のために使うことはできる?
在宅勤務のために会社から個人の自宅宛に転送をしている人もいるようです。しかし、本来の用途ではないため、郵便局の担当者の判断で受け付けてもらえないこともあるようです。実際に使うときには、窓口に行ってしっかり確認することをオススメします。
また、在宅勤務で使うときに念頭に入れておかないといけないことは、↑にも書いているように転送は止めることができないということです。自社の在宅勤務は短期的なのか、長期的なのかしっかりと見極めましょう。
転送はかけずに、自宅から郵便物を確認したい場合は「クラウド郵便サービス」を使ってみよう
転送をかけたくない、または転送不要の郵便物も確実に受け取りたい場合は、クラウド郵便サービスの利用を検討してみるのも手段のひとつです。
クラウド郵便サービスとは?
会社の郵便ポストに届いた書類を回収し、スキャン・電子化してくれるサービス。
電子化されたデータはオンライン上で共有できるため、場所を問わずにチェックできます。
「転送不要」の郵便物もまとめて電子化し、重要書類の内容を見逃すことなく確認可能。
例として「atena(アテナ)」などのサービスでは、都心部のオフィス宛てに届いた郵便物を定期的に回収し、データ化して提供。これなら物理的な転送手続きは不要で、紙の郵便物を扱う負担が大きく減ります。

△ atena のサービス画面。届いた郵便物が一覧で見れる。
まとめ
在宅勤務が一時期ほど多くなくても、郵便物管理は依然として課題。週数回の在宅やサテライトオフィスなど、働き方の多様化に合わせた対応が必要です。
郵便局の「転居・転送サービス」は比較的簡単な手続きで利用できますが、「転送不要」郵便物が返送される点や、途中で転送を止められない点には注意が必要です。
本来の用途(住所移転)がはっきりしていないケースでは、郵便局に相談しても認められない可能性があります。
転送不要の郵便物まで確実にカバーし、紙の手間を削減したいのであれば、クラウド郵便サービスという選択肢も検討してみましょう。
アフターコロナでの働き方が定着するにつれ、オフィスの使い方も多様化しています。それぞれの実情に合わせて、最適な郵便管理の方法を選びましょう!