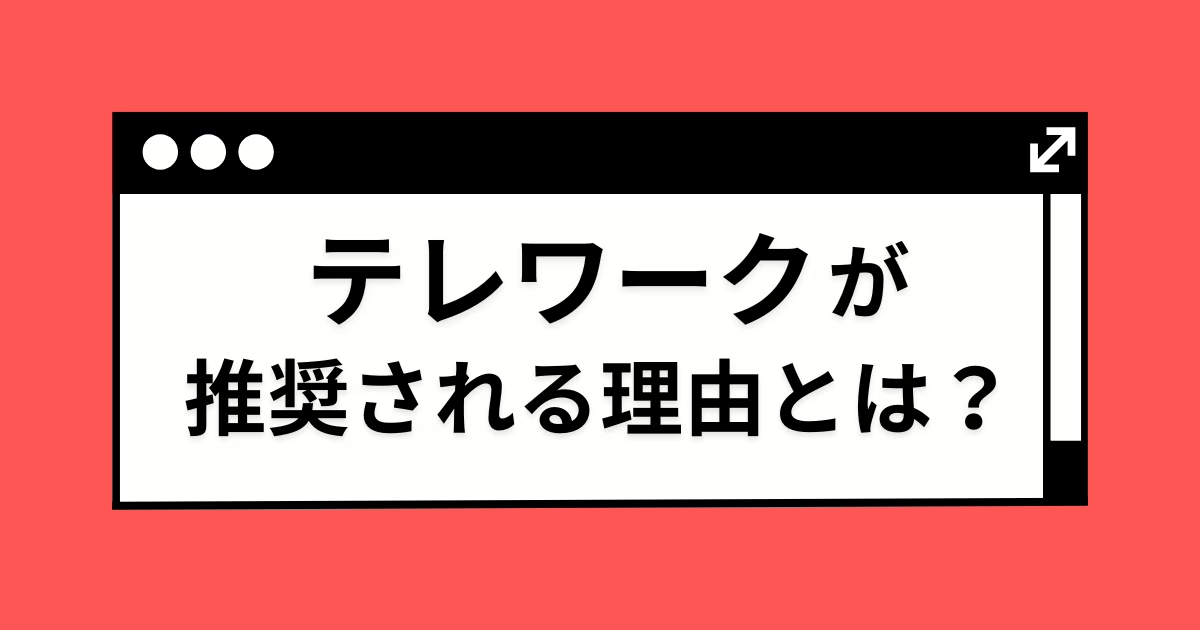近年「テレワーク」という働き方は、新しい労働スタイルとして常識のものとなっています。しかしその一方で、テレワークの導入に踏みきれていない企業が多いことも事実です。
そこで本記事では、テレワークが推奨されている理由や世間の導入状況、テレワークを導入するメリットについて紹介します。テレワーク導入の流れについても解説するため、ぜひお役立てください。
テレワークが推奨される理由
テレワークの導入が推奨される理由はいくつかありますが、その一つが「柔軟な働き方が可能になる」という点です。従来のように通勤時間が必要なくなるため、日常的な負担を削減でき、子育て中の家庭でも仕事に参加しやすいなどのメリットがあります。
テレワークは従業員の負担を減らし、自由な働き方を支援できる方法として、多くの企業に推奨されているのです。
世間のテレワーク導入状況
総務省「令和元年通信利用動向調査の結果」によれば、テレワークを導入したことがある企業は3割程度になっています。一見少ないように感じますが、テレワークを導入している企業が、年々増加していることが伺えるのではないでしょうか。
テレワークを導入することで「業務効率化が実現できる」という認識が一般化しているため、今後も導入を行う企業は増えると予想されます。
テレワークを導入するメリット
テレワークの導入が推奨される背景として、多くのメリットがある点が挙げられます。以下では、テレワークの導入における主なメリットを解説します。
離職率を下げられる
テレワークは、従業員の離職率を下げられるというメリットがあります。近年は「自分に合った働き方がしたい」という従業員が増加し、会社の体制次第では離職してしまうケースが増えているのが現状です。
子育てや介護で通常業務を行うのが難しい従業員などは、働きたくても離職をせざるを得ないこともあるでしょう。テレワークによってそういった従業員の離職率を下げられるため、人材不足を解消できるとともに、人材採用コストの削減にもつながります。
従業員の交通費を削減できる
テレワークの導入は、従業員の交通費を削減できる点もメリットです。交通費は毎月のコストになるため、支給の必要な授業員が多いと大きな出費につながります。
その点、テレワークでは出勤の必要がないため、交通費を丸々削減することが可能です。
遠方から出社している従業員が多い企業は、テレワーク化することで交通費と従業員の通勤時間を削減でき、大きなメリットを得られます。
オフィスコストを削減できる
テレワークによってオフィスに来る人数が減ると、光熱費や備品コストを削減できます。場合によっては現在のフロアを解約して、最小限の大きさを持つ低価格のオフィスへの引っ越しなども検討できるでしょう。
浮いたコストを活用することで、従業員が使いやすいサテライトオフィスを契約するなど、テレワークのための環境構築も進められます。
DX化が進めやすい
テレワークの導入が推奨されている理由の一つに、DX化が進めやすくなることもあります。出社して仕事を進めるスタイルの場合、資料作成などによる印刷コストや、オフィス環境を保つためのさまざまな備品のコストが発生し、現代においては必要のない出費で会社の経済状況を圧迫します。
しかし、多くの企業では上記のようなコストがかかると分かっていても、工程の複雑さや慣れた環境を手放すことを惜しんで、DX化に踏み切れないケースも多いです。そこでテレワークを導入すると、嫌でもあらゆる業務のDX化が必須となるため、強制的に多くの仕事に改革をもたらすことができます。
テレワークによるDX化は結果的に業務効率化にもつながるため、企業における大きなメリットになるでしょう。
優秀な人材を確保しやすい
テレワークはワークライフバランスを整えやすい働き方であるため、現状を変えたい優秀な人材が新たに就職してくれる可能性が高まります。人材の流出を防ぐと同時に、優秀な人材の確保にも期待できる点は、テレワークが推奨される理由になっています。
また、入社を希望しているが、遠方からの出社や引っ越しを懸念して入社を諦めてしまっている人の採用も、積極的に行えることが特徴です。テレワークであればどれだけ自宅と会社が遠くても関係なく仕事を行えるため、あらゆる状況にいる人材を採用対象にできます。
事業の継続性が高い
テレワークの導入は、事業継続性を高められる点でも推奨されています。非常事態や自然災害などが原因となって、仕事の継続が難しくなる場合でも、テレワーク中心の環境が整っていれば事業を継続して行えます。
2020年に発生したコロナウィルスの影響で対面接触が不可能になった際に、事業を畳む企業が続々と現れたことは記憶に新しいでしょう。そういった想定外の事態にも安心して事業を継続できる点が、テレワークのメリットです。

テレワークを導入する際の主な流れ
テレワークを導入する際には、基本となる流れがあります。今後テレワークの導入を検討する際には、以下の手順を参考にしてみてください。
テレワークの対象部署を決める
テレワークを導入するには、まずテレワークを実施する部署を決めます。対面での作業がない、出社する必要がない部署などに対してテレワークを実施して、経過を観察することが最初の段階です。
その他、子育て中の人や疾病によって出社が難しい人などを優先してテレワークの対象とするのも一つの方法となります。休職や退職を防ぐことができるため、テレワークの効果を確認しつつ人材の損失を回避可能です。
テレワークの業務形態を決める
テレワークを導入する際には、具体的な業務形態も決める必要があります。在宅ワーク、サテライトオフィス勤務、レンタルオフィスの契約など、テレワークにはさまざまな業務形態があるのです。
自社にとって一番やりやすい業務形態を選ぶことで、効率的にテレワークを進められます。その他、状況によっては出社日を設定し、テレワークと出社を使い分けることも検討することがポイントです。
労務管理の方法を決める
テレワークにおいては、労務管理の方法をきちんと確立しておくことも重要です。例えば会議やイベント、勤怠管理などをどのように進めるかが、テレワーク導入の鍵になります。
まずはテレワークでも従業員が不自由なく出勤できるよう体制を整え、無駄な負担をかけないように進めていくのが大切です。適切な労務管理を行うためには専用のツールを導入し、テレワークでも担当者が問題なく業務を行える環境を整えることも推奨されます。
社内ルールを見直す
現状の社内ルールがテレワークに向いていないと判断される場合には、根底から見直すことも推奨されます。例えば従来使用していたツールをそのままテレワークに使用するのではなく、より環境に適した新ツールに変更することなどが考えられるでしょう。
その他、従業員にテレワークに必要な設備負担を強いることのないように、特別手当を支給することも検討されます。
テレワークに必要なツールを導入する
テレワークを実施する際には、多くのツールが必要になります。クラウド管理システム、Web会議システム、コミュニケーションツール、その他自社の業務に関するツールの導入が求められるでしょう。
ツールは従業員が使いやすいものになるように、比較検討しながら慎重に選定するのがポイントです。
テレワークに関わる研修を行う
テレワークの導入時には、従業員に向けて研修を行うことも推奨されます。会社にとってだけでなく、従業員にとってもテレワークによる労働ははじめての経験です。そのため実際にテレワークに踏みきる前に、従業員に対して研修を実施して、反応を確認しておく必要があるでしょう。
研修の際には会社のルールやツールの活用方法などを伝達し、実際にテレワークが行われたときに問題が出ないように備えます。それと同時に、トラブルが発生したときの問い合わせ先もあらかじめ伝えて、従業員に負担をかけない体勢を作るのが重要です。
テレワークは推奨されるが課題もある
テレワークの導入は多くの企業に推奨されていますが、解決が難しい課題もたくさん残っているのが現状です。そのためただ流れに乗ってテレワークを導入すると、業務効率の低下や従業員のストレス増加など、多くのマイナス要素を発生させるリスクがあるでしょう。
テレワークにおいては、明確に準備すべき環境や最適なルールがまだ確立されていないため、適宜自社で最適なルールを設けることが重要です。さまざまな企業の事例を参考にしたり、いろいろなツールを試しに導入したりして、自社にとっての最高のテレワーク環境を模索しましょう。
まとめ
テレワークは多くの企業に導入が推奨されるほど、さまざまなメリットを持つ次世代の働き方です。しかし、その一方で導入時にはデメリットやリスクもあるため、事前に詳細を確認したうえで導入の準備を進めてください。
テレワーク導入時には、郵便物に関する対応が一つの課題になり得ます。「atena」はテレワーク環境においても、郵便物をメールのように管理できるシステムです。この機会にツールの一つとして導入をご検討ください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、
便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。