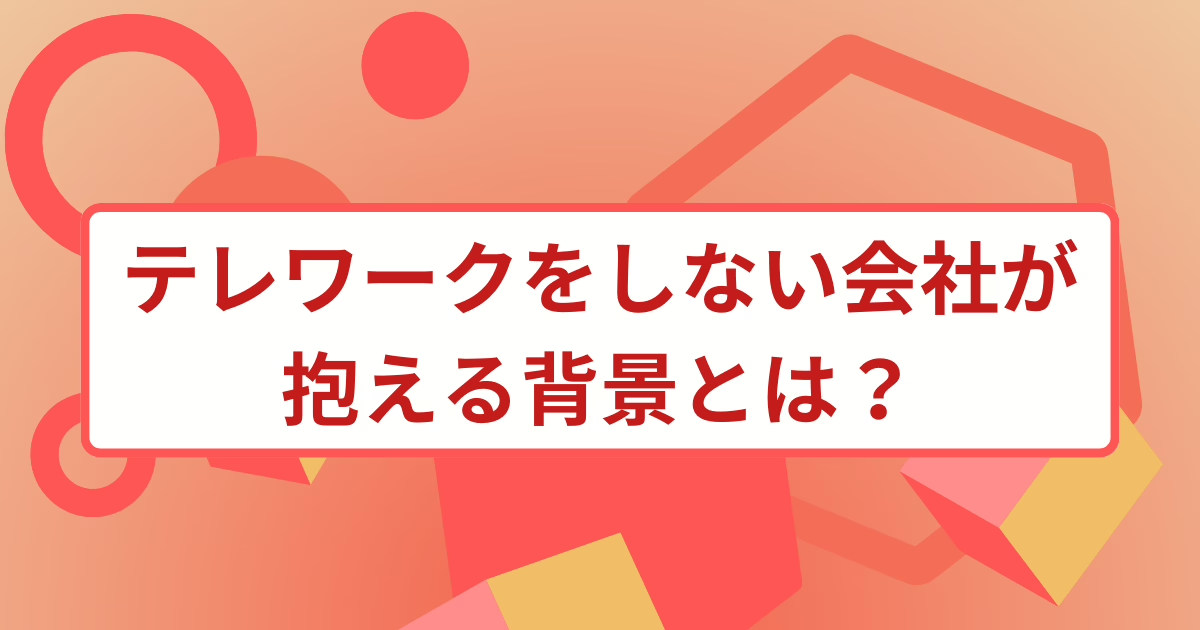郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークは日本企業にも浸透していますが、いまだ導入しない会社も珍しくありません。テレワークをしない会社には、何らかの理由や背景があり、それらが導入を阻んでいるというケースが多いです。
本記事ではテレワークをしない会社の特徴や理由の紹介、解決方法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
テレワークをしない会社は多い
近年、テレワークという働き方が世間に認知されるようになってきました。ところが、現在でもテレワークを実施している企業は少なく、未だ大幅に普及しているとはいえないのが現状です。
総務省が実施した、令和3年「テレワークの実施状況」によると、コロナウィルスの緊急事態宣言時には17.6%から56.4%に上昇している一方で、その後は下降し、平行線をたどっています。
また、30人以上の従業員がいる東京都内の会社において、テレワークを行っている会社は62.5%に過ぎないというデータも出ています。
会社がテレワークをしない理由
テレワークを導入しない会社には、さまざまな理由があります。ここでは、よくあるテレワークを実施しない理由についてみていきましょう。
テレワークを支援する余裕がない
テレワークを実施する場合、従業員ごとにパソコンを支給するなど、テレワーク環境でも仕事ができる設備が必要となります。
しかし、道具を導入するためには大幅にコストが発生します。特に中小企業の場合、業績に余裕がなく、テレワークを実施できないという選択肢を取る企業も存在しているようです。
機密情報を取り扱う業務が多い
会社の業務上機密情報を取り扱う機会が多いと、テレワークの導入はリスクになります。例えば、テレワーク中に従業員がパソコンを紛失したり、無線Wi-Fiに接続したことによって機密情報が流出したりすれば大問題となり、場合によっては顧客に迷惑をかけてしまうケースがあるでしょう。
そういった問題を避けるために、そもそもテレワークをしない判断を下す会社も多いです。
テレワーク中のマネジメントノウハウがない
テレワークの勤怠管理や業務の進捗管理など、マネジメントノウハウがないことも理由として挙げられます。
適切なマネジメントができないと「従業員が仕事をサボるのでは?」という点を問題視し、テレワークの導入を躊躇してしまう経営者は多いようです。
「テレワークよりも出社した方が良い」という固定概念がある
歴史の古い会社であるほど、「出社によってモチベーションが上がる」「対面で仕事をする方が効率が良い」といった、固定概念を持っているケースが多いです。
このように、テレワークを軽視する意見が会社上層部によって提示されると、そこが壁となり、導入に踏み切れないというケースが発生します。
緊急事態のときだけ必要と考えている
テレワークは定着させるものではなく、万が一の手段として用意すべきという意見を持つ会社もあります。
確かにテレワークには、緊急時も事業を進められるというメリットがありますが、「緊急事態のときにだけテレワークを実施する」というスタンスで会社が運営される場合、普段からテレワークをメインにした業務ができないケースも多いでしょう。
会社の事業内容がテレワーク向きではない
そもそも、会社の事業内容によっては、テレワークに向いていないこともあります。会社の備品や書類を頻繁に使ったり、直接取引先に出向くことを前提としていたりする場合、テレワーク化が困難になることもあるでしょう。
出社を優先したがる従業員がいる
「出社しないと仕事を評価されない」「テレワークだと出世できない」という考えを持っている従業員もいます。そういった従業員が会社に存在すれば、テレワークを進めることが難しくなるでしょう。
場合によっては、従業員がテレワークを拒否し、会社に浸透しないという可能性もあります。
テレワークに1度失敗している
緊急事態宣言の際、テレワークを1度は導入してみたが、成果を得られなかったという会社もあります。このような場合、「テレワークでは成果が出せない」という認識が強くなり、再び導入する必要がないと判断されてしまうのです。

テレワークをしない企業のリスクについて
テレワークには働き方を改善するという背景があるため、導入しない場合、会社にとってリスクが発生するケースもあります。ここでは、テレワークを実施しないことで発生するリスクについて紹介します。
テレワークができる会社に従業員を引き抜かれる可能性がある
テレワークの働き方に魅力を感じる従業員が多いことは事実です。場合によっては、テレワークが既に浸透している会社に転職する意向を示す従業員もいるでしょう。
テレワークを進めたいという要望を放置していると、離職率が上昇することもあるため、注意が必要です。
テレワークを主流とした会社と取引が難しくなる
働き方改革が実施されている現代では、テレワークを実施していない企業は時代に合っていないと考えられるケースも多いです。
場合によっては、テレワークを主軸にしている会社との取引が難しくなり、契約解消に発展する可能性があります。また、直接対面したいと考える自社とテレワークによるインターネット通話を希望している相手企業で、意見の食い違いが起き、破談になる可能性も否めません。
今後テレワークを主流にする企業が増えた場合、取引できる会社が絞られてしまうリスクもあるため、テレワークにも対応できるよう準備を進めることが大切です。
テレワークをしない会社を変える方法
テレワークを実施しないと考えている会社を変えるためには、どのようにすべきでしょうか。ここでは、テレワークの導入を働きかける5つの方法を紹介します。
テレワーク専用の環境を整備する
まずは、必要なツールや職場環境を整備することが、テレワーク導入の第一歩となります。
少しのツールとパソコン、通信環境さえあれば簡易的にでも実施できるため、テレワークに必要なものが少ないにもかかわらず、得られる恩恵が大きいことを伝えることが大切です。
従業員にテレワークに必要なアイテムを提供する
従業員に対してテレワークに必要なアイテムを提供することも、推進を促す1つの方法です。
具体的には、専用のソフトが入ったパソコンを導入したり、サテライトオフィスを構えたりすることで、テレワークに対する認識が少しずつ変わっていくかもしれません。
テレワークのメリットを伝える
そもそもテレワークのメリットを会社の上層部や従業員が理解できていない場合、実施は難しいでしょう。そのため、まずは総務などが主導となってテレワークのメリットをまとめ、伝えることから始めましょう。
その上で、テレワークを実施したい従業員が増えたかを改めてヒアリングし、上層部・従業員に周知していくことが大切です。
フレックスタイム制など労働環境の改善を進める
フレックスタイム制など新たな働き方を導入することが、結果としてテレワーク導入につながる可能性につながります。
自由な働き方を実現しやすい環境を整えれば、テレワークにも注目が集まり、導入したいという意見が増えてくるでしょう。
テレワーク中に出社しなければならない理由をピックアップする
テレワーク中でも、場合によっては出社が必要になるケースがあります。そういった問題を懸念し、テレワークの導入に踏み切れないケースがあります。
例えば、出社する日を順番に設定したり、週に1度だけ全員が出社するなど、対策を設けることでテレワークを実施しやすくなります。
郵便物の管理で出社を余儀なくされているなら「atena」の利用がおすすめです。
テレワークをしない会社に将来性はある?
ここまで、テレワークをしない理由などを紹介しましたが、テレワークをしない会社に将来性はあるのでしょうか。
自社の人気が落ち込む可能性がある
社会全体でテレワークを含めた働き方改革は進んでいます。そのため、テレワークをしない会社は人気が落ちることも考えられるでしょう。
先にも挙げた通り、離職率が増えたり、新規で従業員を確保しづらくなったりする可能性があるため、可能な限りテレワークの導入に踏み切った方が良いといえます。
モチベーションの低下や業務の効率を低下させる恐れもある
テレワークが普及すれば、より便利な専用ツールや環境が充実することが予想されます。
場合によっては出社メインの会社よりも、テレワーク中心の会社の方が従業員が働きやすくなり、モチベーションが上がったり、業務効率化が進んだりする可能性があるでしょう。出社メインの会社は、時代に取り残されてしまう可能性があるというのが実情です。
まとめ
本記事では、テレワークをしない会社の特徴や理由の紹介や解決方法について解説しました。テレワークを導入することで、従業員のモチベーションを維持するなどさまざまなメリットがあります。本記事の内容も参考に、テレワークの導入も検討してみてください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況