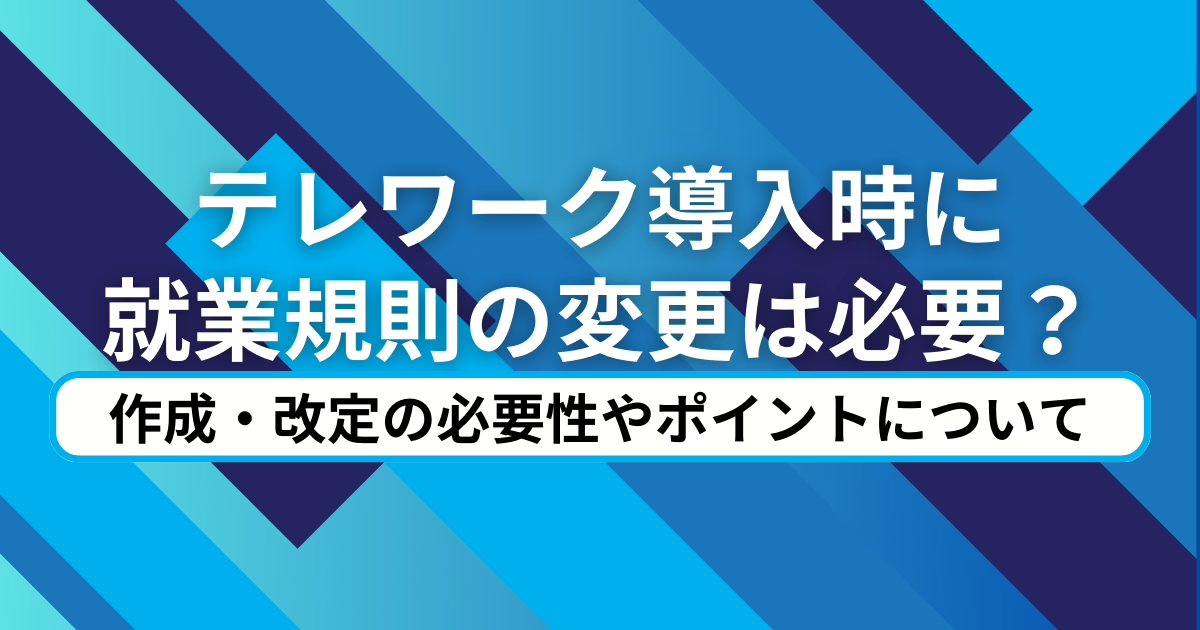郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークを実施する際には、さまざまなルールの作成が必要です。就業規則の変更および新規作成も、テレワークの導入時に求められる作業となるでしょう。
本記事ではテレワークの導入時における就業規則の必要性と、作成・改定のポイントを解説します。
テレワークの実施時には就業規則の作成・改定が必要?
テレワークを実施する場合、現在の就業規則の見直しや変更は必要となるのでしょうか。以下では、テレワークにおいて就業規則の作成や改定が必要なのかについて解説します。
テレワークを実施するなら就業規則の作成・改定は必要
テレワークを実施する場合、就業規則を新たに作成・改定しなければならないケースがあります。
対象となる従業員や業務上のルールなどを、テレワーク専用の形で明確にすることは必要不可欠です。そのため、基本的にテレワークを実施するのなら、就業規則の見直しが求められるでしょう。
通常業務と労働時間や労働条件が同じ場合には変更不要
一方で、通常業務とテレワークの労働時間・労働条件が変わらない場合には、就業規則の変更は不要です。厚生労働省の「テレワークモデル就業規則〜作成の手引き」によると、「通常勤務とテレワーク勤務において労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができます」となっています。
しかし、テレワークの際には始業・終業時間が変わったり、通勤手当の代わりに在宅勤務手当を支給して賃金の計算方法が変化したりするケースが多いです。通常業務と時間や条件が異なることがほとんどなので、就業規則の作成や変更は基本的に必要になると考えておくと良いでしょう。
従来の就業規則とは別に作成することがおすすめ
テレワークの就業規則は、従来の就業規則とは別に新規で作成が可能です。現在使用している就業規則を変更する場合、内容全体を見直さなければならないため手間と時間がかかります。
テレワーク用の就業規則を別で作成してしまえば、一から必要な要素だけを導入できるため、比較的簡単に作業が進められるでしょう。
就業規則の作成方法
就業規則の作成方法には、いくつかのポイントがあります。実際に作成することを想定して、以下のポイントをチェックしてみてください。
労働者の過半数を代表する者の意見書が必要
就業規則の作成時には、労働者の過半数で組織された労働組合か、過半数を代表する人の意見書が必要となります。会社側の都合のみで、テレワーク用の就業規則を作ることはできません。
就業規則の内容についてよく話し合い、労働者との間に溝を作らないように注意するのがポイントです。
労働者にとって合理的な内容でなければならない
就業規則を作成・改定する際には、内容が労働者にとって合理的なものでなければなりません。労働者(従業員)にとって不合理かつ不利益となる内容の場合には、作成や改定が認められないケースもあるでしょう。
テレワークをする従業員の視点に立ち、意図せず不合理な内容を構築しないように気を遣う必要があります。
テレワークの就業規則で定めるべき項目
テレワーク用の就業規則を作成する際には、定めるべき項目があります。以下では、テレワークの就業規則に取り入れるべき項目を解説します。
テレワークの定義
テレワーク用の就業規則では、「テレワークの定義」を明確にする必要があります。自社におけるテレワークの内容を具体的に定義し、言語化して就業規則に記載しなければなりません。
在宅勤務、サテライトオフィス勤務など、テレワークの種類ごとに定義を整える必要もあります。
テレワーク勤務を行う対象者
テレワーク用の就業規則には、実際にテレワーク業務を担当する対象者を指定する必要もあります。全労働者を対象にするだけでなく、職種や家庭内の事情(介護や育児など)で条件をつけることも可能です。
全ての業務をテレワーク化することが難しい場合には、まず特定の従業員のみを対象にした就業規則を作ることが考えられます。
テレワーク中の服務規律
テレワーク用の就業規則には、業務中の服務規律も設定します。例えばセキュリティ上のルールや秘密保持義務などを定義して、従業員に守るよう指導する必要があるでしょう。
既に自社の就業規則にセキュリティガイドラインがある場合、そのまま内容を流用することも可能です。
一から服務規律を作成する場合、総務省の「テレワークセキュリティガイドライン」が参考にできます。
テレワークにおける労働時間制
就業規則には、テレワークにおける労働時間を定義しなければなりません。始業時間や終業時間、休憩の時間や具体的な方法などを決めて、従業員が全員同じ条件で働けるようにします。
「フレックスタイム制」「裁量労働時間制」「事業場外みなし労働時間制」など、テレワーク用に労働スタイルを新たに採用することも可能です。
テレワークの賃金や手当
テレワーク用の就業規則作成時には、賃金や手当の設定も必要です。都道府県ごとの最低賃金はテレワークでも適用されるため、基本的な金額に変更はありません。
そもそもテレワーク業務への移行を理由に、基本給を減額することはできないとされています。また、通勤手当や固定残業手当などがある場合、テレワーク用に「在宅勤務手当」の新規規定を設けるといった対応も必要です。
テレワークに関する費用負担
テレワークを実施する場合、さまざまなコストが新たに発生します。そのため就業規則で、テレワーク中に必要な費用を会社側がどの程度負担するのか定めておく必要があるのです。
例えば自宅の通信費や光熱費、備品の購入費などを負担することが多くなっています。費用負担の項目では、請求方法や限度額も決めておくことがポイントです。
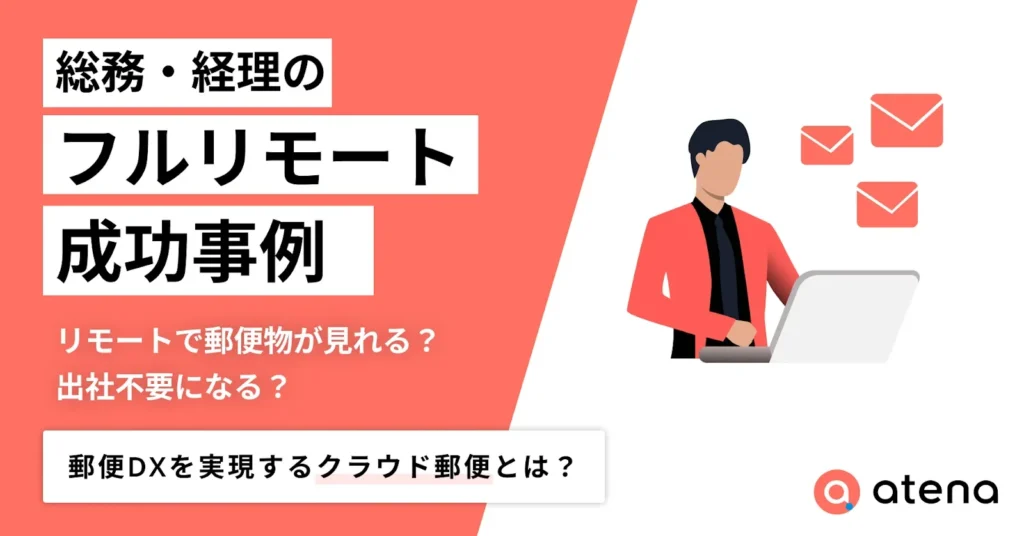
テレワークの就業規則を作成・改定する場合のポイント
テレワークの就業規則を作成・改定する際には、いくつかのポイントや注意点があります。以下を参考に、把握するべきポイントをチェックしてみてください。
テレワークでも労働法を遵守する必要がある
テレワークの就業規則でも、労働法は遵守しなければなりません。例えば「テレワーク中の労働時間を正確に把握できないから、時間外労働の賃金を払わない」といった規定を作ることは、不可能となっています。
必ず労働法を把握したうえで、テレワークならではの働き方に合わせたルールを作ることがポイントです。
「事業場外みなし労働時間制」は適応できない可能性がある
「事業場外みなし労働時間制」は、テレワークに対して適応できないケースが多い点に注意が必要です。事業場外みなし労働時間制とは、労働時間の正確な算定が難しい場合に、算定義務を免除して「特定時間に労働をした」とみなせる制度を指します。
テレワークは基本的にネットで会社と接続するため、事実上いつでも管理者からの指示を受け取れてしまう状態にあります。そのため「事業場外で業務を行い、労働時間の算定が困難かつ会社の具体的な指揮監督が及ばない」という、事業場外みなし労働時間制の条件を満たせないことが多いのです。
テレワークでの業務を強制にはできない
テレワーク業務は、就業規則によって強制ができません。労働者の意思を尊重して、必ず選択できるようにすることが必要です。
会社は労働者の就業場所を決める権利がありますが、在宅およびテレワークでの勤務を強制的に命じることはできないため注意しましょう。
テレワークの就業規則の作成後にすべきこと
テレワークの就業規則の作成後には、いくつかやるべきことがあります。以下では、就業規則の作成後にすべきことについて解説します。
労働基準監督署へ届け出る
テレワークの就業規則を作成したら、労働基準監督署に提出する必要があります。就業規則、届出書、意見書を2部ずつ準備し、提出と保存が行えるようにしましょう。
提出方法は窓口と郵送のほか、電子媒体や電子申請などが可能です。
就業規則の変更を従業員へ周知する
就業規則の作成や変更を行った際には、その内容を従業員全員に周知しなければなりません。社内の見やすい場所に掲示したり、書面で交付したり、常時確認できる媒体に記録して従業員が自由に閲覧できるようにしたりすることが必要です。
テレワークをスムーズに進めるためには、従業員への周知を徹底し、必要に応じて研修などを行うことが検討されます。
まとめ
テレワークを導入する際には、就業規則の作成や改定が必要です。就業規則を新規作成する場合にはさまざまな下準備が求められるので、この機会に基本的な方法や注意点を確認してみてください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、
郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。