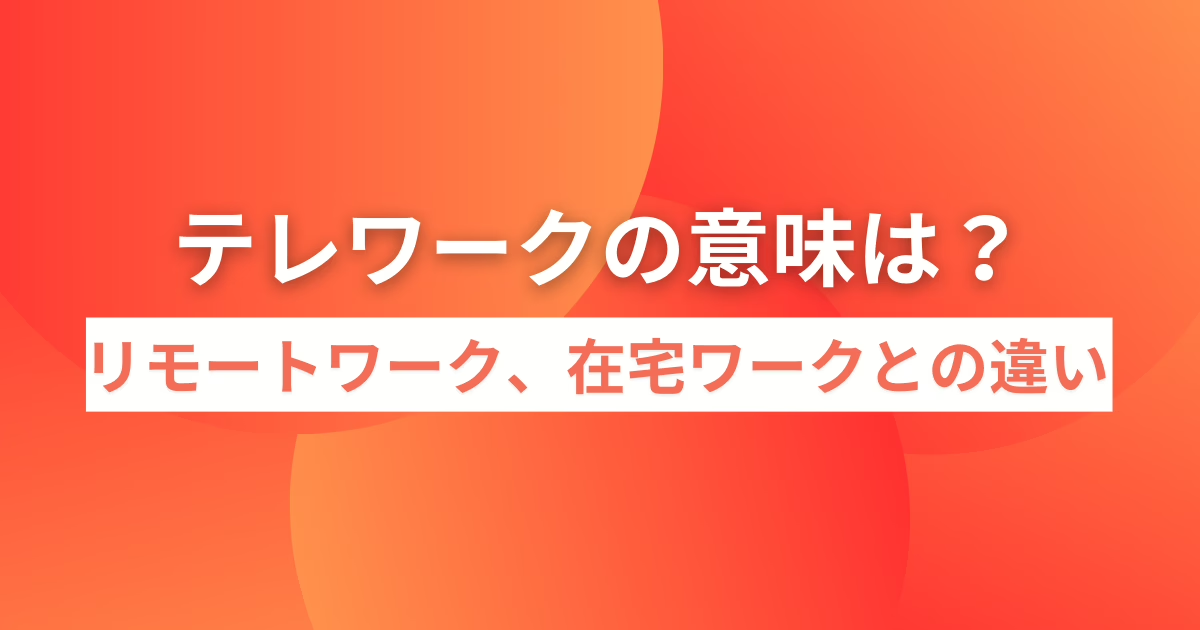郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークとは、「在宅ワークやリモートワークと同じ位置づけ」だと解釈している方もいるのではないでしょうか。しかし、テレワーク・リモートワーク・在宅ワークの意味や定義は、厳密には少々異なります。
本記事では、テレワークの意味や、テレワークの3つの労働形態、導入する意味について紹介します。また、導入する際に注意点も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
「テレワーク」とは
テレワークとは、ギリシャ語で「離れた場所」を意味する「tele」と、「働く」という意味を持つ「work」から生まれた造語です。一般的にはICTなどを活用し、従業員が会社に出社することなく働ける環境および労働スタイルを意味します。
テレワークは勤務形態によって、在宅ワーク、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務といった形で呼び分けられています。それぞれ働き方や仕事をする場所が変わりますが、基本的には会社に行かずに業務を行うテレワークのスタイルが採用されているのが特徴です。
テレワークが生まれた理由
テレワークはもともと、大気汚染や石油ショックなどの影響で、出社ができなくなった際に生まれた労働方法といわれています。一方で、日本でのテレワークの普及は当時の理由と異なり、産休・育休の従業員でも仕事を継続できるように、雇用機会均等を目指して導入を進めたことがきっかけです。
現代においてテレワークは、従業員の労働負担を解消するための施策としても機能し、多くの企業で採用されています。
テレワークが導入されたタイミング
テレワークが導入されたタイミングは、1970年ごろと言われています。最初はアメリカ・ロサンゼルスなどではじまり、徐々に世界に普及していきました。
日本では一足遅れ、1984年に日本電気(NEC)でテレワークが導入されたのが最初の事例です。
リモートワークとテレワークの違い
リモートワークとは、「remote=遠隔・遠い」と「work=働く」を組み合わせた造語です。テレワークと違い、リモートワークは日本で使われるようになってからまだ歴史が浅く、明確な定義がありません。
そのため、リモートワークとテレワークは、同様の意味で用いられることが多いのが特徴です。テレワークもリモートワークも、「会社から離れた場所で仕事をする」という意味を持つため、基本的にはどちらの言葉を用いても問題ありません。
テレワークに属する3種類の労働形態とは
先に紹介した通り、テレワークは3種類の労働形態に分けられています。ここでは、それぞれの労働形態の詳細を解説します。
在宅勤務
テレワークの中でも、主に従業員の自宅で作業をするスタイルを「在宅ワーク」または「在宅勤務」と呼びます。カフェや別のオフィスなどで作業をする場合には、在宅ワークおよび在宅勤務という言葉は使われません。
在宅勤務は通勤の時間が省略できるなどのメリットがある一方で、労働に適した環境が整備できないというデメリットもあるのが特徴です。環境整備が不十分だと従業員の生産性を下げることもあるため、新たな課題を生み出すケースもあります。
モバイルワーク
カフェ、ホテル、飛行機、電車など、さまざまな環境下で働くテレワークのスタイルを「モバイルワーク」と呼びます。隙間時間を活用して働けるため、効率的に業務を進められるのがメリットです。
一方で、パソコンの覗き見による情報漏洩の対策など、モバイルワークならではの課題もあります。
サテライトオフィス勤務
サテライトオフィス勤務とは、テレワークを想定して設置された専用スペースで働くことを意味します。
Wi-Fiやデスクなど、業務に役立つ環境が整備されている「働くための空間」を従業員が活用できる点が特徴です。
テレワークでも生産性を保ったまま働きやすく、セキュリティ面も安心できる一方で、導入・利用費用がかかるなどのデメリットがあります。
テレワークを導入する意味
テレワークを導入することには、多くの意味およびメリットがあります。以下を参考に、テレワークを導入する意味について考えてみましょう。
通勤時間から解放される
テレワークの導入には、従業員を通勤時間から解放するという意味があります。毎日出社する必要がなくなることで、満員電車での移動などに感じるストレスの改善につながるでしょう。
日本における平均通勤時間は、往復で1時間19分程度といわれています。通勤時間がなくなることで、従業員が毎日1時間程度の余裕を持てるようになるため、ワークライフバランス向上につながる点がメリットです。
オフィスの家賃など経費を削減できる
テレワークの導入には、オフィスの家賃や電気代など、固定費の削減につながる点でも意味があります。プリンター代など設備の利用コストも削減できるため、経費削減を実現可能です。
オフィスにおける無駄なコストを大幅に削減できるため、その分を従業員に還元してモチベーションを高めたり、新しい設備の投資に充てたりできます。
企業イメージがUPする
テレワークの導入は、会社に先進的な印象を与える結果にもつながります。現代では多様な働き方を容認していることが印象アップになるケースも多く、会社の知名度を高めることにもなり得るでしょう。
テレワークによって場所に捉われない人材確保も可能になるため、遠方や海外に住む従業員なども採用対象にできます。
事業継続性が高い
テレワークを常駐化すれば、事業継続性を高めることも可能です。例えば災害が起きてオフィスに問題が発生しても、テレワークをしている従業員が多ければ事業を中断せずに済みます。
業務がストップすることによって、損害を発生させるリスクを軽減できるのもテレワークの特徴です。
優秀な人材を確保しやすい
テレワークの導入には、優秀な人材を確保しやすくなるメリットもあります。働く場所を選ばないため、仮に優秀な人材が会社に出社できない場所に住んでいても、問題なく採用を決断可能です。
また、介護や育児などによって出社が難しくなってしまった人材の離職を、テレワークによって防ぐこともできます。
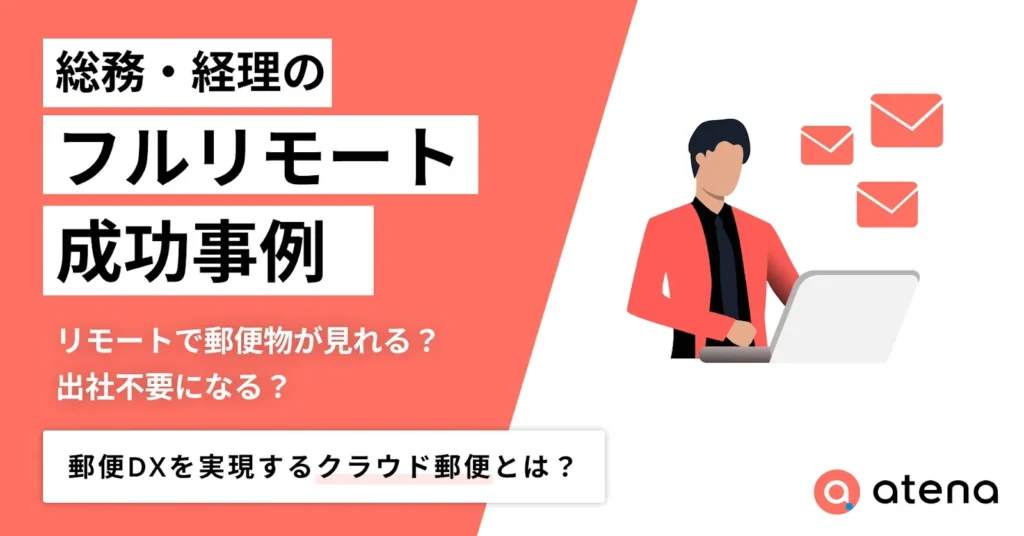
テレワーク導入の注意点
テレワークの導入時には、いくつか注意すべき点があります。以下を参考に、注意点を事前に把握しておきましょう。
福利厚生の見直し
テレワークを導入する際には、福利厚生の制度を見直す必要があります。例えば通勤手当は出社しなくなることによって不要となるため、廃止および縮小が検討されるでしょう。
一方で在宅勤務をする従業員に対して、電気代や通信費を在宅勤務手当として支給するかどうか考える必要が出てきます。企業によっては働く場所に制限がなくなることから、家賃補助の内容や条件を見直さなければならない場合もあるでしょう。
ツール導入で生産性を向上する
テレワークの導入時には、生産性を向上させるためのツールの利用が欠かせません。例えばGoogle MeetやZoomのような、コミュニケーションとタスク管理が行えるツールを導入し、効率化および生産性向上を目指すことが考えられます。
テレワークに必要なツールの導入は、従業員同士のコミュニケーションやプロジェクト進行を円滑に進める基盤になります。自社の業務内容や環境に合ったツールを選定する必要があるため、まずはさまざまなツール・サービスを試してみるのが重要です。
テレワークを導入する際のポイント
テレワークの導入においては、事前にいくつかのポイントを理解しておくことも必要です。ここでは、テレワークの導入におけるポイントを解説します。
業務可視化ツールを導入する
テレワークの導入時には、勤怠状況や業務状況を可視化できるタスク管理ツールを利用するのがポイントです。現在の業務状況を可視化することで、誰がどのタスクを担当しているのか、進行状況が順調なのかといった点を判断できます。
従業員ごとの業務成果や勤務状況を管理できるため、人事評価に活用できるのもメリットです。
テレワーク環境を整える
テレワークを実施する際には、業務に支障が出ない環境を整えるのもポイントです。
業務をスムーズに行えるスペックを持つパソコンなど、仕事で問題なく使えるデバイスを用意しましょう。会社側でデバイスを支給しない場合には、Wi-Fiの通信速度など必要なスペック基準を設けて、従業員に情報提供をすることが環境整備につながります。
セキュリティ対策を講じる
テレワークの実施時において、セキュリティ対策は必須の項目となります。情報漏洩などのトラブルを防ぐために、セキュリティ要件を満たしたデバイスや通信回線を利用することが基本です。
従業員にもセキュリティの重要性を説明し、「保護されていない回線には接続しない」など注意を促す必要があります。テレワーク中の安全性を高めるのであれば、専用のデバイスを準備したり、具体的なセキュリティ要件を規定したりといった対策も考えられるでしょう。
まとめ
テレワークとは、「tele」と「work」を合わせて造られた造語です。その意味を正確に理解することで、テレワーク本来の必要性や重要性が見えてくるため、この機会に基本的な概要を確認してみてください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。
東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、
従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。
最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし
自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。
atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。詳しくはコチラをご覧ください。