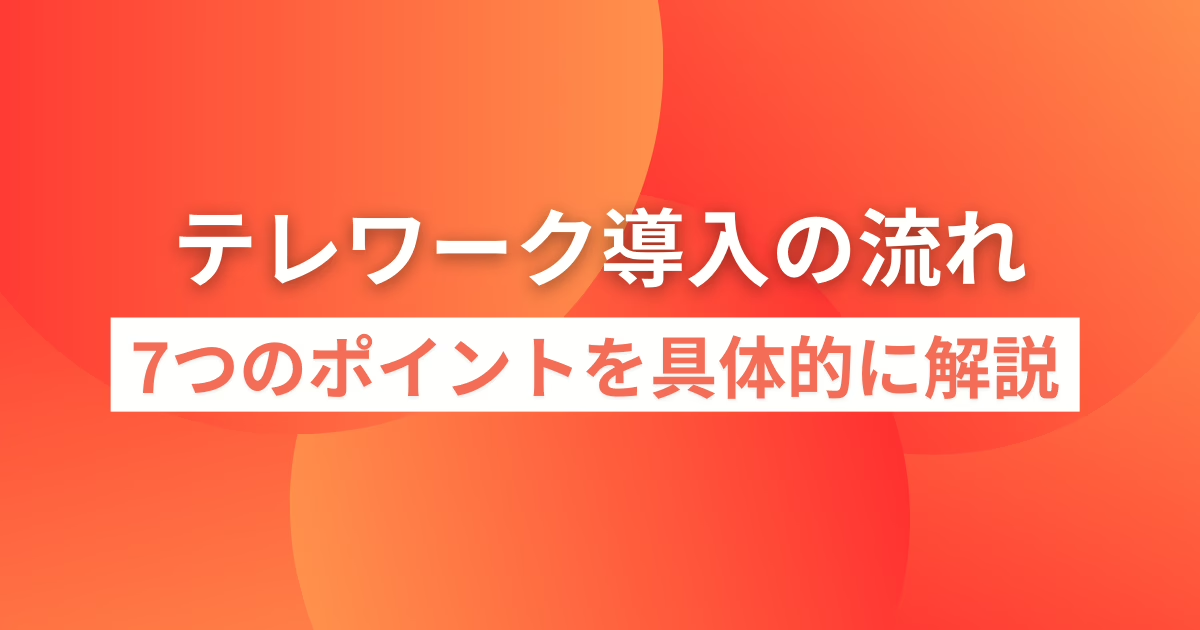郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
せっかく費用をかけたテレワークの導入が失敗に終わってしまうという、災難に見舞われる可能性があります。
本記事では、テレワーク導入におけるポイントを紹介するとともに、テレワーク導入に必要な手順も紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
テレワーク導入におけるポイント
テレワークを導入する際、さまざまなポイントに注意して導入を進める必要があります。ここでは、3つのポイントを紹介します。
タスクの進捗を共有できるようにする
チームで業務を行う場合、テレワークだとタスクの進捗を確認しづらいという難点があります。状況がわからないと上司がフォローしたり、仲間の仕事を代わりに受けたりすることができず、不安を感じる方も多いでしょう。
そのため、ビジネスチャットを活用したり、タスクの進捗を共有できるシステムを導入したりすることが大切です。そういったツールを導入することで、タスク進捗を素早く共有できるようになります。
自宅で業務ができる環境を整える
テレワークを導入する際、よく問題になるのが、従業員の作業環境です。会社と異なり、自宅の場合は業務を効率的に行えない環境である可能性があります。ネットワークの速度が遅い、パソコンのスペックが望む性能ではない、といったこともあるでしょう。
そのため、企業がテレワークを導入する際は、従業員全員が同じように業務を行えるよう、環境を整備し、導入を促進することが大切です。また、場合によってはテレワーク用の物品を支給することも必要になります。
密に情報共有を行う
テレワークの最大のデメリットは、情報の共有がしづらいという点です。コミュニケーション不足に頭を抱える企業担当者も多いでしょう。
そのため、業務で知り得た情報を逐一共有できる環境を整えることが大切です。ビジネスチャットや会議システム、進捗状況・スケジュール確認アプリなど、さまざまな情報共有アプリを臨機応変に活用しましょう。
テレワーク導入の手順①:導入の目的を明確にする
テレワーク導入には7つの手順を踏まえる必要があります。
まず、テレワーク導入の前には、導入する目的や導入によって得られる効果を考えてから導入しましょう。テレワークには、コスト削減や生産性の向上など、さまざまなメリットがありますが、どの要素を優先するかによって必要なツール、最適な環境が異なるためです。
まずは、自社にとって最適な環境を構築できるよう、テレワークにおけるコスト削減や生産性の向上などを考え、導入準備を行いましょう。
テレワーク導入の手順②:社内の状況を確認する
次に、自社でテレワーク導入に必要な設備や制度がどのくらい用意されているのか、現状把握することが大切です。すでに導入されているツールを再度契約してしまうと、不必要なツールを再度導入することになり、コストや時間の無駄になってしまいます。
まずは社内のツール利用状況、従業員がどのように仕事をしているかなどを事前に把握し、テレワーク導入に必要な道具を揃える基準を明確にしましょう。
また、自社の制度がテレワーク環境に不向きで、少し問題あると感じた場合には、その時点で最適な方法に変更することが大切です。
テレワーク導入の手順③:必要な機材やツールの把握
テレワークを導入する際、今後自社に必要な機材やツールを確認することが大切です。ここでは、それらを把握する上で必要な考え方をいくつかご紹介します。
電子化できるものはないかを考える
まずは、なにか電子化できる部分がないか考え、可能であれば導入を検討することが重要です。例えば、文書を紙で印刷して保存しているなら、ツールを導入して電子保存に切り替えるなど、テレワーク環境に備えて電子化を進めましょう。
一括購入したほうがよい機材は購入する
業務上必要な機材がある場合はリストアップし、従業員に事前に周知しておくとよいでしょう。また、業務上必須となるものやまとめて安く購入できるものなど、一括購入したほうがよい機材は会社負担で先に購入しておくこともおすすめです。
一方で、個人で選んだほうが生産性が上がりそうなものは、従業員に選択肢を与えることも効果的でしょう。
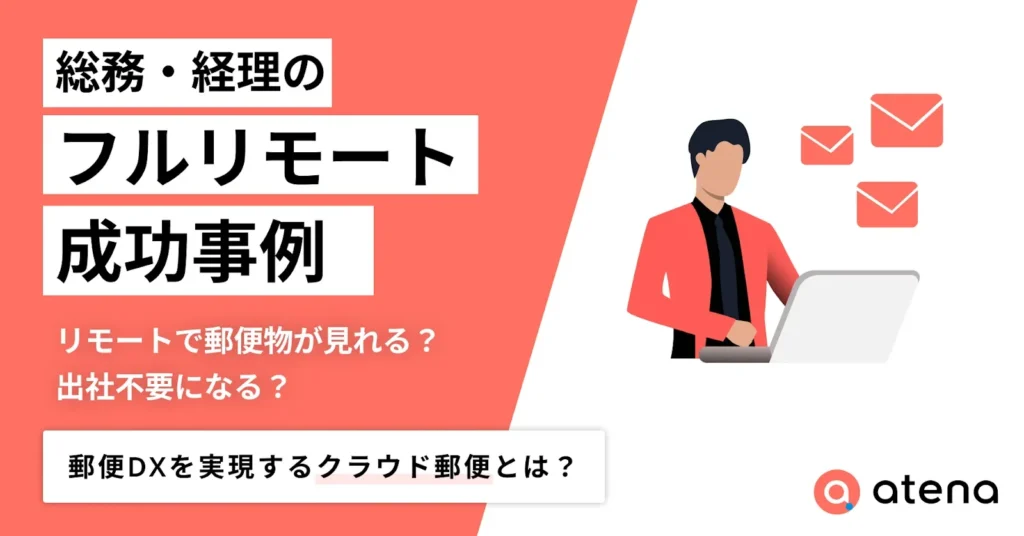
テレワーク導入の手順④:導入にあたってルールを決める
テレワークを導入する場合、どのような頻度でテレワークを行うかなどルールを設ける必要があります。ここでは、ルールの設定方法についてみていきます。
テレワークの頻度を考える
どのくらいの頻度でテレワークを行うべきなのかを考えることは重要です。業務にはテレワークで効率的に行えるものとそうでないものがあり、それらをバランスよく組み合わせなければ、失敗してしまいます。
すべての業務をテレワークで行えそうであれば、完全テレワークにする、一部会社に出勤する必要がある場合は、出勤する曜日を決めるなど、出社頻度のルール作りは欠かせません。
テレワーク規定に即して勤怠管理を見直す
テレワークを導入するにあたって、必ず労働関連法令を順守しましょう。テレワークに関する法令は、主に以下の3つです。
・テレワーク勤務を命じることに関する規定
・テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定
・通信費・情報通信機器などの負担に関する規定
これらのルールに基づいていない場合、会社として大きな問題に発展することもあるため注意しましょう。
教育や研修を通してテレワークのルールを共有する
テレワークを導入する際には、ルールを理解してもらうため従業員への教育が必要です。ルールをしっかりと会社全体に浸透させられれば、業務を一定のクオリティに保てるでしょう。
また、会社で教えたり動画を作成したりしてルールを共有するなど、直接教えるだけではうまく浸透しない内容は、マニュアルに残すことも重要となります。
テレワーク導入の手順⑤:セキュリティ対策やトラブルの対処法を考える
ITツールを選ぶ際にはセキュリティ対策を講じる必要があります。セキュリティ対策を実施しなければ、社内の機密情報が漏れてしまう危険性があるためです。特に、リモートワークの場合は管理者が把握できないため、特に重要な項目になります。
具体的には、社内システムに接続する際にパスワードを入力したり、ログイン用の専用IDカードを配布したりするなどの対策を考え、セキュリティを強化できるようにしましょう。また、トラブル対策ができる部署を用意するなど、トラブルが起こったときにすぐに連絡できる窓口を設けることが大切です。
テレワーク導入の手順⑥:テレワークを実際に導入する
次は、実際に導入を進めます。これまでの手順を踏まえた上で最適なツールやシステムなどを実際に導入してみることで、自社に最適なツールを導入できるでしょう。
試しに導入することが大切
導入前には、複数のツールを試用してみる必要があります。ツールを一気に導入すると、導入後に使いづらさなどの不具合が発生するためです。
特に、ステップ①で設定したテレワーク導入目的を満たしているかを確認しながら、試しにツールを利用してみるとよいでしょう。
テレワーク導入の手順⑦:導入後のPDCAサイクルを回す
テレワークは、導入後も気を抜いてはいけません。導入後には必ずと言ってよいほど問題が生じるためです。
問題が起こったときには面倒くさがらず対処法を考え、PDCAサイクルを回す必要があるでしょう。その際に役立つ基準として、量的基準と質的基準があります。
量的にテレワークを評価する
量的評価とは、数値として出ているものを基準に評価を進める方法のことを指します。具体的には、コスト削減などの数値が改善されていれば、量的に評価が高いといえます。
質的にテレワークを評価する
質的評価は数値にできない情報を評価したものです。コミュニケーションが円滑に取れた、顧客からフィードバックをもらったなどが質的評価となります。
量的評価・質的評価を基準にテレワークの効果を把握すると、導入したツールの問題・良いところが明確になりやすいです。
まとめ
本記事では、テレワーク導入におけるポイントやテレワーク導入に必要な手順を紹介しました。テレワークは適切な手順を踏んで導入すべきです。本記事の内容を参考に、テレワークを導入してみてください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。

引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況