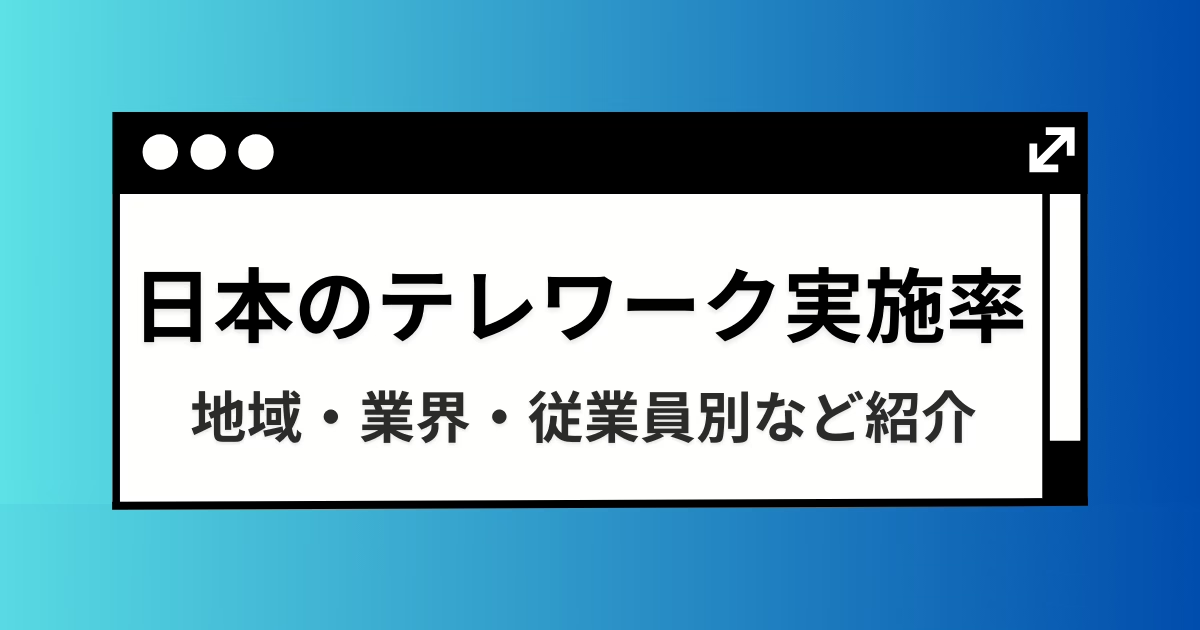郵便物を電子化しいつでもどこでもクラウド上で確認が出来る
クラウド郵便atenaライターチームです。
テレワークを導入している企業は多いです。中には、他社の導入状況が知りたいと考える企業も多いでしょう。
本記事では、テレワークの実施率や導入が伸び悩む原因、解消方法、導入時のポイントなどを詳しく紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
テレワークとは
テレワークは、自宅やカフェなど会社以外の場所で仕事をすることです。遠隔地(tele)と働く(work)を掛け合わせた造語となっており、近年普及してきた働き方です。
厚生労働省のテレワーク推進やコロナウィルス蔓延によって、日本でも近年急速に広がりつつあります。
テレワークの実施率
テレワークが各方面で実施されているということは周知の事実ですが、地域・会社規模・業界において、一体どのくらい実施されているのでしょうか。ここでは、テレワークの実施率を3つの指標に基づいて紹介します。
地域別のテレワーク実施率
国土交通省の「平成29年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果-」によれば、三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県)49.1%、地方都市圏(その他の地域)50.9%という結果になりました。
数値だけ確認すると、地方都市圏の方が多いように感じますが、実際のところ、三大都市圏の地域のみで49.1%もの数値を出していることから、都市圏のテレワーク実施率が高いことが分かります。
参照:平成29年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果の概要-
従業員数別のテレワーク実施率
東京都の調査(スムーズビズ)では、従業員30人以上99人未満企業のテレワーク実施率は50.2%、100〜299人の企業は63.8%、300人以上の企業は73.2%という結果です。この結果から、従業員数が多くなるにつれ、テレワーク実施率が高まることがわかります。
参照:東京都 テレワーク実施率調査結果
業界・業種別のテレワーク実施率
国土交通省の「平成29年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果-」によれば、雇用型では「情報通信業」のテレワーカーの割合が最も高く30%を超えています。次に「学術研究、専門・技術サービス業」が27.0%、他業種は約10〜20%となっており、「宿泊業・飲食業」の7.2%が最も低いという結果が出ました。
また、自営型の場合も「情報通信業」が最も高く40.0%、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」が38.6%。他業種は約 10〜20%台となっており、「農林水産・鉱業」の9.0%が最も低いという結果です。
両調査とも、情報通信業の割合が高いという結果が出ています。
参照:平成29年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果の概要-
テレワーク実施率は全体的に上昇している
地域別のテレワーク実施率の全国調査を見ると、全体的に上昇していることがわかります。つまり、テレワークが実施されている企業は拡大傾向となっています。
一方で、実施割合はほぼ横ばいになっており、普及率が上昇しているわけではありません。
一部の企業がテレワークの実施に踏み切れない理由
テレワークが普及しているのは事実ですが、一部テレワーク導入に踏み切れない企業も少なくないようです。ここでは、テレワークに踏み切れない理由を6つ紹介します。
テレワークに適した仕事がない
テレワークで対応できない仕事がある企業はテレワークに踏み切れません。特に、飲食店や接客業など、人を相手にする業務内容の場合、テレワークの導入は容易ではないでしょう。
これは仕方ないことですが、農林水産業などの一部企業がテレワークを導入していることを考えると、工夫次第で導入できる企業もあるといえます。
情報漏洩が心配
IT企業など膨大なデータを保有している企業の場合、情報漏洩のリスクを心配する声もあります。そのような企業は情報漏洩を懸念し、テレワークを導入することが難しい傾向です。
ただし、自宅作業を徹底する、セキュリティを守るために必要な機器を導入するなどルールを設けることで、対策は可能でしょう。
業務の進行が難しい
連携して業務を行う場合、進行状況を確認できず導入に踏み切れないケースもあります。例えば、会議を頻繁に行い、進捗を確認するデザインなどの業務においては、内容が複雑でテレワークに対応できないケースもあります。
社内のコミュニケーションが円滑に図れない
社内のコミュニケーションを円滑に図るのが難しい場合は、テレワークに向いていません。従業員の自宅にテレワーク向けの環境が整っておらず、そもそもツールを使いこなせないケースもあるでしょう。仕事が思うように進まないことを懸念している企業もあります。
電子化が進んでいない
電子システムを一切導入していない企業もあります。そのような企業がテレワークを実施することは難しいといえるでしょう。
このような場合、シンプルで操作性が高いDXツールを活用したり、DXに強い人材を雇ったりすることで、導入が推進される場合があります。
費用がかかる
テレワークを導入する際、ツールや従業員の自宅環境整備費用などコストが発生します。結果的には、オフィスコストを抑えられるためコスト削減につながることもありますが、資金不足に悩まされており初期費用を支払えない企業は、テレワークの導入が容易ではないでしょう。
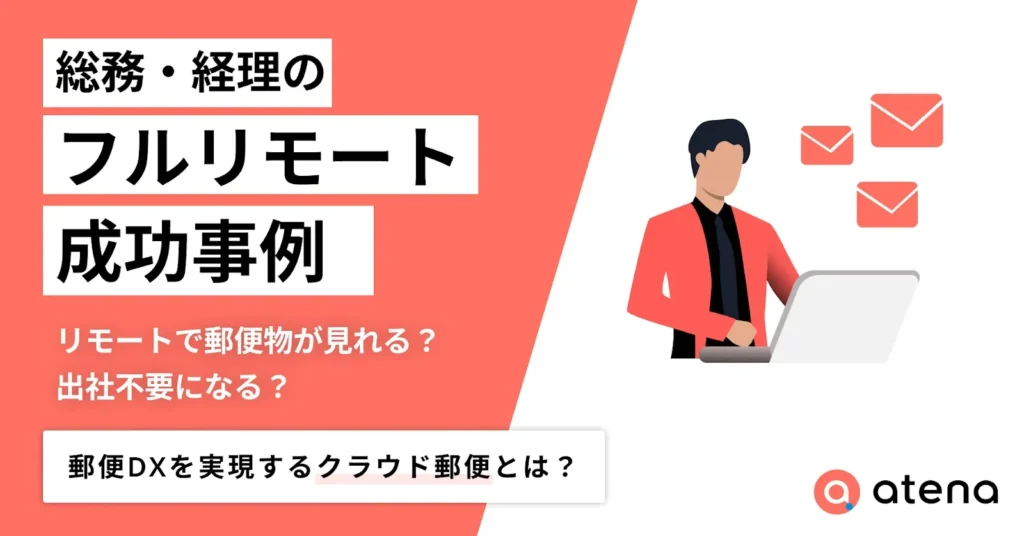
テレワーク実施の原因を解消する方法
テレワーク実施においてはさまざまな原因が生じます。しかし、導入することでコストカットや従業員の働き方改革につながるのも事実です。ここでは、テレワークのさまざまな原因に対処する3つの方法を見ていきます。
仕事内容ごとにテレワークの向き・不向きを選別する
仕事内容によってはテレワークが不可能なこともあります。そのような場合には、テレワークが可能・不可能を業務内容ごとに選別することで、どの業務をリモート化すればよいかがわかります。
例えば、ミーティングなど実際に会った方がよい場合は実際に出社して業務を行い、自分個人で完結する業務はリモート化するなど、自社の業務に合わせて向き・不向きを選別しましょう。
テレワークに向けてルールを整える
テレワーク環境向けのルールをマニュアル化し、いつでも確認できる状況を作ることも1つの方法です。トラブルが起こったときに連絡できる手段や、どのように対処すべきかといった内容を全て記載することで、テレワーク導入における問題を事前に対処できるようになります。
テレワーク導入時に補助金・助成金を使う
テレワークの導入コストに頭を抱えているなら補助金・助成金を使用することも方法です。補助金・助成金を利用すれば、テレワーク導入が有利に進みます。ただし、補助金・助成金は新しく現れたり、すぐに消えたりしてしまうため、タイミングをしっかりと理解しておくことが大切です。
テレワークを実施する際のポイント
テレワークを実施する際、主に2つのポイントを意識して導入を進めるとよいでしょう。ここでは、主な2つのポイントを紹介します。
業務効率化できるツールを導入する
テレワークにおいては、ツール導入が必要不可欠です。そのため、複数のツールを比較し、自社に最適なツールを探しながらツールを導入しましょう。
勤怠管理ツールや業務に必要なツールなどを自社目線で揃えることで、業務がより効率的に進むようになります。
少しの期間試しに導入してみる
テレワークに使うツール選定ができたら、ツールのお試し期間を使って少しだけ社内でテレワークを進めてみるとよいでしょう。いきなりツールを購入してしまうと、業務上どこに問題が生じるかなどを把握できず、テレワーク導入に弊害が起きてしまうためです。
ただし、慎重になりすぎるとタイミングを逃すため素早い判断が必要となります。「少し効率は落ちるが、安定して業務を進められそう」という場合には、思い切って導入することがおすすめです。
まとめ
本記事では、テレワークの実施率や導入が伸び悩む原因、解消方法、導入時のポイントなどを紹介してきました。テレワークを導入している企業は増えましたが、その一方でうまく導入に踏み切れていない企業も存在します。本記事の内容をもとに補助金・助成金などを利用すると、導入を進めやすくなるでしょう。ぜひ、参考にしてみてください。
テレワークを推進・導入する企業は増えてきました。東京都の調査によると都内企業ではテレワーク実施率が56.4%となり、従業員数300名以上の企業では73.2%と高い水準となっています。
企業単位ではテレワークが進む一方で、部署単位では総務・経理などのバックオフィス関連は
「交代制で週1日以上出社している」と回答した方が62.4%と今だに出社率が高いことが分かります。最も出社の要因となっているのが「郵便物の対応」です。
弊社が運営するクラウド郵便「atena」は郵便物のための出社をなくし自宅などからメールのように郵便物を確認できるクラウド郵便サービスです。atenaを導⼊することでバックオフィスの方々もテレワークを実現し、郵便物のための出社が不要になります。
詳しくはコチラをご覧ください。

引用:【2022年・まん延防止期間】テレワーク実施率含む働き方に関する調査結果(東京都内勤務の正社員対象)
東京産業労働省 都内企業のテレワーク実施状況